Published by 学会事務局 on 09 5月 2020
【和文誌】『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編 掲載のお知らせ
生物工学会誌で好評連載中の「生物工学基礎講座-バイオよもやま話-」を学生実験の補助教材として利用しやすいように整理して掲載しました。⇒『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編はこちら
Published by 学会事務局 on 09 5月 2020
生物工学会誌で好評連載中の「生物工学基礎講座-バイオよもやま話-」を学生実験の補助教材として利用しやすいように整理して掲載しました。⇒『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編はこちら
Published by 学会事務局 on 08 5月 2020
「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―」は、生物工学会誌の名物企画として好評をいただいています。実験の原理を知りたい若手研究者や学生に向けて、多くの執筆者の先生方に、発酵・醸造・プロセスエンジニアリング技術など、バイオテクノロジーの次代継承に役立つ知識を詳細に解説していただいています。内容は多岐にわたりますが、本ページでは、特に学生実験の補助教材として利用することを前提にトピックを整理してみました。
若手研究者や学生の皆様が、最新の技術だけでなく生物工学の基礎についても理解・習熟する一助として、研究・教育の場でご活用いただければ幸いです。内容は随時更新いたしますので、お気づきの点やご意見などがあれば事務局()にお知らせください。(和文誌編集委員会)
| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |
|---|---|---|
| 遠心分離について ―遠心分離の基礎から超遠心や密度勾配遠心まで― | 内山 進 | 95-5-262 |
| 緩衝液のイロハ | 加藤 太一郎 | 95-8-476 |
| 糖の定量法 | 北村 進一 中屋 慎 | 90–12–790 |
| 顕微鏡は微生物学の基本 Ⅰ | 田中 隆明 | 90–2–84 |
| 顕微鏡は微生物学の基本 II ―顕微鏡によるバイオイメージング― | 尾碕 一穂 | 90–3–122 |
| 脂肪酸分析は意外と簡単 | 市原 謙一 | 90–2–89 |
| ザ・ヒストリー・オブ・クロマトグラフィー | 岡澤 敦司 | 93-6-345 |
| 実は奥が深いpH測定とその制御 | 尾島 由紘 田谷 正仁 | 94-4-198 |
| 何から始めよう 微生物の同定-細菌・アーキア編- | 浜田 盛之 鈴木 健一朗 | 89–12–744 |
| 微生物名ってどうやって決まるの? | 森 浩二 中川 恭好 | 89–6–336 |
| 培地の成分知っていますか? | 駒 大輔 山中 勇人 森芳 邦彦 大本 貴士 | 89–4–195 |
| 意外に知らない分子量と質量の単位の違い | 吉野 健一 | 91-8-464 |
| 統計にだまされるな | 川瀬 雅也 | 91-4-205 |
| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |
|---|---|---|
| エタノール沈殿あれこれ | 春木 満 | 89–5–254 |
| いまさら聞けないプラスミド抽出法の原理 | 高木 昌宏 | 89–9–544 |
| どうして核酸は変性するの? | 藤原 伸介 | 89–4–200 |
| 制限酵素物語~発見からゲノム編集まで | 川上 文清 | 94-3-124 |
| 酵母ベクターの種類と歴史 | 大橋 貴生 | 95-1-16 |
| pUCプラスミドにまつわるエトセトラ | 橋本 義輝 | 89–10–609 |
| シームレスクローニング法 ~古典的な制限酵素とDNAリガーゼを用いないクローニング~ | 本橋 健 | 96-1-20 |
| 3番目のDNA連結反応NHEJ:なんとほんとにeasyじゃん | 赤田 倫治 中村 美紀子 星田 尚司 | 98-1-23 |
| 大腸菌の菌株の特徴を知ろう | 林 勇樹 | 94-1-15 |
| 大腸菌を宿主とした異種タンパク質高発現のイロハ | 東端 啓貴 | 91–2–96 |
| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |
|---|---|---|
| 細胞の増殖を捉える―計測法から比速度算出まで― | 小西 正朗 堀内 淳一 | 93-3-149 |
| 流加培養による酵母の生産 | 長森 英二 並木 健 | 93-1-32 |
| 培養細胞への酸素供給 | 黒澤 尋 | 91-11-646 |
| フラスコ培養とジャー培養の違い | 岸本 通雅 堀内 淳一 熊田 陽一 | 90–4–192 |
Published by 学会事務局 on 27 4月 2020
2020年5月21日(木)東京農工大学 新1号館グリーンホールにおいて開催を予定しておりました2020年度日本生物工学会総会は、新型コロナウイルス感染拡大の防止、皆様の安全を最優先する観点から物理的なご出席は要請しないこととしインターネットによる議決権の行使により実施することにしました。
<2020年度日本生物工学会総会>
日時:2020年5月21日(木)13:00~
場所:日本生物工学会 事務局(大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学工学部内)
関連行事として予定しておりました第25回生物工学懇話会、懇親会、また5月22日(金)のSBJシンポジウムは開催を中止いたします。参加をご予定いただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
関連記事:
Published by 学会事務局 on 23 4月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 6(2020年6月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 学会事務局 on 23 4月 2020
生物工学会誌 第98巻 第4号
横田 篤
先般、岡山大学で開催された本会第71回大会において、本部企画シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)を生物工学にどう活用するか」に出席した。時宜を得た企画であった。6人の演者からの話題提供とパネルディスカッションがあり、筆者はバイオエコノミーに関わる後半を聴講した。巻頭言執筆を依頼されて久しく色々と理由をつけて逃げ回っていたが、これを題材として責を果たしたい。
話題の元となった「バイオ戦略2019」は、2019年6月に統合イノベーション戦略推進会議において策定された国の方針である。ただし、バイオの技術面ではなく、バイオを活用して国内外の人材や投資を呼び込んでビジネスを創出し、持続可能で健康に暮らせる社会を作るための戦略である.類似の方針策定が欧州連合や米国、ASEAN諸国で先行する中、我が国は後塵を拝する形になっている.国の持続可能な社会の形成に対する取組みが十分でなかったからであろう。
シンポジウムを聴講して、筆者は本戦略に上滑り感を禁じ得ず、絵に描いた餅になるのでは、との懸念を抱いた。この戦略の立案やシンポジウムに関わられた方々が大学の現状を十分ご存知ないと思ったからである。そこで、戦略の実施を担うべき大学の立場から、シンポジウム終了間際に次のような意見を申し上げた:
「法人化後15年を経た国立大学は弊疲し、大学の教育研究の持続性が大きく損なわれている。戦略の実現にはこうした状況の改善が必要なのに、これに関する言及はどなたからもなく残念だった。それぞれのお立場で正しいことを述べられたとは思うが、大学としては遠い話に聞こえる。」
大学の教育研究機能の健全化は「バイオ戦略2019」の大前提である。このことに関連して、戦略を読んで気になった点を3点あげる。
日本生物工学会にはこの戦略にどう向き合うかが問われている。学会は戦略を鵜呑みにすることなく、その実現を阻む要因を明確にして、打開のために関係方面に提言や働きかけを行う役割を担う必要があるだろう。この度のシンポジウムがその契機となることを願っている。
著者紹介 北海道大学大学院農学研究院(教授)、日本生物工学会監事
Published by 学会事務局 on 23 4月 2020
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 22 4月 2020
こちらでは、生物工学会誌第98巻(2020年)掲載の特集記事一覧(PDF)をご覧いただけます。
⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら
第98巻|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|
Published by 支部:関西 on 20 4月 2020
2020年7月3日(金)に大阪工業大学にて開催予定の第117回醗酵学懇話会につきまして、この度延期することを決定いたしました。
毎年夏と冬に開催してきた恒例行事ですので、何とか開催できないかこれまで関西支部企画委員を中心に検討してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という観点から延期を決定いたしました。開催時期については、 国内の状況等を鑑みながら決定したいと思いますが、新型コロナウイルス感染症が終息し、皆様が安心して参加できる時期に改めて開催したいと思います。
参加をご検討して下さった皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力を下さいますようお願い申し上げます。
関西支部企画委員一同
人生100年時代を迎えた今、私たちの食や健康、運動への意識は益々高まりつつあります。標記例会では、生物工学に加え、食品・醸造科学や健康科学など、様々な分野をまたぐ研究者の方にユニークな研究をご紹介いただき、生物工学が私たちのQOL向上に果たす役割を議論します。多数のご参加をお待ちしています。
13:30~ 受付
14:00~14:05 開会の辞 藤山 和仁(関西支部支部長・大阪大学生物工学国際交流センター)
14:05~14:35
「酵素合成技術を利用した新規糖質素材の開発とスポーツ栄養素材としての特徴」
………渡邊 浩史(江崎グリコ株式会社 健康科学研究所)
江崎グリコでは、自社開発の酵素を用いて、特徴的な性質を持つ糖質素材を開発してきた。近年われわれは、消化速度が緩やかで、かつ難消化性成分が少ない(ほぼ完全に消化される)という特徴を持つ新しいデキストリン、遅消化性環状デキストリン『クラスター デキストリン®-SE』を開発した。クラスター デキストリン-SEは、健康を害するリスクが示唆されている急激な血糖値上昇(血糖スパイク)や過剰なインスリン分泌(インスリンスパイク)を起こしにくく、健康影響の少ない糖質栄養として期待される。本講演では、この新しい糖質素材の酵素合成反応や機能性、用途について紹介する。特に、スポーツ栄養素材用途として、クラスター デキストリン-SEを運動中に摂取した時、脂肪代謝抑制を起こしにくく、脂肪と糖の両方をエネルギーとして利用可能であることが呼気ガス分析より示唆されており、この結果についても紹介する。
14:35~15:05
「卵麹と熟成卵黄の開発」………中川 拓郎(株式会社樋口松之助商店)
卵は様々な調理法が存在する一方でその栄養成分はそのまま利用しており、微生物を利用した伝統的な食品は無い。そこで、麹菌を用いて卵の麹化を試みた。様々な卵素材と麹菌を組み合わせ、原料処理を工夫する事で卵と麹菌のみを用いる卵麹の製造方法を開発したので紹介する。
米麹や酵素剤を用いて卵黄液を消化した場合には卵黄本来のおいしさを損なう呈味成分が発生し、卵黄のおいしさが喪失した。一方で、卵麹を用いた『熟成卵黄』の風味は、卵黄らしさを残したままコクやうまみが増強され特有のおいしさが付与されていた。遊離アミノ酸量は未処理の卵黄の5倍増加しており、熟成香や甘い香りの揮発成分の生成が認められた。
15:05~15:35
「産学連携による新たな醸造製品の開発」………山本 佳宏(京都市産業技術研究所)
産学連携がクローズアップされ、地域産業の活性化においても、さまざまな取組みが行われている.今回、京都市の事例として、地域産業の主体となっている醸造産業への成果事例として、佐々木酒造とともに行った麹を活用した商品開発事例と大手となる黄桜株式会社とともに行った工程改善の取組みについて紹介する.佐々木酒造との連係では京都府立大学の研究成果を統合し、新たな生産システムを作り上げ、醸造飲料をはじめとする各種製品開発を行った.また黄桜との事業では製品評価技術基盤機構、産総研、京都大学、大阪市立大学の研究成果を反映し、製品製造プロセスの高度化につなげている.産学連携は先端バイオ技術を中小企業へローリスク、短時間で導入できる有効な手段となっているが、より有効な活用について議論をお願いしたい。
15:35~15:50 休憩
15:50~16:20
「奈良県で分離・育種したユニークな酵母及びそれらを用いた純米酒の醸造について」
………大橋 正孝(奈良県産業振興総合センター)
昭和50年代をピークとして、清酒の消費量は現在約1/3まで減少している。この状況を打破するために、当センターでは、これまでに、野生酵母から酒造に適した酵母の分離や、特徴のある清酒酵母の育種を行ってきた。今回、奈良県の県花である奈良八重桜の花から分離した「ナラノヤエザクラ酵母」、酒造の神様として多くの信仰を集めている大神(おおみわ)神社の境内に自生していたササユリの花から分離した「山乃かみ酵母」、そして、育種により取得した、細胞内にオルニチンを高生産する「オルニチン蓄積酵母」、これら3種類のユニークな酵母について紹介する。さらに、これら酵母を用いた純米酒の特徴についても、あわせて紹介したい。
16:20~16:50
「元気な骨格筋細胞培養と活性張力評価技術、応用」………長森 英二(大阪工業大学大学院工学研究科)
試験管環境で培養可能なマウス骨格筋細胞を、周期的なパルス電気刺激を加えた環境で長期間培養すると、活発に収縮運動する状態が得られる。この培養骨格筋細胞の収縮力を定量する技術を開発したところ、より生体に近い機能を評価可能なin vitro実験系として製薬メーカー等に好評を得た(Biotechnology and Bioengineering, 106(3), 482-489. (2010))。以来10年、ヒト細胞への適用が課題であったが、解決の糸口が見えつつある。この間、骨格筋は健康長寿を担うキー臓器として認識されるようになり、世の中の注目が高まった。幅広い分野に分散した骨格筋研究者を横糸でつなぐコンソーシアム活動等についても紹介したい。
16:50~17:20
「“腸活”における運動のポテンシャルについて」………横山 久代(大阪市立大学)
腸内細菌の特性は、炎症性腸疾患ならびに肥満や2型糖尿病といった代謝性疾患の発症と関連するだけでなく、気分や意欲などの精神面にも影響を及ぼし、ヒトの健康状態に寄与することが知られている。個人の腸内細菌叢は固定したものではなく、食事などの環境要因によって変化する。実際に臨床の現場でも、腸内環境を整えるために一般に水分や食物線維の摂取とならび、適度な運動が勧められるが、運動そのものがヒトの腸内環境に及ぼす影響については不明な点が多い。
運動はヒトの腸内細菌叢を変化させるのか、そうであれば、どのような運動方法が腸内環境の改善に有効なのかを明らかにするために、今回、健常な高齢女性の腸内細菌叢に対する運動介入効果を運動種目別に検討したため、これまでの知見も交えて紹介する。
17:30~19:00 懇親会(204セミナー室にて)
JR「大阪」駅から徒歩5分、地下鉄御堂筋線「梅田」駅から徒歩5分、地下鉄谷町線「東梅田」駅から徒歩5分、阪急「大阪梅田」駅から徒歩3分、阪神「大阪梅田」駅から徒歩7分
Published by 学会事務局 on 14 4月 2020
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止策のため、日本生物工学会事務局では、4月14日(火)より原則在宅勤務を実施いたします。
平日は、職員若干名が職場勤務しますが、基本的には電話での対応が難しくなりますので、各種お問い合わせについては、なるべく電子メール(info@sbj.or.jp)をご利用くださいますよう、お願いいたします。
ご不便をおかけすると存じますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。通常業務再開の折には、改めてお知らせいたします。
Published by 学会事務局 on 08 4月 2020
2020年4月8日
公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏
2020年5月21日(木)東京農工大学 新1号館グリーンホールにおいて開催を予定しておりました2020年度日本生物工学会総会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響、政府による緊急事態宣言の発出を受けまして、開催の場所、方法を変更させていただきます。総会は大阪千里ライフセンターにおいて、書面・電磁的方法による議決権の行使により開催することを検討し、早期に代議員にお知らせします。
また、関連行事として予定しておりました第25回生物工学懇話会、懇親会は中止いたします。登壇をご予定いただいた講師の先生、ご準備いただいた先生方、参加をご予定いただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。
⇒日本生物工学会総会の開催方法の変更および関連行事の中止について![]()
関連記事:
Published by 学会事務局 on 06 4月 2020
公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏
大会実行委員長 中山 亨
第72回日本生物工学会大会(2020)は2020年9月2日(水)~9月4日(金)東北大学川内北キャンパスにおいて開催の予定です。しかしながら、ご承知の通り新型コロナウイルス感染拡大の影響は日に日に厳しくなっております。このような状況を鑑みまして、講演の申し込み期間を5月13日(水)~6月11日(木)に変更いたしました。4月の申し込みに向けてご準備いただいていた方には申し訳ありませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。
この講演申し込み期間変更に伴って、本大会の要旨集が通常の年の製本の形式とは異なりpdfファイルでの配布になる可能性があることをご承知おきください。
なお、コロナウイルスの感染拡大については、現状、見通しが立たない状況であることから、引き続き、開催の有無、方法について検討し、お知らせ致しますので、大会ホームページ等をご覧いただきますよう、お願いいたします。
以上
♦ 関連記事(重要なお知らせ):
Published by 学会事務局 on 02 4月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 5(2020年5月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 学会事務局 on 02 4月 2020
| 内容 | 開催日 |
|---|---|
| 【協賛行事】日本学術会議公開シンポジウム「植物科学分野における若手キャリアパスの現状と将来」〈大阪〉[開催中止] | 2020.03.21 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「非破壊・非侵襲技術の社会実装」〈東京〉[開催延期] | 2020.03.17 |
| 【協賛行事】熱測定スプリングスクール2020(第84回熱測定講習会)~基礎から応用まで!充実した個別相談であなたの質問へ回答します~〈東京〉[開催中止] | 2020.03.12-2020.03.13 |
| 【協賛行事】第15回理研「バイオものづくり」シンポジウム〈和光市〉[開催延期] | 2020.03.06 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「未病マーカー」〈東京〉[開催延期] | 2020.03.06 |
| 【協賛行事】第1回世界エンジニアリングデイ記念シンポジウム〈東京〉[開催中止] | 2020.03.05 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「最新ネコねこバイオロジー」〈東京〉[開催延期] | 2020.02.28 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「バイオの匠~未来へつなぐ技術伝承」〈東京〉 | 2020.02.21 |
| 【協賛行事】第93回日本細菌学会総会〈名古屋〉 | 2020.02.19-2020.02.21 |
| 【協賛行事】化学工学会東日本支部 第11回ホットな話題の講演会「気液固分散のオペレーションとデザインの現在と未来」〈埼玉〉 | 2020.02.17 |
| 【協賛行事】令和元年度 産総研 材料・化学シンポジウム 『21世紀の化学反応とプロセス ~「橋渡し」の次のSTEPへ:企業連携の拡充に向けて~』〈つくば市〉 | 2020.02.14 |
| 【協賛行事】GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向:講演会&見学会」~連続製造技術と装置設計における品質保証~〈大阪〉 | 2020.02.06-2020.02.07 |
| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会 公開講演会「AI型バイオエンジニアリング ~AIの関わる社会進化論~ 日本が世界で生き残るためのキーテクノロジーを考える」〈東京〉 | 2020.01.31 |
| 【協賛行事】第25回高専シンポジウムin Kurume〈久留米〉 | 2020.01.25 |
| 【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会「もっと光を!!次世代の光が魅せる新しい未来」〈東京〉 | 2020.01.21 |
| 【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会「地震減災と微生物~津波減災、液状化対策、地震波軽減」〈東京〉 | 2020.01.10 |
| 【協賛行事】第32回バイオエンジニアリング講演会〈金沢〉 | 2019.12.20-2019.12.21 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「NITE-NBRCの輝く金塊(菌塊)を掘り起こす!」〈東京〉 | 2019.12.16 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「睡眠改革~眠れればいいの?いや、リズムでしょ!」〈東京〉 | 2019.12.11 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会”「食品のリスクコミュニケーションにおけるメッセージはどのようにあるべきか」〈東京〉 | 2019.12.09 |
| 【協賛行事】第39回水素エネルギー協会大会〈東京〉 | 2019.12.02-2019.12.03 |
| 【後援行事】第7回国際フードファクター会議(ICoFF2019) / 第9回ポリフェノールと健康国際会議(ICPH2019)/ 第12回国際機能性食品学会(ISNFF2019)〈神戸〉 | 2019.11.28-2019.12.05 |
| 【協賛行事】第46回炭素材料学会年会〈岡山〉 | 2019.11.28-2019.11.30 |
| 【協賛行事】INCHEM TOKYO 2019〈千葉市〉 | 2019.11.20-2019.11.22 |
| 【協賛行事】第33回日本吸着学会研究発表会〈名古屋〉 | 2019.11.14-2019.11.15 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「先制医療と革新的検査技術 ~エクソソーム、血中マイクロRNA 、尿中ポルフィリンに着目して~」〈東京〉 | 2019.11.08 |
| 【協賛行事】コロイドおよび界面化学討論会 第70回記念国際会議(Okinawa Colloids 2019) | 2019.11.03-2019.11.08 |
| 【関連行事】第12回 北陸合同バイオシンポジウム〈福井〉《中部支部共催》 | 2019.10.25-2019.10.26 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「遺伝性腫瘍の遺伝子診断と遺伝カウンセリング」〈東京〉 | 2019.10.25 |
| 【協賛行事】第55回熱測定討論会〈大阪〉 | 2019.10.24-2019.10.26 |
| 【後援行事】第88回日本醤油研究発表会〈和歌山〉 | 2019.10.24-2019.10.25 |
| 【協賛行事】第34回日本イオン交換研究発表会〈山梨〉 | 2019.10.24-2019.10.25 |
| 【後援行事】第23回国際バイオハイドロメタラジーシンポジウム〈福岡〉 | 2019.10.20-2019.10.23 |
| 【協賛行事】第36回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2019〈東京〉 | 2019.10.16-2019.10.18 |
| 【協賛行事】19-2 エコマテリアル研究会「機能性バイオベースポリマーの新展開」〈大阪〉 | 2019.10.04 |
| 【協賛行事】第17回高付加価値食品開発のためのフォーラム「食の未来のあり方と持続可能なタンパク質資源について」〈静岡〉 | 2019.09.27-2019.09.28 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会 イブニング懇話会「海外バイオとエコビジネス・勝利の方程式」〈東京〉 | 2019.09.25 |
| 【協賛行事】日本化学会関東支部講演会「プラスチック問題 -資源循環社会に向けての化学からの新たな取り組み」〈東京〉 | 2019.09.13 |
| 【協賛行事】第21回日本感性工学会大会「感性を科学する知性」〈東京〉 | 2019.09.12-2019.09.14 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「バイオ素材百花繚乱14:彩飾賢微の医療・ヘルスケア材料」〈東京〉 | 2019.09.11 |
| 【協賛行事】Marine Biotechnology Conference 2019〈静岡〉 | 2019.09.09-2019.09.13 |
| 【後援行事】JASIS2019〈千葉〉 | 2019.09.04-2019.09.06 |
| 【後援行事】第15回国際好熱菌学会(Thermophiles 2019)〈福岡〉 | 2019.09.02-2019.09.06 |
| 【共催行事】第21回生体触媒化学シンポジウム〈石川県野々市〉 | 2019.08.29-2019.08.30 |
| 【共催行事】第33回日本キチン・キトサン学会大会〈神奈川〉 | 2019.08.28-2019.08.29 |
| 【協賛行事】第32回におい・かおり環境学会〈草津市〉 | 2019.08.27-2019.08.28 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「ゲノム編集技術による植物育種と食品開発のゆくえ」〈東京〉 | 2019.08.22 |
| 【協賛行事】熱測定サマースクール2019(第83回熱測定講習会)~基礎から応用まで!材料・食品・バイオ分野の熱測定ユーザー向け基礎講義&実習~〈東大阪市〉 | 2019.08.20-2019.08.21 |
| 【共催行事】第38回日本糖質学会年会(日本糖質学会創設40周年記念大会)〈名古屋〉 | 2019.08.19-2019.08.21 |
| 【協賛行事】極限環境生物学会 第20回シンポジウム〈東京〉 | 2019.08.03 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「深淵なる地球生命圏を紐解く~22世紀のエネルギー革命を目指して」〈東京〉 | 2019.07.30 |
| 【関連行事】JPrOS/JES 合同大会シンポジウム『第3回 日本生物工学会 バイオ計測サイエンス研究部会 シンポジウム~1細胞解析技術の新展開~』《宮崎》《バイオ計測サイエンス研究部会共催》 | 2019.07.26 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「機知機略のドラッグデザインin京都大学~独自AI・機械学習、独自標的探索から新規可視化技術まで~」〈東京〉 | 2019.07.23 |
| 【協賛行事】微生物ウィーク2019〈東京〉 | 2019.07.22-2019.7.27 |
| 【協賛行事】第2回天然ゴム研究会シンポジウム「天然ゴムから考えるバイオマテリアルエンジニアリングのこれから」 〈横浜〉 | 2019.07.19 |
| 【後援行事】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019〈仙台〉 | 2019.07.14 |
| 【協賛行事】大阪工研協会 バイオ実習セミナー ―微生物・細胞取扱いと検査・試験の基本操作―〈大阪〉 | 2019.07.05, 2019.07.08 |
| 【協賛行事】第32回イオン交換セミナー「挑戦するイオン交換 V」〈東京〉 | 2019.07.05 |
| 【後援行事】早稲田地球再生塾シンポジウム2019「脳科学と感性科学の融合」〈東京〉 | 2019.07.03 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「東京五輪への課題シリーズ4:SDGsと感染症サーベイランス」〈東京〉 | 2019.07.03 |
| 【協賛行事】バイオプロセス講演・見学会「急速に進歩する体外診断薬、その最前線」〈新潟〉 | 2019.06.27-2019.06.28 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「牛馬のゲノム科学・遺伝学研究」〈東京〉 | 2019.06.20 |
| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会講演会「バイオ医薬品の連続生産の現状と課題」〈東京〉 | 2019.06.19 |
| 【協賛行事】未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(44)「生活を豊かにする高圧技術と応用展開」 〈横浜〉 | 2019.06.14 |
| 【協賛行事】19-2ポリマーフロンティア21「これからの地球環境課題にプラスチックはどう向い合?」〈東京〉 | 2019.06.11 |
| 【協賛行事】世界水素技術会議(WHTC)2019〈東京〉 | 2019.06.02-2019.06.07 |
| 【協賛行事】第64回低温生物工学会大会 (セミナー及び年会)〈つくば〉 | 2019.06.01-2019.06.02 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「未来の食のアドベンチャー~培養肉、昆虫食、熟成肉」〈東京〉 | 2019.05.29 |
| 【協賛行事】界面コロイドラーニング-第35回現代コロイド・界面化学基礎講座(東京・大阪)〈東京:5月23・24日/大阪:6月13・14日〉 | 2019.05.23-2019.05.24 2019.06.13-2019.06.14 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「東京五輪への課題シリーズ3:アンチ・ドーピング」〈東京〉 | 2019.04.25 |
Published by 学会事務局 on 31 3月 2020
2020年3月31日
公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏
大会実行委員長 中山 亨
第72回日本生物工学会大会(2020)は2020年9月2日(水)~9月4日(金)東北大学川内北キャンパスにおいて開催の予定です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を注意深く見守りながら通常通りの開催に向けて実行委員会を中心に準備を整えております。今のところ例年と同じく、通常開催をする方向で準備を進めております。4月8日には一般講演の申し込みが開始されますので5月13日(水)正午の締め切りまでに多数の応募をお願い申し上げます。また、懇親会は開催の可否も含めまして、6月中旬以降に別途メール等でお知らせ致します。
なお、コロナウイルスの感染については予断を許さない状況もあることから状況に応じて開催の方法について変更が生じる可能性があることをご承知おきください。
以上
Published by 学会事務局 on 27 3月 2020
2020年7月4日(土)~5(日)の日程で石川県にて開催予定の2020年度若手会夏のセミナーについて、この度延期することを決定いたしました。新たな開催時期については未定ですが、1年程度延期し、2021年夏ごろの開催を予定しております。
毎年開催してきた伝統のある夏のセミナーですので、何とか開催できないかこれまで実行委員を中心に検討してまいりましたが、夏のセミナーの内容や趣旨、および参加する皆様への影響を勘案しまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という観点から上記のように延期を決定いたしました。2021年の開催時期については、国内の状況等を鑑みながら決定したいと思いますが、新型コロナウイルス感染症が終息し、皆様が安心して参加できる時期に改めて石川県で開催したいと思います。
参加をご検討して下さった皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力を下さいますようお願い申し上げます。
馬場 保徳(夏のセミナー実行委員長、石川県立大学)
中島 一紀(若手会会長、北海道大学)
Published by 学会事務局 on 24 3月 2020
生物工学会誌 第98巻 第3号
三宅 淳
人工知能といえば、医療画像の自動判定や自動運転技術として注目の的である。医学領域では、その本質である「診断」が定性的・概念的方法であって人工知能の機能と相応することから、応用研究が急速に広がりつつある。生物工学の分野では、厳密な数値を求める工学の立場が強いだけに応用はまだ限定的である。しかし生物は単純なモデルでの解析が困難であり、個と全体が簡単に結びつかない複雑系である。人工知能が大いに役立つ分野である故に、早晩応用が進むであろう。
留意したいのは、ルネサンス以降発展してきた自然科学が可能とした定量性と、人工知能が提示する概念性という対極にある2つの方法が初めて揃ったことである。ギリシャに始まった科学哲学は我々の自然認識や方法の基礎ではあるが、自然科学がその唯一の子孫とは言えない。自然科学の特徴は物理学によく見ることができる。すなわち、長さ、重さ、時間という3つの要素を「人為的に」選択し、その関係を定式化するものである。問題は3つの要素だけでは森羅万象を記述しきれないことである。自然科学の体系は産業革命を経て形成され、発展を続けてきた社会・技術と相互作用しながら特定の方向へ形成されてきこともあり、もともと応用学との相関が深い。また、自然科学は体系性が特徴である。計測された事実を含むすべての空間における共通した構造を知ろうとする。現象は一旦体系に昇華され、そこから数的・精密な検証が可能となる。
自然科学だけを習ってきた我々は、専門性を研ぎ澄まし、範囲を狭めてキリのように深めていく細密さが自然を理解するための唯一の合理的方法と信じてきた。しかし、細密な領域での深堀りを続けると、我々の理解は、無限に小さな領域の、相関性の乏しい集合になってしまう可能性がある。エネルギーと物質の再帰を含む循環型社会のような複雑な対象になるとうまく扱いきれない。複雑系を扱う難しさは生命系・感性においてさらに顕著である。自然科学によって人間の感情・情動・アーティスティックな価値の扱いは困難であった。脳の中の構造や機能を分子のレベルから解明できればヒトの知性は再現できるという漠然とした期待があったが未だブレークスルーに至っていない。
これに対して人工知能は帰納的な方法である。ヒトの「考え方」の模倣であって、提示された現象から、自ずからなるカテゴリーを見いだし、個々の現象をそこへ分類する。がん組織や細胞をX線写真から見いだすのも典型的なカテゴリー分類である。写真に映った対象物をカテゴリーにわけて、がんが分類されたカテゴリーに属しているかどうかを判定する。ヒトよりも解析が詳細であるから診断はより正確になる。
経済、地球環境、疾患と原因などの多すぎる相関をどのように結びつけるか、環境負荷のない経済発展はあるのだろうか。人工知能はこのような超多量要素からなる問題を解くうえで役立つだろう。さまざまな要素の組合せを行ってカテゴリーを創出し、最良の現象につながるものを選び出すことができる。自然科学とは方法も対象も異なっていて、要素を限定せず、全体の特性=概念あるいはカテゴリーを抽出したり定義したりする。細部へではなく、上へ上へと階層を昇って行き、俯瞰する方法である。定量的な「法則」が存在しないので、精密性がないと誤解されるが、概念を扱う方法であって分担範囲は異なる。
生命体を構成する分子は、物質・エネルギー・情報を内包する三位一体の存在である。すでに生物工学は生命体の機能そのものとなる膨大な情報と制御に関わる多くの事象を扱っている;たとえば、細胞内の分子反応の連関、情報ネットワーク、遺伝的制御、細胞集合体の機能などである。しかし、情報は物質の特性に付随するものだと思われているところもある。情報によって形成される概念が「もの」の価値を超える可能性も遠い未来ではないかもしれない。我々は、システム全体を俯瞰した概念の形成とその利用を行う人工知能という、自然科学に基づいた厳密な工学と相補い合うものを見いだしつつある。それらをただつなぎ合わせるのではなく、より高次の理解と応用の方法を創造的に編みだすことができるなら、工学は感性やアートの世界も内包し、生命・複雑系をフィールドとする、これまでにない体系を持つことになるに違いない。
著者紹介 大阪大学国際医工情報センターおよび大阪大学工学系研究科Hitz協働研究所(特任教授)
Published by 学会事務局 on 24 3月 2020
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 16 3月 2020
2020 Sakura-Bio Meeting は、webを用いて開催します。ただし、要旨の公開と、発表者有志による一般講演のビデオ発表とPDFポスター発表のみになり、招待講演は行われません。
3月30日からpdf閲覧とビデオ閲覧が可能になる予定です。また3月31日10時よりZoomを用いて、ビデオ講演と質疑応答を行います。
参加希望者は、下記申し込みサイトよりお申し込みください。参加費は無料です。なお参加者は100名までとさせていただきます。参加登録者にはアクセス情報をメールにてお知らせします。
The 2020 Sakura-Bio Meeting will be held on the Internet with free of charge.
However, no invited lectures are available. Instead, only video talks and pdf posters are provided by some voluntary presenters in addition to the abstract.
Pdf and video viewing will be open from March 30. Zoom meeting for video streaming and Q & A sessions will start from 10:00 on March 31st.
All the participants are requested to apply from the registration site below.
The maximum number of participants is limited to 100. Approved participants will receive an e-mail about the access information.
♦関連記事:
Published by 学会事務局 on 06 3月 2020
SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野について、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、創立100周年に向けて新たにスタートしたものです。
抗体医薬の発展により21世紀の創薬は革命と言える変化が起きました。今後、遺伝子治療、CAR-T細胞医療や再生医療など、バイオ医薬品による革命は続くと考えられています。化学合成による安定な生産が可能な低分子医薬品と異なり、バイオ医薬品の生産は、細胞の状態や製造条件により品質や生産量が大きく影響を受けます。また、製造コストが高いという問題もあります。フレミングが発見したペニシリンが医薬品として利用されるには、フローリーとチェインによる生産技術の開発が不可欠であったように、今後のバイオ医薬品による革命には生産技術の発展が必要となっています。このため、これまで以上に生物工学の貢献が大きく期待されています。本シンポジウムでは、バイオ医薬品の開発から生産までの技術について最新の研究成果および技術・戦略動向を紹介し、それらの課題から生物工学の役割と期待を議論するシンポジウムにしたいと思います。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
【主催】公益社団法人 日本生物工学会
【協賛】公益社団法人 化学工学会、一般財団法人 バイオインダストリー協会
一般社団法人 日本蛋白質科学会
【後援】公益社団法人 日本農芸化学会
公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)
TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034
E-mail: (SBJシンポジウム担当)
Published by 学会事務局 on 04 3月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 4(2020年4月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 学会事務局 on 03 3月 2020
第72回日本生物工学会大会(2020)のホームページを公開しました。 大会サイトでは、2020年9月2日(水)から4日(金)に、東北大学川内北キャンパスで開催される年次大会に関する情報を発信していきます。
講演要旨登録と大会参加申込のウェブ受付は、2020年4月8日(水)より開始いたします。
本大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
公益社団法人日本生物工学会
第72回年次大会(2020)ホームページアドレス
https://www.sbj.or.jp/2020/
Published by 支部:西日本 on 02 3月 2020
日本生物工学会 西日本支部長
稲垣 賢二
日本生物工学会西日本支部では、この度「西日本支部若手研究者賞」を創設致しました。この賞は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した優れた若手研究者の研究を奨励し、さらにステップアップしていただくことを目的とするものです。若手研究者の皆さん、どうぞ積極的な応募をお願い致します。
Published by 学会事務局 on 29 2月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 3(2020年3月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 学会事務局 on 27 2月 2020
| 日時 | 2020年5月21日(木)14:40~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 東京農工大学 新1号館グリーンホール 〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16 |
| 参加費 | 無料(事前申込み不要) |
(司会:上平 正道)
古くから“医食同源”の概念として知られるように、食生活は生体内の恒常性を調節し、その調節機構の破綻は生活習慣病につながる。近年の食科学の進歩に伴い、食と健康の関係が単なる現象論だけではなく、その分子作用機序の解明という科学的根拠に基づいた証明がなされ始めた。特に、細胞膜上脂肪酸受容体群の同定により、食由来脂肪酸が単なるエネルギー源であるだけではなく、シグナル分子として重要であることが明らかとなり、肥満・糖尿病等の代謝性疾患の標的分子として、これら脂肪酸受容体群は注目されている。
(座長:養王田 正文)
技術革新の加速が求められる今日、研究開発の効率化は国内外で大きな課題となっています。そして、AI・人工知能技術の活用も、現在の第三次AI・人工知能技術ブームを経て年々競争が激化しています。このような背景を踏まえ、当会では、(i)AI・ディープラーニング技術が、研究開発にどのように活用されているのか、(ii)AI・ディープラーニング技術を活用する際に実験データや成果物はどのように管理・運用されているのかについて、国内外の事例を踏まえてご紹介したいと思います。
(座長:上平 正道)
♦ 関連記事:【事務局より】2020年度総会および関連行事のお知らせ
Published by 学会事務局 on 27 2月 2020
2020年度日本生物工学会総会は、新型コロナウイルス感染拡大の防止、皆様の安全を最優先する観点から物理的なご出席は要請しないこととしインターネットによる議決権の行使により実施することにしました。⇒詳しくはこちら
日本生物工学会の2020年度総会およびその後の諸行事を下記のとおり開催いたします。
会員のみなさまにおかれましては,多数ご出席くださいますようご案内申し上げます。
日時:2020年5月21日(木)13:00~14:20
場所:東京農工大学 新1号館グリーンホール(〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16)
⇒大阪千里ライフセンター
⇒(変更しました)日本生物工学会 事務局(大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学工学部内)
次第:
日時:2020年5月21日(木)14:40~17:00
場所:東京農工大学 新1号館グリーンホール
参加費:無料(事前申込み不要)
プログラム: ⇒講演要旨はこちら
日時:2020年5月21日(木)17:00~19:00
場所:東京農工大学 140周年記念会館(〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16)
参加費:5,000円(税込)(懇親会費は当日受付にてお支払いください。)
申込方法:懇親会参加者希望者は、原則としてあらかじめ参加申込してください。
申込締切日:2020年5月8日(金)
申込先:日本生物工学会事務局
TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034 E-mail:
Published by 学会事務局 on 26 2月 2020
2020(令和2)年2月26日
日本生物工学会会員の皆様
公益社団法人 日本生物工学会
会長 髙木 昌宏
2020(令和2)年2月20日(木)、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、厚生労働省よりイベントの開催に関するメッセージが発出されました。
日本生物工学会といたしましては、このような状況に鑑み、日本生物工学会が関係する集会や会合の開催について、支部、研究部会、会員の皆様にご協力のお願いをいたします。感染の広がり、会場の状況などを踏まえ、開催の必要性をご検討いただきたいと思います。
開催に当たっては、以下のご協力をお願いします。
また、海外からの招へい者がいらっしゃる場合には、出入国に当たっての状況等、当該国の対応にも留意をお願いいたします。
以上は、現時点での対応となりますが、状況は日々変わりつつありますので、会員の皆様には迅速な情報提供、ご案内を行うべく努めてまいります。
皆々様には、どうぞご自愛頂きますよう、よろしくお願いいたします。
♦参考資料:
Published by 学会事務局 on 25 2月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) では、2020年2月19日(水)よりEditorial Manager®で論文を受け付けています。⇒ JBBへの投稿・査読(Editorial Manager®)はこちらから
※ご利用にあたっては、初回ログイン時にパスワードの設定をする必要があります。
Editorial Managerのユーザー名とパスワードは、Elsevier Profileとは連動しませんので、ScienceDirect等他のElsevierのサービスで設定されたユーザー名とパスワードに変更はありません。
Published by 学会事務局 on 21 2月 2020
生物工学会誌 第98巻 第2号
柏木 豊
近年、夏の猛暑、豪雨、強力な台風などの気象災害が多発しています。おりしも国連気候行動サミットが開催され、わが国からは環境大臣が出席され演説をされました。地球温暖化は、人類の化石燃料利用から排出されるCO2などの温室効果ガスが原因であることは定説となっています。
今から40~50年ほど前、化石燃料資源の枯渇が叫ばれ、未利用バイオマス資源を燃料へと変換する研究開発に注目が集まったことがあります。これに呼応して、バイオマス変換技術への微生物・酵素の活用研究が強力に推し進められました。この時期に大学を卒業し、農林水産省の研究機関に採用された私は、バイオマス変換計画のなかで研究生活を送ることになりました。この当時、大気CO2濃度の上昇は観測されていたものの、地球温暖化や気候変動はまだ顕在化していなかったように思われます。むしろ、排気ガスによる大気汚染が大きく問題視されていました。同時に、微生物を利用した化石燃料代替技術の研究開発が進められ、多くの成果が得られましたが、実用技術としての普及はなかなか進まないのが実情であったと思います。しかし、この数年の気象災害の多発を見ると、CO2排出削減が目前の課題として突きつけられ、いよいよこれまでの技術発の結果と、さらなる研究に期待される時期が到来しているのではないでしょうか。
当時、取り組んだ研究課題は植物由来の未利用糖質の資源化というものであり、木質セルロースを食糧や燃料へ変換することを目的としたものでした。配属された研究室では、公設試験研究機関、企業(食品産業に限らず)からの研究員が多数在籍し、精力的に研究が進められていました。その中に混じって微生物探索から研究をスタートしましたが、新規のセルラーゼ生産糸状菌を分離することができ、酵素の特性の解明と酵素遺伝子の単離を行うことができました。もう一つは、非結晶性セルロースからセロビオースを特異的に生成する細菌におけるセロビオース生成要因の解明というものでした。すでにセロビオヒドロラーゼ(CBH)が結晶性セルロースからセロビオースを生成することは研究されていましたが、非結晶性セルロースに作用するCBHは未発見であり、新発見の可能性が期待されました。結局、該当の酵素はβ-グルコシダーゼの一種であるがセロビオースへの作用が低いために培地にセロビオースを蓄積することがわかり、新発見には到りませんでした。当時は、開発されたばかりのゲル板式の蛍光DNAシーケンサーやPCR装置が研究所に導入され始め、遺伝子の配列解析にようやく活用される時期でした。現在の研究環境からすると隔世の感があります。
その後、本省の研究行政部署に移動になり、続いて地方公設試験場に転勤になり、バイオマス変換の研究から離れてしまいました。1997年に研究所に戻った時には、発酵食品を所掌する応用微生物部の糸状菌研究室に室長ポストとして配置されました。このころに、麹菌Aspergillus oryzae EST解析・ゲノム解析研究コンソーシアムに参画し、企業、国研、大学の皆様と自由闊達に大変に楽しく研究させていただきました。麹菌ゲノム解析コンソーシアムに参加したNITEのDNAシーケンスセンターの解析能力に後押しされて、当初の予想よりも短期間の3年ほどでドラフト配列が判明し、2005年に全塩基配列の解読に成功しました。同時に、アメリカ、EUにてA. fumigatus、A. nidulansのゲノムが解明され、海外勢力に遅れることなく、Aspergillus属3菌種ゲノムのそろい踏みが叶いました。
麹菌や発酵食品の研究のつながりで、縁あって、伝統ある東京農業大学醸造科学科にお世話になっています。研究機関から大学への転職となり、一番に気がついたのは、学生の人数と多様性の多さです。多いときには200人近くの学生に講義をしています。授業で受講生がどれだけ満足してもらえたのか、未だに判然としないままですが、醤油醸造学などの講義をしています。現在は、新原理のNGS(次世代シーケンス)が次々と開発されてゲノム解析研究が身近になり、また測定機器が発展し、分析技術が充実しています。若い研究者の方々は、このような研究環境を活かして、これまでの研究から大幅に前進した研究成果を得られていることと思います。社会からの注目度により研究が促進されることよくあることですが、冒頭の話題のように、地球環境の観点からも発酵や生物工学の研究の進展が大いに期待されていると思います。
著者紹介 東京農業大学 醸造科学科(教授)
Published by 学会事務局 on 21 2月 2020
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 19 2月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) では、予定より早く、2020年2月19日(水)にEditorial Manager®への移行作業が完了しました。
新しい投稿サイトのアドレスは次の通りです。ブックマークをお願いします。
初回ログイン時にパスワードの設定をする必要があります。
Editorial Managerのユーザー名とパスワードは、Elsevier Profileとは連動しません。
ScienceDirect等他のElsevierのサービスで設定されたユーザー名とパスワードに変更はありません。
Published by 学会事務局 on 17 2月 2020
Published by 学会事務局 on 10 2月 2020
Journal of Biosicence and Bioengineering (JBB)では、論文投稿・査読受付システムをEVISEからEditorial Managerに移行する予定です。つきましては、データ移行作業のため、以下の期間システムの利用ができなくなります。
現システム(EVISE)で受付をした論文およびユーザーのアカウント情報はすべて新システムに移行されます。
EIVISEのユーザーには、移行が完了した時点で、新しい投稿サイトおよびシステムへのログイン方法をメールでお知らせいたします。移行後は、新しいサイトで作業を進めていただくことができます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
Published by 学会事務局 on 09 2月 2020
新型コロナウイルス拡大汚染防止および汚染の懸念から 2019年度サスティナブル工学研究会講演会を中止とさせていただきました。
サスティナブル工学研究部会では、下記の通り、サスティナブル工学特別講演会を開催いたします。
講師である木田建次先生(熊本大学名誉教授)は、メタン発酵およびエタノール発酵などの発酵プロセスによる廃棄物系バイオマスの循環利用・資源化の基盤技術研究を精力的に進められています。木田先生は、本会で長年ご活躍され、2010年度第29回生物工学賞「バイオマスのバイオガス化・バイオエタノール化のための基盤技術開発とその応用」を受賞されています。さらに、研究活動だけではなく、得られた研究成果を自治体の資源循環型まちづくりの構築に活用されるなど、社会貢献も精力的に行っておられています。熊本大学を定年退職後、中国四川大学に移られて、サスティナブル工学に関する教育、研究および社会貢献に従事されて、中国の現状に大変精通されています。本講演会では、中国での活動・経験を中心としてご講演いただきます。
サスティナブル工学、資源循環利用などをキーワードとする研究に興味のある方はもちろん、中国で国際共同研究などの活動を予定されている方のご来聴を心より歓迎いたします。(非研究部会員の方も奮ってご参加ください。)
【主催】日本生物工学会サスティナブル工学研究部会
【共催】九州大学大学院農学研究院土壌環境微生物学研究室
Published by 部会:バイオインフォマティクス on 07 2月 2020
本部会活動においてこれまで作成・運用されたコンテンツをご覧になることができます。
情報は随時更新されます。
当日使用したセミナー資料を株式会社Preferred Networks様よりご提供いただきました。
資料1 メディカルAI専門コース オンライン講義資料 (深層学習の理論とChainer関数群の解析用)
資料2 microscopy_data_with_chainer (今回の実習のプログラム実行内容)
資料1 Rを用いたRNA-Seqデータのクラスタリング
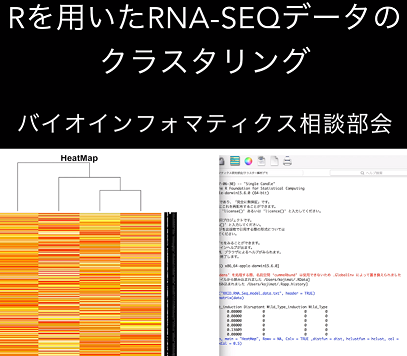
(リンクかサムネイル画像をクリックすると動画の再生が始まります)
資料2 Rを用いたRNA-Seqデータのクラスタリング (入力用スクリプト)
講演会の開催趣旨説明用のスライドです。講演会、ならびに本部会の運営理念についての理解の一助にしていたけますと幸いです。ファイルは読取専用です。pptx版は説明原稿付きとなっております。
第三回講演会 開催趣旨スライドpptx版(説明原稿付き)・pdf版
第二回講演会 開催趣旨スライドpptx版(説明原稿付き)・pdf版
産業技術総合研究所 人工知能研究センター
堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第97巻 第6号
和文誌編集委員長 岡澤 敦司
この度、生物工学会誌編集委員長を拝命いたしました大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の岡澤敦司です。就任にあたり、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
期せずして、新元号への切り替わりという歴史の節目に、伝統ある生物工学会誌(以降、和文誌と記します)の編集委員長を任せられることになり、大変名誉に思うとともに、一層の重責を感じております。任を与えていただいた前執行部役員の先生方に、まずは心よりお礼申し上げます。
私は、園元謙二先生が編集委員長を務められていた時に和文誌編集委員に加えていただき、幸運にも木野邦器先生、藤原伸介先生という3名の編集委員長の先生方と和文誌の編集に携わることができました。園元先生は、学会誌として、「学問情報の伝達」「学会活動の伝達」および「会員の相互交流」を使命に掲げられ、木野先生は、さらに「産学連携の強化や民間研究の発信」にご尽力され、前任の藤原先生は、それまでの方針を継承しつつ、「会員が欲する情報の発信」という視点での編集に努められました。その甲斐もあり、「特集」「バイオミディア」ならびに「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―(現在は続編として継続中)」といった、和文誌の基幹といえる記事のダウンロード件数は、依然右肩上がりとなっています。また、「プロジェクト・バイオ」「生物材料インデックス」「バイオ系のキャリアデザイン」ならびに期間限定連載のバイオインフォマティクスや統計解析に関する講座なども、他に類を見ない、あるいは、他に先駆けて取り組んだユニークな記事として、大変好評を得ております。これもひとえに、編集委員、バイオミディア委員、ならびに、支部編集委員の皆様と執筆者の先生方、事務局の連携の賜物であり、ひいては、学会誌に期待を寄せていただいている学会員のご支援によるものと感謝しております。新体制においても、これまでの編集委員会の基本方針を踏まえ、より魅力的な誌面作りを進める所存です。
平成は、科学技術という側面では大変な飛躍を遂げた時代であり、特にバイオ関連の技術革新には目を見張るものがありました。和文誌においても、時流に乗った先端のバイオ技術を「特集」や「バイオミディア」で積極的に発信することができました。一方、社会に目を向けると、度重なる自然災害や、宗教あるいは政治的な対立が激化し、あらゆる分断が生じた時代でもあり、科学技術の進展が世界平和につながると信じる楽観主義者にとっては、試練の時であったかもしれません。令和への切り替わりを一つの機会として、和文誌から発信する科学技術について、あるいは、科学者や科学そのものについて、社会との関係を改めて根本的に考えてみる必要があると感じています。醸造、醗酵から連綿と続くバイオテクノロジーを、どのように社会に受容また活用してもらえるかについて、特には哲学的にも考えなくてはいけない時代になりつつあると思っています。生物工学会は、数ある学術団体の中でもずば抜けて自由闊達な雰囲気をもち、若手からシニアまですべての年代層の活力に満ちている学会だと思います。和文誌が、学会員の皆様の多様なご意見を頂戴し、広く発信することで、学会内外での対話を促し、学会活動を社会に還元するための一端を担うことができないか模索したいと思います。
新体制では、長森英二先生(大阪工業大学工学部)に編集副委員長を務めていただきます。前期より継続していただく9名の委員に加え、4名の企業の方を含む8名の新任の委員の皆様、10名(内4名が新任)のバイオミディア委員の皆様、各支部編集委員の皆様、事務局の皆様とともに和文誌の編集を進めて参ります。ご存知のように、和文誌のほとんどの記事は、学会内外の執筆者からのご寄稿によっています。執行部、各支部、ならびに、若手の会を含む各研究部会とも連携を取りながら、充実した誌面作りを目指して参りますので、引き続き会員の皆様のご支援とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第97巻 第6号
英文誌編集委員長 神谷 典穂
この度、英文誌編集委員長を拝命しました九州大学未来化学創造センターバイオテクノロジー部門兼工学研究院応用化学部門の神谷典穂です。就任にあたり、自己紹介方々、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
私と本会の出会いは、20年以上前に遡ります。1995年に第47回大会が九州大学工学部で開催された修士2年の秋、私にとってはバイオの専門家が集う学会での初めての発表に、たいへん緊張したことを覚えています。これがきっかけで、当時の指導教官である後藤雅宏先生より投稿を勧められ、本誌への初投稿論文はJournal of Fermentation and Bioengineering(JFB)に受理されました。工学部の片隅でバイオに関する研究を始めたばかりの学生にとって、掲載可否もさることながら、生物工学の専門家からどういった評価が下されるのか、期待と不安を抱きながらの投稿作業でした。結果として受理に至りましたが、率直で建設的な査読意見を頂戴し、その後の学位論文の執筆に大いに役立ちました。学術誌への投稿に際し、自身の研究を客観視し、誠実なreviewに伴う厳しさと温かさ、次の展開に繋がるヒントを求める気持ちは、当時と今であまり変わりはありません。
改めて英文誌の歴史を紐解くと、前身の醗酵工學雑誌には1973年から1976年までは奇数月が日本語、偶数月は英語の論文が掲載され、1977年に和文誌「醗酵工学会誌」と英文誌‘Journal of Fermentation Technology’が誕生します。その後、1989年にJFBへ、1999年にJournal of Bioscience and Bioengineering(JBB)へと変遷を遂げ、現在に至ります。JBBへの名称変更により、本誌のスコープがより幅広い分野の研究者に対して浸透し、新たな研究発表の場として本誌を選択するモチベーションを高める契機となったのではないかと拝察します。
さて、直近4年間の英文誌編集作業は、加藤純一編集委員長と20名の編集委員、7名の海外編集委員、英文誌を担当する編集事務局の方々の献身的なご尽力に支えられてきました。国内編集委員の任期は4年、2年ごとにその半数が入れ替わり、次の担い手に襷が渡されます。私自身は、大竹久夫編集委員長に編集委員としての責務を、髙木昌宏編集委員長に学術誌の編集作業に関わる意味をご指導頂きながら、編集委員を4年間務めました。その後、化学工学会英文誌(JCEJ)、Biochemical Engineering Journal(Elsevier)の編集に携わってきましたが、アジア各国からの投稿の増加に比べ、日本からの論文投稿数の減少を実感・危惧しています。Elsevier社による直近数年間の分析結果によると、本誌への投稿数、掲載論文ダウンロード数の何れも中国が日本を上回っている状況にあります。インパクトファクターが2を超えたJBBへの年間原稿受付数は約850報に至る勢いです。編集委員の多くは若手・中堅の本会会員であり、ご自身の研究と教育に対するエフォートに加え、本誌の編集業務に携わっていることをどうかご理解頂き、査読依頼が届きましたら積極的にお受け頂きますようお願いする次第です。
昨今、非常に多くの電子ジャーナルが乱立している状況にあり、皆様のお手元にも投稿依頼のダイレクトメールが届いているかと思います。なかには一見JBBと見間違うような名称を冠した雑誌もあり驚くこともありますが、JBBはその歴史と伝統から新興雑誌とは一線を画します。科学(Bioscience)と工学(Bioengineering)の両面に向き合い、これらをバランス良く取り扱える点は、国内外の関連学会英文誌や関連商業誌と競争・共奏するうえでの特徴にもなります。最近は産の研究者からの投稿も増えていると聞いており、この点もJBBの強みになると考えます。産官学の会員の皆様からの投稿論文が起点となり、新しい学術や研究開発に繋がる思考の種を与え続けるジャーナルにしていくことが、結果として本誌の価値をさらに高めていくものと思います。
最後に、本誌編集委員長の重責を負うことは、私にとって大きな挑戦であり、新たな学びの機会でもあります。編集委員・事務局の皆様と、著者・査読者・読者として関わってくださる皆様のご意見ご叱正を賜りながら、JBBが日本、引いてはアジア圏のバイオテクノロジーを世界に発信するフラッグシップジャーナルとしてさらに成長するよう、精一杯尽力する所存です。令和元年からの4年間、何卒宜しくお願い申し上げます。
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
こちらでは、生物工学会誌第98巻(2020年)掲載の『バイオミディア』掲載記事(PDF)をご覧いただけます。
⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら
|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|
Published by 学会事務局 on 27 1月 2020
生物工学会誌 第98巻 第1号
会長 髙木 昌宏
新年明けましておめでとうございます。
お正月を代表する料理に、お雑煮があります。皆さんが召し上がったお雑煮は、どんなだったでしょうか?周囲の人に尋ねると、「家のお雑煮は、普通の……」と答えつつ、その中身は、ずいぶんと異なっていたりします。興味のある方は、お雑煮マップ(https://chefgohan.gnavi.co.jp/season/ozoni/)をご覧ください。あまりの種類の多さに、驚かれることと思います。お雑煮に限らず、当たり前だと思っていることを、詳しく調べて考えてみると、思わぬ発見があり、自分の先入観の危うさに気づかされるものです
我々は(少なくとも私は)、子供の頃から、「よく考えろ」「ちゃんと考えろ」と言われ続けてきました。皆さんは、「考えなくては……」と思いつつも、いったい「考える」とは、どういうことなのだろうかと疑問に思ったことはありませんか?
【考えるとは?】
「考える」を要素に分解すると、次の4種類になるそうです。
このことを知るだけでも、考えるプロセスが整理できそうで、基本は「もれなくダブりなく事柄を洗い出す」「事柄について、基本軸を明確にしつつ、全体像を把握する」「解決法を優先順位をつけて策定する」ということになります。しかし、我々が思い浮かべる「考える」となると、ほとんどの場合、結局、「深く考える」しか頭になくて、「広く」「分けて」考えることを忘れてしまっています。いい大人が集まって議論する、大学や会社の会議でもよくありそうな話です。「広く」「分けて」考え、そこから筋道を見つけ出すには、たとえば図にしてみるのも有効な方法で、その代表が、「ロジックツリー」です。詳しくは述べませんが、興味のある方は、ぜひ調べて、使ってみてください。
【演繹・帰納・アブダクション】
「筋道を立てて考える」というのは、まさに論理的思考です。この論理的思考は3つに分けられ、「演繹」「帰納」「アブダクション」です。「演繹法」は、一般的に正しいとされることと、ある事象から妥当と考えられる結論を導き出す手法、「帰納法」は、複数の事象をもとに一つの結論を導き出す方法で、これらについては、御存知の方も多いと思われます。多くの日本人が、知らないか、使いこなせていない手法に、「アブダクション」があります。これは、「仮説形成」とも言われる論理展開法で、起きた事象に対する仮説を立てて、検証する手法です。仮説は、あくまでも仮説なので、間違っている可能性もあります。失敗を極度に怖れる日本人は、特にこの「アブダクション」という思考方法は、苦手だと思われます。
【応用基礎研究とアブダクション】
哲学者の西田幾多郎は、「生きるために便利だから真理なのではなく、逆に真理だから、我々の生活にとって、有用にされ得るのである。」(哲学概論)と述べています。本誌97巻6号の会長挨拶で、望遠鏡から幾何光学が、蒸気機関から熱力学が発展したことを例に、応用基礎研究(応用が先で、基礎が後)について紹介させていただきました。見方を変えると、応用研究は、我々を真理に導く「アブダクション」を与えてくれるのです。欧米の先端科学に追随する状況、つまりは正しい仮説(ゴール)が与えられている状況から日本が抜け出すカギは、独創的な「アブダクション」にあると思います。そして我々の個性、人生もまた、いかなる「仮説」を設け、それをいかに証明するかで決まると言えるのではないでしょうか?
研究はもちろん、人生においても、今年は「仮説」を立て「証明」を試みる思考法を実践したいものです。
「プロならプロであることを証明しなければならない」(広岡達朗:野球解説者)
「各人はいわば一つの仮説を証明するために生れている」(三木 清:人生論ノート)
著者紹介 北陸先端科学技術大学院大学(教授)、日本生物工学会(会長)
Published by 学会事務局 on 26 1月 2020
日本生物工学会では、2020年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。
授賞規程![]() および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。
および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。
<推薦要領>
【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:
メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。
※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。
各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。
【書類提出締切】2020年3月13日(金)
※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の締切は、各支部で異なりますので、所属支部の支部長にお問い合わせください。
受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。
♦ 関連記事:
Published by 学会事務局 on 26 1月 2020
日本生物工学会では、2020年度研究部会の設置申請を募集しております。
研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程![]() に従って 研究部会設置申請書
に従って 研究部会設置申請書 を2020年2月26日(水)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。
日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。
2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。
理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、2016年に研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。
2020年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。
活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただくともに、年度末には活動報告書および会計報告書の提出をお願いいたします。
Published by 学会事務局 on 23 1月 2020
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 20 1月 2020
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 2(2020年2月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 支部:東日本 on 09 1月 2020
2020(令和2)年1月6日
日本生物工学会 東日本支部長
青柳 秀紀
2020年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い
日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。
東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。
つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。
| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |
|---|
|
| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |
詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。 |
「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」
に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 029-853-7212)宛、2020年2月25日(火)迄にお送りください。
ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
Published by 支部:東日本 on 09 1月 2020
第8回日本生物工学会東日本支部コロキウムは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、中止となりました。
13:00~13:05 開会の挨拶………青柳 秀紀(筑波大学)
♦コロキウム「腸内細菌研究の最前線」
13:05~13:10 趣旨説明………山田 千早
13:10~13:50
「腸内細菌が産生する代謝産物から紐解く細菌の共生機構」
……西山 啓太(慶應義塾大学)
13:50~14:30
「ヒトマイクロバイオームのメタゲノミクス」
……須田 亙(理化学研究所)
14:30~15:10
「腸管IgA抗体による腸内細菌制御」
……新蔵 礼子(東京大学定量生命科学研究所)
15:10~15:20 休憩
♦学生ポスター発表 (弥生講堂内)15:20~16:00
♦学生講演 16:00~17:40
16:00-16:25 学生講演1
16:25-16:50 学生講演2
16:50-17:15 学生講演3
17:15-17:40 学生講演4
17:40~17:50 閉会の挨拶………石井 正治(東京大学)
18:00~20:00 懇親会(東大農学部生協)
【協賛】一般財団法人バイオインダストリー協会
►東日本支部Top
Published by 学会事務局 on 07 1月 2020
このページには2019年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。
| 掲載日 | 内容 |
|---|---|
| 2019.12.26 | 【西日本支部】2019年度日本生物工学会西日本支部学生賞受賞者決定のお知らせ |
| 2019.12.25 | 【JBB】Vol. 129, No. 1(2020年1月号)オンライン公開 |
| 2019.12.23 | 【和文誌】97巻12号の一部を公開しました |
| 2019.12.23 | 【随縁随意】アカデミアによる工学研究-高木 睦 |
| 2019.12.23 | 【和文誌】第97巻9号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.12.23 | 【年次大会】第72回大会 ランチョンセミナー(開催趣旨と協賛企業の募集) |
| 2019.12.23 | 【学術賞】第17回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |
| 2019.12.19 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月28日~1月5日) |
| 2019.12.16 | 【学会賞】2020年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集 |
| 2019.12.13 | 【研究者の皆様へ】研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケー ト調査ご協力のお願い |
| 2019.12.10 | 【年次大会】第71回日本生物工学会大会(2019)後記 |
| 2019.12.10 | 【告知】「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ-グローカルに活躍する関西地域企業の魅力に迫る!-(2019)」開催中止のお知らせ |
| 2019.11.25 | 【随縁随意】実証研究を考える-本多 裕之 |
| 2019.11.25 | 【和文誌】97巻11号の一部を公開しました |
| 2019.11.25 | 【和文誌】第97巻8号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.11.12 | 【事務局より】2020年会費納入のお願い |
| 2019.11.12 | 【JBB】Vol. 128, No. 6(2019年12月号)オンライン公開 |
| 2019.11.11 | 【関西支部】2019年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い |
| 2019.10.25 | 【随縁随意】「My hunch is ..(. 私の勘だと……)」または「私のゴーストがそう囁く……」-加藤 純一 |
| 2019.10.25 | 【和文誌】97巻10号の一部を公開しました |
| 2019.10.25 | 【和文誌】第97巻7号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.10.17 | 【国際交流】2019年 KSBB秋季大会に参加して |
| 2019.10.17 | 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2019年度優秀学生発表賞決定!! |
| 2019.10.16 | 【学会賞】2020年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞) 受賞候補者推薦のお願い |
| 2019.10.07 | 【JBB】Vol. 128, No. 5(2019年11月号)オンライン公開 |
| 2019.10.01 | 【研究助成】山田科学振興財団 2020年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.10.01 | 【学術賞】第61回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.09.26 | 【年次大会】第72回日本生物工学会大会(2020) シンポジウム公募のお知らせ《締切:12月27日(金)》 |
| 2019.09.25 | 【和文誌】97巻9号の一部を公開しました |
| 2019.09.25 | 【年次大会】第71回岡山大会は盛会のうちに終了しました |
| 2019.09.25 | 【随縁随意】微生物の学名と分類学が基盤となるもの-鈴木 健一朗 |
| 2019.09.25 | 【和文誌】第97巻6号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.09.10 | 【西日本支部】2019年度学生賞候補者推薦募集 |
| 2019.09.10 | 【JBB】Vol. 128, No. 4(2019年10月号)オンライン公開 |
| 2019.09.02 | 【東日本支部]第4回 日本生物工学会東日本支部長賞 受賞者決定 |
| 2019.08.27 | 【学会賞】2019年度授賞式・受賞講演のご案内 |
| 2019.08.23 | 【和文誌】97巻8号の一部を公開しました |
| 2019.08.23 | 【和文誌】第97巻5号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.08.23 | 【随縁随意】日本酒が面白い-西村 顕 |
| 2019.08.02 | 【JBB】Vol. 128, No. 3(2019年9月号)オンライン公開 |
| 2019.07.30 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月10日~15日) |
| 2019.07.30 | 【学術賞】第1回小林賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |
| 2019.07.24 | 【和文誌】97巻7号の一部を公開しました |
| 2019.07.24 | 【和文誌】第97巻4号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.07.24 | 【随縁随意】複雑な微生物系に挑む-金川 貴博 |
| 2019.07.23 | 【若手会】2019年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告 |
| 2019.07.05 | 【JBB】Vol. 128, No. 2(2019年8月号)オンライン公開 |
| 2019.07.03 | 【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ《候補者募集 締切:8月19日》 |
| 2019.06.24 | 【和文誌】97巻6号の一部を公開しました |
| 2019.06.24 | 【和文誌】第97巻3号バイオミディア公開 |
| 2019.06.21 | 【JBB】2018 Impact Factor 2.032 |
| 2019.06.10 | 【JBB】Vol. 128, No. 1(2019年7月号)オンライン公開 |
| 2019.06.06 | 【学術賞】第28回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.06.06 | 【学術賞】令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.06.03 | 【学会賞】2019年度学会賞受賞者決定のお知らせ |
| 2019.06.01 | 【JBB】編集委員長交代と新体制発足のお知らせ |
| 2019.05.22 | 【和文誌】97巻5号の一部を公開しました |
| 2019.05.22 | 【和文誌】第97巻2号バイオミディア公開 |
| 2019.05.22 | 【随縁随意】卒業研究は楽しく-太田 明徳 |
| 2019.05.20 | 【関西支部】Thai Society of Biotechnology (TSB) 主催 国際シンポジウム(TSB2019)ジョイントセッション講演者の募集 |
| 2019.05.17 | 【JBB】Vol. 127, No. 6(2019年6月号)オンライン公開 |
| 2019.05.17 | <法定点検によるサーバ停止のお知らせ> 2019年5月18日(土)18:30 ~ 19日(日)8:30 |
| 2019.05.17 | 【学術賞】第9回(2019年度)三島海雲学術賞候補者推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.04.23 | 【随縁随意】バイオものづくりは面白い-宇多川 隆 |
| 2019.04.23 | 【和文誌】97巻4号の一部を公開しました |
| 2019.04.23 | 【和文誌】第97巻1号バイオミディア公開 |
| 2019.04.22 | 【国際交流】2019KSBB春季大会に参加して |
| 2019.04.09 | 【事務局】「10連休」期間の休業のお知らせ |
| 2019.04.08 | 【年次大会】第71回大会 講演要旨受付中 ! <締切: 2019年5月14日(火)正午> |
| 2019.04.03 | 【学術賞】2019年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.04.03 | 【学術賞】第51回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.04.03 | 【研究助成】第51回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |
| 2019.04.03 | 【研究助成】第47回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |
| 2019.04.03 | 【学術賞】第10回(2019年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |
| 2019.04.02 | 【JBB】Vol. 127, No. 5(2019年5月号)オンライン公開 |
| 2019.03.25 | 【代議員選挙】選挙結果のお知らせ(2019-2020年代議員一覧) |
| 2019.03.25 | 【和文誌】第96巻12号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.03.25 | 【随縁随意】生物工学会として温故知新-秦 洋二 |
| 2019.03.25 | 【和文誌】97巻3号の一部を公開しました |
| 2019.03.11 | 【JBB】Vol. 127, No. 4(2019年4月号)オンライン公開 |
| 2019.03.01 | 【代議員選挙】投票受付終了のお知らせ(2019-2020年度代議員選出) |
| 2019.03.01 | 【年次大会】第71回日本生物工学会 大会サイトオープン |
| 2019.02.26 | 【学術賞】第16回日本学術振興会賞(JSPS PRIZE 2019)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |
| 2019.02.25 | 【随縁随意】あなたの研究の顧客は誰?-栗木 隆 |
| 2019.02.25 | 【和文誌】97巻2号の一部を公開しました |
| 2019.02.25 | 【和文誌】第96巻11号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.02.15 | 【代議員選挙】投票受付中<締切:2019年3月1日(金)正午>終了しました |
| 2019.02.13 | 【東日本支部】2019年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |
| 2019.02.06 | 【JBB】Vol. 127, No. 3(2019年3月号)オンライン公開 |
| 2019.01.24 | 【和文誌】97巻1号の一部を公開しました |
| 2019.01.24 | 【和文誌】第96巻10号の特集とバイオミディア公開 |
| 2019.01.24 | 【随縁随意】いま、大学が求められていること-山本 秀策 |
| 2019.01.24 | 【JBB】Vol. 127, No. 2(2019年2月号)オンライン公開 |
| 2019.01.23 | 【学会賞】2019年度各賞受賞候補者推薦のお願い |
| 2019.01.23 | 【事務局より】2019年度研究部会設置申請募集《締切:2月26日(火)》 |
| 2019.01.21 | 【代議員選挙】2019–2020年度代議員 立候補受付終了のお知らせ |
| 2019.01.10 | 【正会員の方へ】2019–2020年度代議員選挙立候補受付のお知らせ(締切:1月21日正午) |
| 2019.01.07 | 新着情報2018年 |
Published by 部会:代謝工学研究部会 on 26 12月 2019
2019年度の代謝工学研究部会の活動として、代謝工学に関する研究分野においてアクティブに活躍されている3名の先生方を講師にお招きし、シンポジウムを企画しました。産学の研究者、学生の皆様の来聴を歓迎します。
日時: 2020年1月24日(金) 14:00~16:20
場所:大阪大学吹田キャンパス 情報科学B棟B101
<プログラム>
参加費: 無料
参加登録: 不要
連絡先:
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-5
大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座
戸谷 吉博 E-mail TEL 06-6879-7432
Published by 支部:西日本 on 26 12月 2019
日本生物工学会西日本支部では、生物工学に関連する優れた実績を讃え、 下記の3名に西日本支部学生奨励賞を授賞致しました。(2019年12月7日)
池田 湧 君(岡山大院・自然科学)
矢野 佳果 さん(岡山大院・環境生命)
吉岡 実咲 さん(岡山大院・ヘルスサイエンス)
Published by 学会事務局 on 25 12月 2019
Acinetobacter sp. Tol 5 is a hydrocarbon-degrading bacterium and exhibits noteworthily high adhesiveness to various abiotic surfaces from hydrophobic plastics to hydrophilic glass and metals. This unique nonspecific adhesiveness is mediated by AtaA, a nanofiber protein on the cell surface. The photograph shows a fluorescent microscopic observation of mCherry-expressing Tol 5 cells stained with an anti-AtaA antibody. The cell body of Tol 5 (red) wascovered with surrounding AtaA fibers (green).
For more information regarding this work, read the article: Aoki, S. et al., “Native display of a huge homotrimeric protein fiber on the cell surface after precise domain deletion“, J. Biosci. Bioeng., volume 129, issue 4, Pages 412-417 (2020)(Copyright@2020 The Society for Biotechnology, Japan).
⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号
⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)
Published by 学会事務局 on 25 12月 2019
Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 1(2020年1月号)をScienceDirectで公開しました。
日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。
⇒詳しくはこちら
Published by 学会事務局 on 23 12月 2019
生物工学会誌 第97巻 第12号
高木 睦
漠然とではあるが、「大学卒業後は人の役に立ちたい」と願っていた高校生の私は「工学部では産業に直結した技術を学べる」と聞き、工学部に入学した。卒業し、「やっと世の中の役に立てる」と喜んで、ある総合化学会社で13年間勤め、一仕事終えて退職して、大学(工学部)の教員になった。
工学は(狭義には)サイエンスを応用して大規模に物品を生産するための方法を研究する学問であると思う。だから、講義や研究指導では「サイエンスも大事だが、ここではエンジニアリングをやる」と学生達に再確認するとともに、「エンジニアリング(工学)は研究結果の実用化、事業化、社会実装を目指すことが前提だから、実用化までのしっかりした(仮説を含む)道筋、すなわちロジックが工研究には大事だよ」と説明するようにしている。言い換えれば「どのような経済的・社会的価値をどのように創出するのか」を十分に調査して組立ててから工学研究を始めるということだ。
実用化までのロジックはさまざまな要素を合わせて組み立てられる。たとえば、反応主原料を輸入する場合、日々変動する為替レートは重要な要素である。この他、その産業分野の状況や流れ、商品の機能やコンセプトの新しさ、コンペティターの状況、製造原価の目標、律速技術打開の可能性などもロジックの要素に含まれるだろう。
現在私が所属している大学の化学系専攻(バイオも含む)だけの大学院には、工学部出身学生と理学部出身学生がほぼ半数ずつ所属している。その中でほとんどすべての理学部出身学生の修士論文発表には、実用化に関するロジックはなく、ひたすら化学反応のメカニズムが追及される。サイエンスはこれでいいのだと思う。
ところで、昔の話だが、私は上記の総合化学会社に入社後も年に数回は工学関連の学会で、特にアカデミアの工学研究を聴講させていただいたが、中にはロジックはあるが具体性が弱く「実用化は難しいのではないか」と思う発表もあったと記憶している。他に、「実用化までのロジックがなくても、特許出願や企業から頂いた奨学金が実用化の十分条件との思いこみ」を感じさせる発表もあった。これらに対して、実用化に至るまでのしっかりしたロジックを工学研究者自らが組み立ててから始めた工学研究を少しでも増やすことができれば、アカデミアの工学研究の産業への貢献が高まるのではないかと思う。
ではどうすれば、少しでも多くのアカデミア工学研究者が、実用化までのしっかりしたロジックを組み立てる力を発揮できるようになるか、たたき台として考えてみた。まず、企業の中堅技術者の実用化までのロジックの考え方を、アカデミアの若手工学研究者がスクール形式やe-ラーニング形式で理解できるようにならないだろうか。もう一つは、アカデミアの若手工学研究者が研究発表する会を設ける方法である。主として実用化までのロジックに関するコメントを、発表を聴講した企業の中堅技術者が紙に書いて(必要ならブラインドで)オーガナイザーに発表会場で渡していただき、オーガナイザーから研究者に訊ねるというのもいいかもしれない。
そして、「(他人のことは偉そうに言う反面自分のことは見えていないかもしれない小生も含めて)大規模な研究にしても小規模な研究にしても、アカデミアの工学研究もちゃんと地に足がついている」と企業の方にもっと言ってもらえるようになれば幸いである。
著者紹介 北海道大学(教授)
Published by 学会事務局 on 23 12月 2019
第72回日本生物工学会大会は開催中止になりました。
第72回日本生物工学会大会(2020年9月2~4日、東北大学川内北キャンパスにて開催)実行委員会では、ランチョンセミナーの協賛企業を募集しています。
詳しくは、ランチョンセミナー開催趣意書![]() およびランチョンセミナーご案内・申込書
およびランチョンセミナーご案内・申込書![]() をご覧ください。
をご覧ください。
本大会でのランチョンセミナー協賛を希望される方はランチョンセミナー申込書(Word / PDFフォーム)に必要事項をご記入の上、e-mail にて下記宛までお送り下さい。
【問合せ・申込み先】
株式会社エー・イー企画
第72回日本生物工学会大会展示会係
E-mail:
TEL: 03-3230-2744
FAX: 03-3230-2479
Published by 学会事務局 on 23 12月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 16 12月 2019
日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2020年度受賞候補者の推薦を募集しております。
生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。
生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。
正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。
推薦書類は、2020年3月13日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。
Published by 支部:東日本 on 13 12月 2019
日本生物工学会東日本支部では、戸山高校SSH部様との共催事業として、『高校生セミナー(付:生徒研究発表会)』を開催しています。本年度は、以下の要領で開催いたします。年末のお忙しい時期とは存じますが、ご参会頂き、ご意見を頂戴できますと、大変幸甚に存じます。
13:00~ 受付開始
13:30~ 開会式
13:35~ 第一部 講演会
「生物工学研究への誘い」
…… 青柳 秀紀(筑波大学 教授)
14:35~ 第二部 大学生や大学院生による口頭発表
「タンパク質を“デザイン”する ~抗体を使った新規センサー構築を目指して~」
…… 井上 暁人(東京工業大学 修士1年)
「研究に挑戦してみて~微小重力を利用した乳酸菌とビフィズス菌の研究~」
…… 増田 亜理沙(筑波大学 修士1年)
「SSHで学んだことは大学で役に立つのか?」
…… 前嶋 大輝(早稲田大学 修士2年)
「研究と向き合って~植物樹皮からの未培養微生物の探索研究について~」
…… 小林 和輝(筑波大学 博士2年)
15:40~ 第三部 高校生によるポスター発表
高校生が研究成果発表を行います。生徒たちの発表には生物工学会の先生方からのコメントがもらえます。
16:30~ 閉会式
【共催】戸山高校SSH部
Published by 学会事務局 on 13 12月 2019
このたび、全国ダイバーシティネットワークの幹事機関である大阪大学と日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会・同アンケート検討小分科会は協力して、「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査(研究者対象)」を実施いたします。
お忙しい中恐縮ですが、ぜひご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。
https://www.opened.network/questionary/questionary-0002/
(調査1)大学・研究機関における男女共同参画の推進状況に対する意見・感想
⇒回答はこちら
(調査2)研究環境に関する意見・感想
⇒回答はこちら
Published by 学会事務局 on 10 12月 2019
大会実行委員長 稲垣 賢二
「晴れの国 岡山」らしい晴天に恵まれ、第71回日本生物工学会大会は2019年9月16日(月・祝)~18日(水)の3日間、岡山市内の岡山大学津島キャンパスで開催されました。当初、連休明け17日(火)からの大会日程で会場予約をしていましたが、他学会との日程重複を最小限にするため、一日早く祝日の16日(月)から開催することとしました。結果的には、祝日であったにもかかわらず、初日から800名以上の方にご来場いただけたので、変更して良かったと思います。全日程では約1600名、海外からも6か国72名もの方に参加していただき、活発な学術交流や産学連携の機会として大いに盛り上がりました。
西日本支部が担当する大会としては今回が5回目で、2013年度大会以来6年ぶり、岡山県内での開催は生物工学会史上初めてとなりました。会場の岡山大学津島キャンパスは、JR岡山駅から徒歩圏内にあり、また平坦な場所にあるため非常に使い勝手の良い場所です。またいつか開催されると良いと思います。
本大会の最大の特徴はシンポジウムと一般講演を全日並行して開催したことでした。両方のプログラムを並行して進めるにあたり、講演者や座長の重複を避けるという運営上の課題がありました。生物工学会は幅広い領域をカバーしているため、異なる分野でも同じ講演者や同じ座長が関わる可能性が高いです。ということで、プログラム編集会議では発表者、そして座長の選定においてシンポジストと可能な限り重複しないように注意しました。その結果、若干の重複はあったものの、特段の混乱はなく上手くいったと思います。会場は3日間を通じて若い会員が多く見られ、シンポジウムも一般講演も各会場大変な盛り上がりで、今回のシンポジウムと一般講演の並行実施の取組みは成功したと考えています。さらに、本年度も話題性のある一般演題30題(1題は辞退)を選定して事前に解説記事を書いていただき、「トピックス集」を作成し、記者発表で配布、紹介しました。また、実行委員の投票により3題を「トピックス賞」として選考し懇親会の会場で発表しました。
3日間にわたり、シンポジウム23件、一般講演605演題の他、ランチョンセミナー8件、懇親会、若手会総会・交流会・イブニングセッション、展示会など、かなりボリュームのある内容でしたが、学会事務局をはじめ、スムーズな大会運営にご協力ご支援いただいた企業および関係団体の皆様に心より感謝申し上げます。

2019年度学会各賞受賞者(敬称略)
前列向かって左から,伊藤伸,紀ノ岡,今井,伊藤一,佐々木,杉浦,小原
中列向かって左から,Li,渡辺昌,石井,鈴木,菅沼,高橋,渡辺大
後列向かって左から,米倉,伊藤智,高野,本山,橋田,大川,馬場

名誉・功労会員推戴
左から,飯島,大竹,松永(敬称略)

受賞講演
ここで簡単に日程を振り返りますと、まず初日16日は午前に岡山大学創立五十周年記念館で名誉会員・功労会員推戴式、各賞の授賞式、続いて、学会賞、功績賞、技術賞の受賞講演が行われ、ランチョンセミナーを挟んで、午後には奨励賞とアジア若手賞の受賞講演、6件のシンポジウムそして一般講演が行われました。特に若手会員が企画したシンポジウムでは立ち見も出るほど盛況でした。18時30分から岡山ロイヤルホテルにて開催した懇親会には当日参加の87名を含む有料参加者386名に招待者約120名を加えた約500名の方にご出席いただきました。大会実行委員長挨拶、髙木会長の挨拶、来賓代表岡山大学槇野博史学長からの祝辞に続いて、岡山の地酒「酒一筋」で有名な利守酒造さんから提供いただいた樽酒で鏡開きを行い、中西一弘大会顧問に乾杯の音頭を取っていただきました。今年はビール醸造協会4社からの新鮮で美味しいビールに加え、地ビールブームの先駆けとなった地元岡山の宮下酒造の「独歩」ビールと、西日本各地の7つのワイナリーから提供いただいたワインの特別コーナーも大好評、会員交流も大盛り上がりで、あっと言う間の2時間でした。

髙木会長 槇野学長

鏡開き

左から,韓国生物工学会(KSBB) Lee会長,台湾生物工学会(BEST)Chang会長,
中西実行委員会顧問,稲垣実行委員長,槇野学長,髙木会長

懇親会の様子
2日目17日は岡山大学一般教育棟にて、本部企画の特別シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)を生物工学にどう活用するか」を含む10件のシンポジウム、10会場で午前と午後の一般講演、ランチョンセミナー3件、代議員会が開催され、この日1日で900名を超える参加がありました。18時からは若手会総会・交流会を兼ねたイブニングセッションが開催され、先端研究の情報提供と研究交流を目的に、学生・若手研究者と企業人との交流の場となりました。イブニングセッションでは酒類総研(広島)と月桂冠(京都)にご出展いただき、約130名もの多くの参加者で大変奥深く実りある交流会となりました。
3日目18日も朝から7件のシンポジウム、10会場で午前と午後の一般講演、ランチョンセミナー2件と、他学会との日程重複にもかかわらず、最終日まで大いに賑わって終了いたしました。
なお、今回は一般講演の合間を利用できるよう隣接した大学会館にて展示会を開催し、参加企業54社から企業の技術シーズと魅力をアピールしていただきました。岡山大学生協も書籍と岡大グッズを販売、地元の土産物店による岡山土産コーナーも好評でした。また今大会では、おかやま観光コンベンション協会のご支援をいただき、無料の託児所も設置することができて、数名の方にご利用いただき好評でした。大会では引き続きの託児所設置が望ましいと思います。
最後になりましたが、今回の岡山大会実行委員会は岡山大学大学院環境生命科学研究科、自然科学研究科、ヘルスシステム統合科学研究科、岡山理科大学の会員の協力で中心メンバーを組織しました。大会運営にご尽力いただきました実行委員の皆様に改めてお礼申し上げます。
Published by 支部:関西 on 10 12月 2019
令和元年12月11日に予定しておりました「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ」の開催を中止いたします。
去る令和元年12月8日、本ワークショップにて運営およびご講演いただくことになっておりました(地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター(生物・生活材料研究部)の村上 洋 様が逝去されました。
今回、多数のお申込みをいただきましたが、事情を考慮し当該ワークショップの開催はできないものと判断いたしました。なお、ワークショップ開催日の延期などについては未決定の状態です。皆様のご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
末筆になりましたが、村上様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
日本生物工学会 関西支部
Published by 学会事務局 on 06 12月 2019
日本生物工学会中部支部では、2020年3月30日(月)、31日(火)に国際シンポジウム「2020 Sakura-Bio Meeting in Nagoya」を開催いたします。発表分野は生物工学関連全般で、すべての発表は英語で行われます。皆様のご参加をお待ちいたしております。
⇒案内用リーフレットはこちら![]()
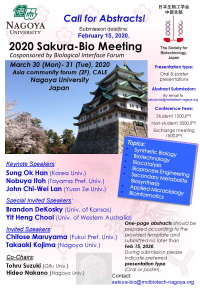
<Special Invited Speakers>
Brandon DeKosky (Univ. of Kansas)
Yit Heng Chooi (Univ. of Western Australia)
<Invited Speakers>
Chitose Maruyama (Fukui Pref. Univ.)
Takaaki Kojima (Nagoya Univ.)
【共催】名古屋大学大学院生命農学研究科、バイオインターフェース研究部会
【協賛】公益社団法人 日本農芸化学会 中部支部
Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 03 12月 2019
脂質駆動学術産業創生研究部会は2019年度第1回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。
会場:京都大学 旧演習林事務室ラウンジ
Published by 支部:西日本 on 26 11月 2019
Published by 学会事務局 on 25 11月 2019
生物工学会誌 第97巻 第11号
本多 裕之
自身のことをつぶやいて恐縮である。私の本務は名古屋大学予防早期医療創成センターである。大学のセンターで“予防”を標榜しているセンターは全国的にも珍しい。このセンターは、2015(平成27)年7月に名古屋大学の全学センターになり、医学研究科から1名の教授、工学研究科から1名の教授(小生である)、産業界から1名の特任教授、センター専任の准教授を学内の管理定員で措置していただいて4名体制で運営している。センター定員とは別に医学研究科長の門松健治先生をセンター長に迎え、松尾清一総長にもサポートいただき、産学連携、医工連携の研究拠点として運営している。
センターのミッションは多分野産学官連携による健康寿命の延伸への貢献である。人生100年時代が到来し、健康寿命と個体寿命の差をいかに少なくするかが問われている。日本の高齢化は世界の最先端にあり、高齢化のための社会システムの構築や予防に向けたモノづくりは世界が注目する最先端事業である。センターの研究の一つに、高齢者の健康維持・増進のためのコホート研究がある。この研究は、企業の現役従業員や退職者をリクルートし、過去から現在までの健康診断データ、リストバンド型の活動量計を使った現在の運動習慣情報やアンケートなどを駆使した食習慣情報、さらには健診の残余血液を使ってDNAを採取し、200 SNP程度の遺伝情報も収集し、過去の健診情報から将来の疾患予測を試みるという研究である。具体的には、メタボリックシンドロームからの脱却を促すため、個々人の体質にあった健康増進アドバイスを解析で得て、それらを特定健診の特定保健指導の一助にしていただくことを考えている。
さて、この研究で、課題は何だと想像されるだろうか?1)エントリーする対象者数、2)体質情報としてのSNPタイピング数、3)健診情報の入手方法の確保、4)レセプトなどを使った疾患発症情報の入手、5)現在の運動習慣・食習慣の正確な情報収集、6)それらを組み合わせた精度の高い推定モデルなど、どれも重要な問題である。しかし、あまりに不正確な入力情報は解析から除いて、データ数の少ない入力情報であれば少ないなりに、アドバイスを出すことはできる。難しいアウトカムを設定しなければ、それなりの疾患発症の関連性は得られる。我々も、たとえばGHRL遺伝子のrs696217のSNPのMajor Alleleを持っている人はカロリーを控えて体重を減らすことが重要といった知見を得ている。誤解を恐れずに言えば、上記の課題を一つずつ解決していけば、より精度の高い関連性が得られるし、複雑なヒトの体質や疾患発症の機構を理解する研究につながる。研究は続けられるのだ。しかし、それだけでいいのか?
生活習慣を変えることを行動変容という。実は一番大きな課題は、特定保健指導をしても生活習慣を変えない、すなわち行動変容につながらない方が多いということである。つながらなければ研究しても意味がない。リアルワールドでの実証こそ何よりも重要である。我々の研究では、自分の体質情報、健康診断情報、運動習慣情報などを掲載したマイページを用意し、対象者個人だけが閲覧できるセキュアな仕組みを作って、データを見える化し、健康意識を高めてもらうようにしている。だがしかし、それでもなお、健康意識の低い方は何も変えない。変える方は元来健康意識の高い方である。メタボリックシンドロームは痛くもかゆくもないため、行動変容につながりにくい。
さて、我々大学教員にとっての“リアル”は学生の教育である。社会に出るまでの最後の教育機関として、その責務は決して軽くない。「もっとどん欲に広い知識を得るようにせよ」「もっとアグレッシブに発言すべし」「しつこくデータを見る努力をせよ」「顕微鏡下で起きていることを想像力で理解せよ」……。指導はしてみるが、行動変容につながっているであろうか。自身のことで恐縮だが、それでもなお、「この子(学生)は、どう言えば(指導すれば)変わってくれるのか」を考える“実証研究”を楽しんでいる。ヒトが一番面白いのだ。陳腐に聞こえることを恐れずに書けば、情熱をもって語りかけ続けることが何よりも大事、である。
著者紹介 名古屋大学予防早期医療創成センター(工学研究科兼務、教授)
Published by 学会事務局 on 25 11月 2019
2014年6月号(92巻6号)にスタートした『バイオ系のキャリアデザイン』では、産学官のバイオ分野で活躍中の現役の方に執筆をお願いし、キャリアデザインに悩み、迷う大学生、院生、ポスドクにエールを送り、また転職を考える読者にも多様な道が拓けることを“魅せる”ことを趣旨として連載を継続しています。
⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら
⇒生物工学会誌Topへ
Published by 学会事務局 on 25 11月 2019
|知的財産編(前編・後編)|技術士編|バイオ系の海外就職指南|
Published by 学会事務局 on 25 11月 2019
『生物工学会誌』97巻11号(2019年11月25日発行)に以下の誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていただきます。
「本部だより:2019年 KSBB秋季大会に参加して」
・p.696 本文下から7行目
誤)SBJ → 正)KSBB
なお当サイトでは修正済みの報告記事(PDF)を掲載しております。
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 支部:関西 on 18 11月 2019
「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ(2019)」の開催は中止になりました。
関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者の方々に広く知っていただくことを目的としています。また、これから就職を考える学生さんには、公設試験研究機関に集まる地域企業の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。
テーブルディスカッション、懇親会を通して、学会などでは難しいこれら企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。奮ってご参加ください!
【公設試験研究機関の紹介】
♦(地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター
生物・生活材料研究部 村上 洋
♦(地独)京都市産業技術研究所
経営企画室 研究戦略リーダー兼京都バイオ計測センター 山本 佳宏
♦ 奈良県産業振興総合センター
生活・産業技術研究部 バイオ・食品グループ 大橋 正孝
【企業からのプレゼンテーション】
♦ 奥野製薬工業株式会社
総合技術研究部 第十一研究室 西原 紗彩
「小麦ペプチド」による食品のコク味,塩味,スパイシー感の向上効果とそのメカニズムについて講演します.
♦ サラヤ株式会社
バイオケミカル研究所 木下 和拓
当社自然派製品を例に,持続可能な洗浄剤の開発と環境に対する取り組みについて講演します.
♦ 日東薬品工業株式会社
研究統括本部 NOSTERバイオ研究所 マクロバイオームグループ 中島 瞳
有用微生物を活用した医薬品の開発,食品の開発の取り組みについてご紹介致します.
♦ ヤヱガキ醗酵技術株式会社
講演者未定
酒造りで培った伝統の”発酵技術”を駆使してオリジナル性の高い色素や機能性食品の研究開発を行っています.
【テーブルディスカッション】
4グループに分かれ,講演者の方を囲んで交流を深めていただきます.各25分×4回
主催:日本生物工学会関西支部
共催:(地独)大阪産業技術研究所
Published by 支部:九州 on 13 11月 2019
♦一般講演プログラム♦
(講演時間12分:発表10分、討論2分)
(講演時間12分:発表10分、討論2分)
(講演時間12分:発表10分、討論2分)
(講演時間12分:発表10分、討論2分)
♦学生賞審査講演プログラム♦
(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)
【修士の部】
(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)
【修士の部】
(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)
【修士の部】
(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)
【修士の部】
【博士の部】
Published by 学会事務局 on 12 11月 2019
平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。
2020年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。
2020年会費 (1月~12月、不課税)
| 正会員 | 9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |
|---|---|
| 学生会員 | 5,000円 |
| 団体会員 | 30,000円 |
| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |
紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。
2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。
毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。
を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。
会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。
2019年12月13日(金)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら
年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。
日本生物工学会事務局
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号
大阪大学工学部内
公益社団法人 日本生物工学会
Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034
E-mail:
Published by 支部:関西 on 11 11月 2019
日本生物工学会 関西支部長
藤山 和仁
日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。⇒受賞者一覧はこちら
日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度に創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。
つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。
Published by 支部:東日本 on 07 11月 2019
日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。令和に入りはじめての賀詞交換会になります。日本生物工学会創立100周年に向けて“生物工学の未来と夢”について語らい、意見交換や懇親を深める場としていただけますと幸いです。
12:40~ 受付
13:10~13:15 開会の辞
13:15~13:45
《2018年度東日本支部長賞受賞講演》
「嫌気性細菌の代謝解析とその応用利用
~ビフィズス菌由来ヒトミルクオリゴ糖分解酵素とメタン発酵制御に関する2つの研究成果〜」
………山田 千早(東京大学大学院 農学生命科学研究科)
13:45~14:15
《2019年度東日本支部長賞受賞講演》
「コリネ型細菌を宿主とした組換えRNA分子の高生産基盤技術の開発」
………羽城 周平(味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所)
14:15~14:45
《2019年度東日本支部長賞受賞講演》
「緑藻Chlamydomonasの新規利用法の開発」
………中西 昭仁(東京工科大学 応用生物学部)
14:45~15:15
《2019年度東日本支部長賞受賞講演》
「哺乳類嗅覚受容体の機能的発現とニオイセンシング応用技術開発」
………福谷 洋介 (東京農工大学大学院 工学研究院生命機能科学部門)
15:15~15:25 休憩
15:25~16:05
「プロバイオティクスの挑戦~活躍の舞台は宇宙へ~」
………酒井 隆史(株式会社ヤクルト本社 中央研究所)
16:10~16:50
「香粧品学が取り組む研究開発イノベーション」
………末延 則子(株式会社 ポーラ・オルビスホールディングス)
16:55〜17:35
「次世代の動物実験代替法開発の世界動向」
………杉浦 慎治(産業技術総合研究所 創薬基盤研究部門)
17:35~17:40 閉会の辞
17:50~19:50 懇親会
【協賛】一般財団法人バイオインダストリー協会
Published by 学会事務局 on 25 10月 2019
生物工学会誌 第97巻 第10号
加藤 純一
1988~1990年、ポスドクとしてイリノイ大学シカゴ校のA. Chakrabarty先生の研究室でお世話になった。Chakrabarty先生は面白い実験データが出ると、しばしば“my hunch is …”と頭にひらめいた解釈を意見として述べ、「それを検証してみたら」とアドバイスしてくれた。しかし、その“hunch”の多くはとてつもなく飛躍していたり、突拍子のないものであったりしたので、アドバイスされた方は困惑してしまう。幸いなことに、その日の夕刻までにChakrabarty先生はhunchを忘れてしまうため、研究室の学生とポスドクはhunchを聞き流すのを常としていた。今振り返ると、hunchを引き出させる事象に遭遇すること、その直感を実験的に実証するに至ること(さらに言うと実証したことが次のhunchへと連鎖反応的に拡がっていくこと)が研究の大きなモチベーションになっていることに気づく。そしてそのためにはChakrabarty先生のように、ことあるごとに“my hunch is …”と意見表明していかなければならないとやっと気づくようになった。
細菌の多くは好ましい化合物には集積し、好ましくない化合物からは逃避する走化性という行動的な環境応答を示す。病原菌や重要な環境細菌の挙動(走化性)の制御を目指し、これまで何種類かの細菌の走化性を測定してきた。アガロースで検定物質を固め入れたガラスキャピラリーを菌体懸濁液に挿入し、キャピラリーの開口部への応答(集積、忌避もしくは無応答)を観測することで走化性を評価する。Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)、Pseudomonas putida、Enterobacter cloacaeではクリアな走化性測定を行うことができたが、Ralstonia solanacearum(青枯病菌)では悩ましい事象に遭遇した。R. solanacearumは時としてコントロール(アガロースのみ)にも集積応答を示してしまうのである。厄介なのはR. solanacearumのコントロールへの応答がばらついていることである。コントロールに対し強い応答を示した日には他の化合物への走化性応答を評価することはできない。ともかく、コントロールへの応答がないか微弱な時の日のデータのみを使うことでこの問題を棚上げしていた。とある日、“my hunch”が頭に浮かんだ。「ガラス由来の化合物に応答しているのかも」早速ガラスキャピラリーの成分に対する走化性を調べたところ、R. solanacearumはホウ酸を誘引物質として感知し、走化性を示すことが判明した。そしてその後すぐにホウ酸走化性のセンサーも特定することができた。興味あることに、ホウ酸走化性センサーのホモログは属を超えた種々の細菌に分布するが、それらはすべて植物病原菌なのである。ホウ酸は植物の細胞壁のペクチンの架橋に使われており、植物にとって生育必須成分である。ホウ酸走化性を介した植物病原菌に共通な感染メカニズムがあるのではないかと、ワクワクしている。
士郎正宗原作の「攻殻機動隊」はSF漫画・アニメである。このSF世界では人類は自らの脳を電脳化し、コンピュータネットワークと直接接続できるようになっている。電脳における個々人の個性、自我、意識、霊性の本源は「ゴースト」と呼ばれている。攻殻機動隊の主人公である草薙素子少佐が直感を得た時につぶやく有名なフレーズが「私のゴーストがそう囁く……」である。今でも科学的な「ゴーストの囁き」を聞ける機会がある。ゴーストの囁きが聞けなくなった時が引退の時期なのだろうか?
著者紹介 広島大学大学院統合生命科学研究科(教授)
Published by 学会事務局 on 25 10月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 17 10月 2019
佐々木 建吾
2019年度生物工学奨励賞(斎藤賞)受賞者
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科
2019年10月9日~11日に韓国大邱広域市EXCO(展示コンベンションセンター)において韓国生物工学会(Korean Society of Biotechnology and Bioengineering; KSBB)の2019年秋季大会(2019 KSBB Fall Meeting and International Symposium)が開催された。日本生物工学会(The Society for Biotechnology, Japan; SBJ)からは、2019年度の学会賞受賞者である紀ノ岡正博先生(功績賞・阪大)、杉浦慎治先生(照井賞・産総研)と筆者(斎藤賞・神大)が招待され、講演を行った。

EXCO正面
大邱は韓国の南部にある都市で、ソウル・釜山に次ぐ第3の都市とされている。筆者は政治問題により減便したLCCを避けた結果、行きは金浦空港(帰りは仁川空港)を使用してソウルから高速鉄道KTXで大邱に向かわざるをえなかった。反日デモの中であったが、道中、特に問題はなかった。コンビニでは日本語表記の商品は隅に追いやられており、日本との関係が目立つものは避けられているように感じられた。
KSBBの秋季プログラムではさまざまな国の研究者が招待講演を行っていたが、中でも欧米に留学した韓国人研究者が多く目立っていた。彼らは流暢な英語をしゃべり、プレゼンテーションについては、実験結果もさることながら、明確なコンセプトをメインとして話すスタイルは欧米そのものであった。Plenary Lectureの6演題のうち筆者が聞けたのは、杉山 弘先生(京大)の「Chemical Biology of Nucleic Acids: DNA Origami and Artificial Genetic Switches(DNA配列を自由に設計した機能性ナノシステムの構築)」、Dr. Peter L. Goering(アメリカ食品医薬品局)の「A Regulatory Science Approach to Assess the Safety of Medical Devices Incorporating Nanotechnology(バイオマーカーの探索およびナノマテリアルによる評価)」、Prof. Young Chul Sung(POSTECH)の「Cancer immunotherapy & IL-7: the past, present & future(がん免疫療法とIL-7:過去、現在そして未来)」の3講演で、応用展開を見据えた韓国の方向性を垣間見ることができた。口演発表やポスターについては、バイオリファイナリー関連(合成生物工学、リグニン利用)に加えて、再生医療関連・ナノバイオテクノロジー関連の発表が多く、先にも記したように創造的な研究に対する高い意欲が感じられた。
初日には、昼食・夕食共に懇親会を催していただき、韓国料理を堪能させていただいた。何よりも現在の両国の緊張した状態にも関わらず、KSBBの先生方とは政治をジョークに変えてお酒を介して楽しく語らうことができ、対話による交流の重要さを痛感させられた。また、年配の先生方からは、我々new-generationが韓国と日本の新しい関係を築いていく、とのお話を頂き、感銘した。筆者としては野心的な韓国の研究者を参考にしつつ、国際交流の重要性を確認した旅となった。
最後に、KSBB訪問をご支援頂いたKSBB会長Hei Chan Lee先生、温かくお世話いただいたJong Wook Hong先生、ならびに日本生物工学会の事務局の方々、何よりも学術的国際交流に関する礎を築いていただいたKSBB-SBJの先生方に厚く御礼申し上げます。

後列左よりProf. Hei Chan Lee(KSBB会長), Prof. Jong Wook Hong, Prof. Hsien-Yeh Chen,
前列左より筆者, 紀ノ岡正博先生, 杉浦慎治先生, 林竜平先生(阪大)
Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 17 10月 2019
次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けております。優秀学生発表賞は、将来を担う研究者の卵たち(高専生、学部生および大学院生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。
本年度は、第71回日本生物工学会大会で一般講演(口頭発表)を行った、大学院前期課程(修士)および大学院後期課程(博士)学生の発表(27名)に対し、部会員の先生方による厳正な審査を行い、以下の5名に優秀学生発表賞を授与いたしました。
受賞された皆様、おめでとうございます!さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。
次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、来年度の大会でも優秀学生発表賞を行う予定をしております。沢山のエントリーをお待ち致しております。
Published by 学会事務局 on 16 10月 2019
Published by 支部:関西 on 10 10月 2019
盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。
標記例会ならびに懇親会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。
12:30~ 受付
13:30~14:30 見学会 沢の鶴醸造蔵「瑞宝蔵」 および 沢の鶴資料館
14:30~14:35 開会の辞 藤山 和仁(関西支部支部長・大阪大学生物工学国際交流センター)
14:35~15:15
「出芽酵母中心代謝の計測と応用」………松田 史生(大阪大学大学院 情報科学研究科)
中心代謝は出芽酵母の発酵能力など、生物によるものづくりを下支えしている生命の基本システムである。中心代謝経路を構成する代謝物、酵素、遺伝子の分子レベルでの理解をもとに、今後は、出芽酵母がエタノールを生産する理由といった中心代謝の動作原理を解明し、中心代謝機能を効率的に活用、改変する方法論を確立していく必要がある。これまで進めてきた出芽酵母中心代謝の代謝物濃度 (J. Biosci. Bioeng., (2015) 120, 280-286)、代謝フラックス (J. Biosci. Bioeng., (2015) 119, 117-120)、酵素タンパク質量 (J. Biosci. Bioeng., (2015) 120, 140-144)計測法の構築と、1遺伝子破壊株、2倍体実用酵母などの解析結果を紹介し、中心代謝を理解し、活用していくための工学的枠組みの重要性について議論したい。
15:15~15:55
「異分野連携による結晶化技術開発と大学発ベンチャー」………安達 宏昭(株式会社創晶)
創晶は、大阪大学発のバイオベンチャーとして2005年7月に起業した。電気工学とバイオ分野の異分野連携による独創的な発想から生まれた結晶化技術を活用し、タンパク質や医薬候補化合物である有機低分子の結晶化受託を事業の柱とし、創薬や生命科学の解明、製造工程における固化や精製など、主に産業界に必要とされる結晶化を支援してきた。近年は、ペプチドや核酸、抗体などの結晶化依頼も増えている。これまで結晶化しなかったサンプルの結晶化に数多く成功しているが、それはフェムト秒レーザーという特殊な光源を用いた結晶化技術が優れていることはもちろん、研究員のスキル向上と研ぎ澄まされた職人的な感覚が相まった結果であると認識している。当日は醗酵学と結晶学の共通点や相違点について、ご参加される方と議論できることを楽しみにしている。
15:55~16:05 休憩
16:05~16:50
「ヤンマー、沢の鶴による酒米プロジェクトの取組」………西向 賞雄(沢の鶴株式会社)
ヤンマー株式会社は、農業を持続可能な「食農産業」に発展させるため、米の育種から流通販売に一貫して取り組むトータルソリューションを展開することになり、これまで公的な農業試験場などが取り組んできた米の育種に参入した。また、この取り組みを「酒米」で行うことにした。「酒米」で良いとされる形質や特徴は遺伝的に、または米粒の大きさなどで判断できるが、実際に良い酒ができるかどうかは、日本酒を醸造して評価しなければならない。そこで、沢の鶴株式会社は酒米候補の醸造試験と評価を行い、2社共同の「酒米プロジェクト」に2016年春から取り組み始めた。ヤンマー株式会社の農業に密着した技術と沢の鶴株式会社の日本酒醸造技術を組み合わせ、新しい価値観の酒米を共同で開発する本取り組みについて紹介する。
17:00~18:30 懇親会
電車:阪神電気鉄道本線大石駅から徒歩10分
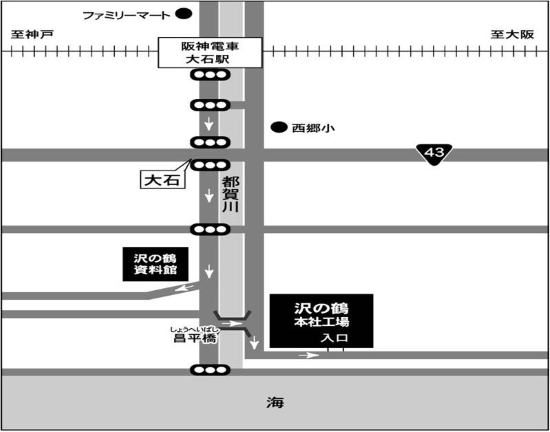
Published by 学会事務局 on 03 10月 2019
科学技術振興機構(JST)では、戦略的創造研究推進事業(ERATO)のテーマ候補・研究総括候補の募集を行っております。
本募集は、ERATO の研究領域(研究プロジェクト)および研究総括に関する選考の前段階である、研究動向調査や研究者調査の一環として、皆様から広く情報を提供いただくという趣旨のもと実施するものです。詳しくはJSTのホームページ(https://www.jst.go.jp/erato/application/index.html)をご参照ください。
Published by 支部:中部 on 03 10月 2019
日本生物工学会中部支部では、企業・アカデミック・学生を繋ぐ取り組みとして、セミナー・企業見学・懇親会をセットにした“CHUBU懇話会”を開催しています。第8回は「知の拠点 あいち」のご協力のもと、以下の日時・内容で開催いたします。
会員・学生の皆さま、奮ってご参加下さい。
<アクセス>
藤が丘」から東部丘陵線[リニモ]に乗り、「陶磁資料館南駅」下車
施設は駅北側に隣接しています。
自家用車も可
【受付】12:30~
【講演会】13:00~15:40
「あいちシンクロトロン光センターの紹介 ~各種測定事例も含めて~」
……砥綿 眞一(あいちシンクロトロン光センター)
「広角・小角X線散乱測定の紹介の紹介とデンプン構造解析への応用」
……杉山 信之(あいちシンクロトロン光センター)
「シンクロトロン光を利用した清酒酵母の育種」
……山本 晃司(あいち産業科学技術総合センター)
「X線小角散乱を用いたタンパク質の立体構造の解析」
……杉本 泰伸(名古屋大学シンクロトロン光研究センター)
「X線結晶解析を用いたcytochrome c oxidaseのプロトンポンピング機構の研究」
……島田 敦広(岐阜大学応用生物科学部)
【施設見学】15:40~16:40
(1)シンクロトロン光施設、(2)その他の計測機器について見学
【懇親会】18:00~20:00
藤ヶ丘までリニモで移動(会場は調整中)
Published by 部会:メタボロミクス on 30 9月 2019
オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき,実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として,今年も例年通り,下記講習会を開催させていただきます.昨年に引き続き,質量イメージング講習をメニューに加え,3日間の講習とします.
♦12月9日(月)(第1日)
イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要
講義:GC/MSと多変量解析
♦12月10日(火)(第2日)
実習:GC/MSを用いたサンプル分析
実習:GC/MSデータの多変量解析 実習終了後,懇親会(予定)
♦12月11日(水)(第3日)
講義(新間):見えないものを見るイメージングMS
実習:イメージングMSを用いたサンプル分析
ラウンドテーブルディスカッション,総括
終了予定 17:00頃
1)メールのタイトルは,「2019メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください.
2)本文中に,以下の項目を記載してください.
氏名,所属,現在の仕事,メタボロミクスを何に使いたいか?
3)申し込み先
福崎英一郎 (日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表)
fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp
Published by 学会事務局 on 26 9月 2019
第72回日本生物工学会大会
実行委員長 中山 亨
第72回日本生物工学会大会は、2020年9月2日(水)~4日(金)に東北大学 川内キャンパス(仙台)にて開催します。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは2日(水)の午後~4日(金)の午後まで、複数会場で一般講演と並行して実施する予定です。
会員各位におかれましては提案書に
1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)
2) 開催の趣旨
3) 世話人名(連絡先)
4) 参加予定者数(講演者、参加者)
5) その他希望事項
をお書きいただき、2019年11月1日(金)~2019年12月27日(金)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。
なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。
会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム)」「産学連携の推進」「地域社会への貢献」「SDGsに貢献する生物工学」「若手研究者主導の研究」「博士人材養成・教育の推進」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。
シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。
上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。
採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。
【申込先】
東北大学大学院工学研究科
シンポジウム担当: 石丸 泰寛
E-mail:
【募集】
【選考の手続き】
■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針
https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html
Published by 学会事務局 on 25 9月 2019
第71回日本生物工学会大会は盛会のうちに終了いたしました。
ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
第72回日本生物工学会大会は、2020年9月2日(水)~4日(金)に東北大学川内北キャンパスにて開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。





Published by 学会事務局 on 25 9月 2019
生物工学会誌 第97巻 第9号
鈴木 健一朗
微生物分類学といえば、以前は分類学者だけの専門分野であった。しかし、今では細菌/アーキアの場合、16S rRNA遺伝子の塩基配列(以下16S rRNAと略す)を決定することにより、誰でも自分の分離した菌株の同定が客観的な基準でできるようになり、微生物学者に身近なものになった。16S rRNAが共通の物差しで分類体系が構築されているため、塩基配列に基づいて菌株を地図上にプロットすれば、その株の学名がわかるとともに、比較の対照にすべき近縁な菌も的確に選定できる。これには国際的なデータベースの利用環境と微生物株保存機関の整備が大いに貢献している。
しかし、異なる株を同一種と決定するハードルはまだ高い。解像度が高くない16S rRNAだけで種は決定できないため、1960年代から使われている染色体DNA交雑による類似度(DNA-DNAハイブリダイゼーション、DDH)が必要である。DDHで70%を種の境界とするという「コンセンサス」がいまだ基準になっている。そうなると、16S rRNAでどのくらい離れていたらDDHをせずに別種にできるかの基準も重要である。これは経験的に16S rRNAの類似度で97%以下とか98.7%以下とか言われている。DDHは、比較する菌株双方からDNAを抽出し、交雑反応を行うウェットな実験として行われてきたが、最近では、全ゲノム塩基配列(ドラフトゲノム)(WGS)の決定が安価で行えるようになり、それを用いてDDHをパソコン上(in silico)で行う方法も普及してきた。
そこで、2018年から国際原核生物分類委員会(ICSP)は、細菌とアーキアの新種の発表の際にはその基準株のWGSの決定をほぼ義務化した。すべての種の基準株のWGSがデータベース化されれば、分離株のWGSを決定するだけで種レベルの同定が可能となり、さらに機能性遺伝子の情報も利用できるようになるため、分類学だけでなく、応用微生物学にも大きく寄与することが期待される。分類学は学問であると同時に、コミュニケーションツールであることから、新技術の導入と命名のルールの調和がますます重要になってくる。
「国際原核生物命名規約」の改訂版が2019年1月に発行された1)。前の改訂が1990年なので、29年ぶりとなる。命名規約では国際微生物学会連合(IUMS)の公式誌『International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology(IJSEM)』への掲載のみを学名の正式発表としているので、そこでそのすべてが把握できる(2017年現在で約3000属17,000種)。命名規約では新種発表に際し、「生きた菌株」のみを種の分類学的基準(基準株= type strain)として指定し、微生物系統保存機関(カルチャーコレクション)へ寄託・公開することが規定されたため、標本、スケッチは不可となった。
さらに2000年からは、基準株の寄託は異なる国の複数の保存機関に行うよに厳格化された。これは生物多様性条約(CBD)による生物資源の国際移転が厳しくなっている現状への対応を見直す良い機会である。分類学は適切な生物資源の管理にとってもっとも基盤となるべき知識と技術のひとつであり、CBDにとっても重要な科学である。そのために、生物遺伝資源への適切なアクセスは研究成果を担保し、発展的に利用できる国際的に公平な学術環境の維持に必要である。分類学は世界共通であり、新種の発表には既知種との比較が不可欠である。生きた基準株へのアクセスの重要性はますます高まっている。
最近ではMALDI-TOF MSが微生物の迅速同定に利用され、そのためのデータベースも市販、あるいは公開されている。マイクロバイオームの解析もゲノムベースで体系化された分類学があるから可能となったと言うことができようこれらの新しい技術が新しい知見を蓄積し、相互評価することで微生物の分類学がますます意味のあるものになっていくことに期待したい。
1) Parker, C. T. et al. (Eds.): Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 69, S1 (2019).
著者紹介 東京農業大学応用生物科学部醸造科学科
Published by 学会事務局 on 25 9月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 部会:バイオインフォマティクス on 21 9月 2019
【開催報告】第71回日本生物工学会大会シンポジウム「ペアで紹介します、WetとDryの融合研究」
第71回日本生物工学会大会シンポジウムにて、部会から公募シンポジウムとして「ペアで紹介します、WetとDryの融合研究」(大会webページへのリンク)を開催しました。
今回のシンポジウムでは2人の講演者が1つの演題を発表するペアプレゼンテーションというユニークな方法を採用しました。各講演はリレー方式、対談(漫才?)方式などで行われ、研究内容のみならず共同研究の成立の経緯や、融合研究を成功させる秘訣などについて語っていただきました。
講演者の先生方による素晴らしいご講演により、大変素良いシンポジウムにすることができました。講演者の先生方、ならびに会場にお越しいただいた皆様に感謝申し上げます。
当日の様子
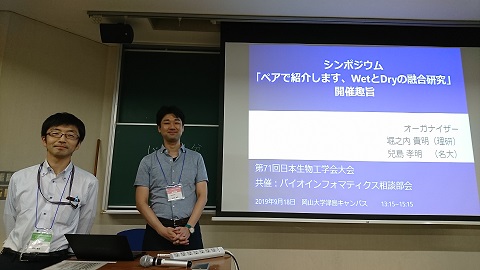
幹事会の堀之内と兒島がオーガナイザーを務めました。
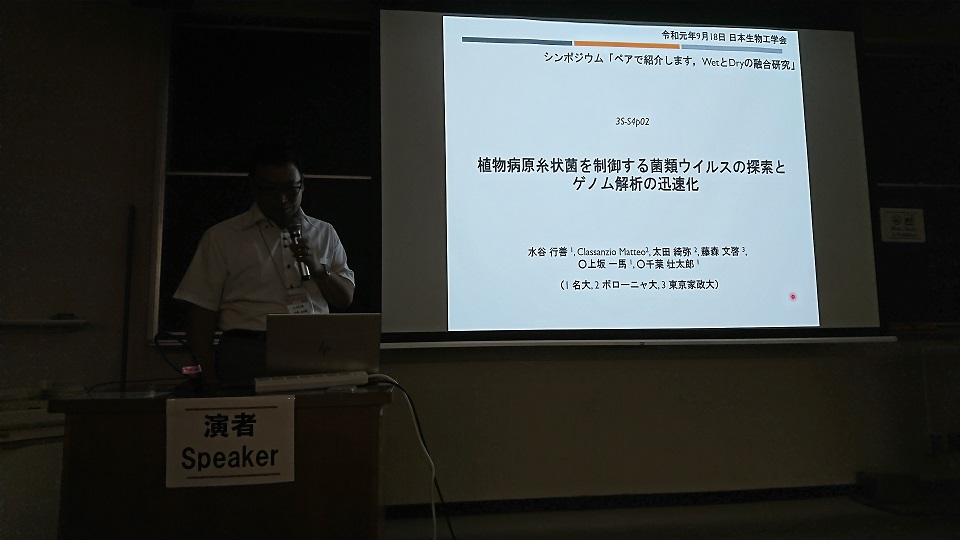
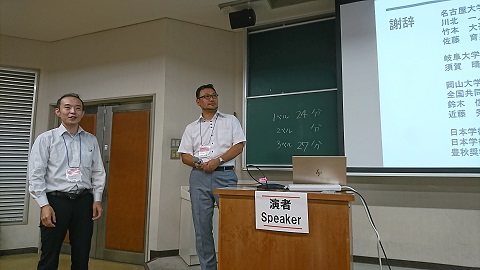
講演1「植物病原糸状菌を制御する菌類ウイルスの探索とゲノム解析の迅速化」上坂一馬先生(名大)・千葉壮太郎先生(名大)


講演2「プロトン共役型オリゴペプチド輸送体の基質多選択性解析」伊藤圭祐先生(静岡県立大)・河合駿様(住友化学)
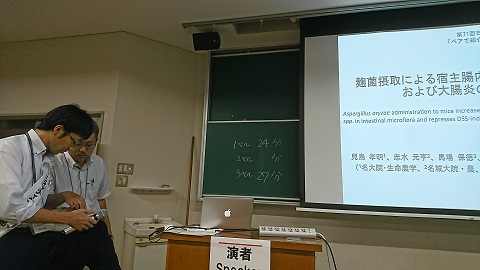

講演3「麹菌摂取による宿主腸内細菌叢の改善および大腸炎の緩和」兒島孝明先生(名大)・志水元亨先生(名城大)

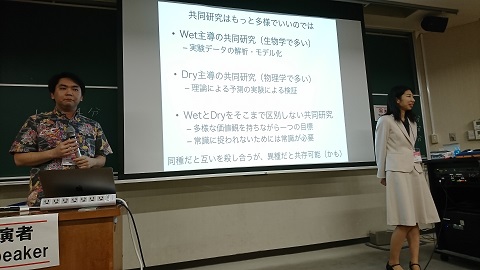
講演4「集まると変わること:酵母のストレス応答、あるいは生物と物理の共同研究について」小田有沙先生(東大)・畠山哲央先生(東大)

会場の様子。最終的には立ち見が出るほどの盛況となりました。ご参加ありがとうございました。
Published by 学会事務局 on 17 9月 2019
Published by 部会:バイオインフォマティクス on 12 9月 2019
会は盛況のうちに終了しました。ご参加ありがとうございました。
この度バイオインフォマティクス相談部会は、第三回講演会を11/20に京都大学で開催する運びとなりました。今回は大規模計測技術とインフォマティクス、ならびにそれらの自動化をトピックとして、バイオ計測サイエンス研究部会との共催により開催いたします。講演会では、生物工学分野の内外でご活躍されている先生方をお招きしてご講演頂きます。
バイオインフォマティクス相談部会 第三回講演会
~大規模計測技術とインフォマティクスと自動化~
(共催:バイオ計測サイエンス研究部会)
概要
近年発展著しいシーケンシング技術やオミクス解析などの大規模計測を用いた研究遂行に際し、計測そのものとその後の情報解析とは不可分の関係にあります。一人の研究者がその両方に取り組む場合もありますが、独力での遂行には限界があり、Wet系研究者とDry系研究者、さらに生物学研究者と分析化学研究者など、複数の分野の協業が必須となります。その場合には文化の壁を超えたコミュニケーションが必要となります。そこで本講演会では、大規模計測技術を利活用して研究に取り組む気鋭の研究者を学会内外から招聘いたします。
また最近では、こうした大規模計測によって得られるデータの前処理や生物学的特徴の抽出をより迅速に行うために、機械学習などを駆使した解析の自動化の試みが盛んに行われています。さらに実験研究においても、多量のサンプルの処理や、手技の違いに由来するバイアスの回避、フェノタイピングデータなどの大規模計測などのための実験自動化の試みがなされるようになってきました。そこでWetおよびDryの両面で、大規模計測に関する実験自動化に取り組む研究者にもご講演いただくことにしました。
今回はバイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として開催することで、より多彩な背景を持つ研究者を招聘いたします。最新の研究成果はもちろんのこと、Wet研究とDry解析をどのように組み合わせたり、異分野間で連携しているかの生の声などもお聞かせいただけるかと思います。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場としてご利用頂けますと幸いです。
プログラム ※敬称略
13:00-13:10 開会挨拶
13:10-13:40 講演1 江崎剛史(滋賀大・データサイエンス教育研究センター)
演題「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」
13:40-14:10 講演2 小野直亮(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)
演題「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」
14:10-14:40 講演3 金澤慎司(島津製作所 / 阪大・情報科学研究科)
演題「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」
休憩
15:00-15:30 講演4 岡橋伸幸(阪大・情報科学研究科)
演題「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」
15:30-16:00 講演5 三枝大輔(東北大・東北メディカルメガバンク機構)
演題「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」
休憩
16:20-16:50 講演6 堀之内貴明(理研・生命機能科学研究センター)
演題「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」
16:50-17:20 講演7 武藤愛(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)
演題「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」
17:20-17:30 閉会挨拶
18:00-20:00 懇親会(北部食堂)
【実行委員】青木航(京都大学)
堀之内貴明(理化学研究所)
兒島孝明(名古屋大学)
蟹江慧(名古屋大学)
【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター
堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp
バイオインフォマティクス相談部会第三回講演会は、バイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として、2019年11月20日-に京都大学吉田キャンパスにて開催しました。今回は「大規模計測技術とインフォマティクスと自動化」と題し、生物工学分野の内外より関連分野の研究者を招聘してご講演いただきました。今回はアカデミア、ならびに企業の参加者が多く、当該分野への関心の高さが伺えました。
ご参加いただいた皆様、ならびに共催として企画にご協力くださったバイオ計測サイエンス研究部会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。
当日の様子
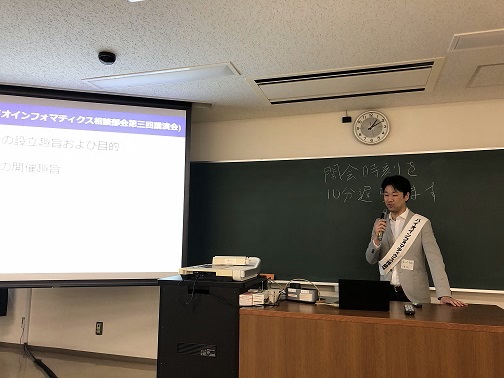
開会挨拶
今回の講演会はトピックが3つあったので、各講演者の講演内容を表としてまとめました。

講演1 江崎剛史先生「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」
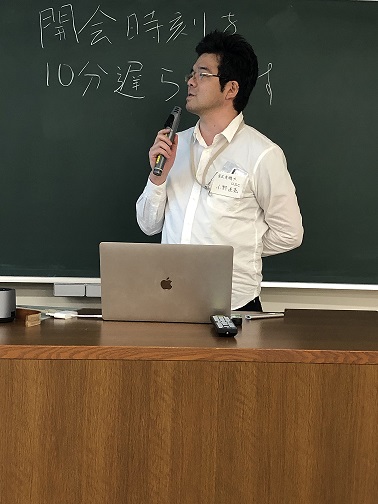
講演2 小野直亮先生「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」
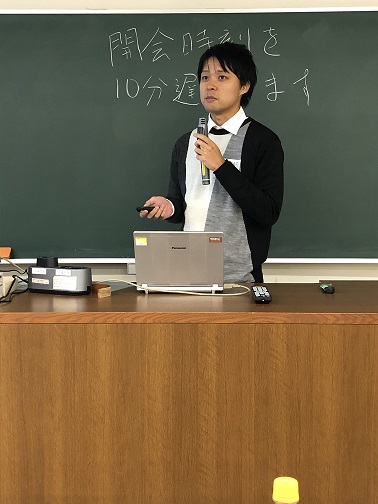
講演3 金澤慎司先生「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」

講演4 岡橋伸幸先生「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」
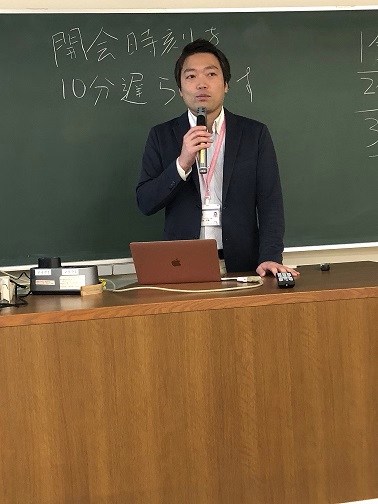
講演5 三枝大輔先生「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」

講演6 堀之内貴明先生 「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」

講演7 武藤愛先生「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」

会場の様子

集合写真


懇親会の様子。異分野交流の促進には欠かせません。

有志により二次会が開催され、さらなる異分野交流が行われました。ご参加ありがとうございました。
Published by 支部:西日本 on 10 9月 2019
日本生物工学会西日本支部では2019年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。
(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程),博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員
(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者
Published by 学会事務局 on 09 9月 2019
お使いのRSSリーダーでJounral of Bioscience and Bioengineering(JBB)をフィード購読をされる場合は、以下のURLをご登録下さい。
https://rss.sciencedirect.com/publication/science/13891723
Published by 支部:東日本 on 06 9月 2019
日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。
| 受賞年 | 受賞者(所属※) | |
|---|---|---|
| 第9回 | 2024年 (R.6) | 西川 洋平(産業技術総合研究所) |
| 第8回 | 2023年 (R.5) | 朱 博(東京工業大学) |
| 福永 圭佑(東京工業大学) | ||
| 第7回 | 2022年 (R.4) | 前田 義昌(筑波大学) |
| 堀之内 貴明(産業技術総合研究所) | ||
| 第6回 | 2021年 (R.3) | 田中 祐圭(東京工業大学) |
| 第5回 | 2020年 (R.2) | 高橋 将人(筑波大学) |
| 第4回 | 2019年 (R.1) | 羽城 周平(味の素株式会社) |
| 福谷 洋介(東京農工大学) | ||
| 中西 昭仁(東京工科大学) | ||
| 第3回 | 2018年 (H.30) | 山田千早(東京大学) |
| 第2回 | 2017年 (H.29) | 雜賀 あずさ(産業技術総合研究所) |
| 伊達 康博(理化学研究所) | ||
| 辻 雅晴(国立極地研究所) | ||
| 第1回 | 2016年 (H.28) | 大室 有紀(東京工業大学) |
| 亀谷 将史(東京工業大学) |
※所属については受賞当時の所属を掲載しています。
Published by 支部:東日本 on 06 9月 2019
【2019年度受賞者】
【関連記事】
【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ
【東日本支部]第4回 日本生物工学会東日本支部長賞 受賞者決定
Published by 学会事務局 on 03 9月 2019
第71回日本生物工学会大会(2019年9月16~18日、岡山大学にて開催)では、以下3件の本部企画シンポジウムを開催しました。
日本の酒類の種類の輸出は量、金額ともに年々増加している。日本酒(SAKE)だけでなく、日本産のワイン、ビール、ウイスキーの品質向上のための技術開発や原料などの取り組みを続けている。その成果として、酒類は世界中で行われる酒類競技会で数々の賞に輝き、その実力が高く評価され、輸出額も大幅に伸張している。日本酒、日本ワインの固有品種の甲州なども地理的表示を取得し、世界を目指した日本の酒類についてのシンポジウムを開催したい。
このシンポジウムは、本学会の特徴である産学官の連携をさらに強化すること、また会長方針である「SDGsを念頭に置いた活動を強化する」に沿って、SDGsを軸に生物工学会として産学官で今後取り組むべき方向を提示したいと考える。なお、本シンポジウムは岡山大学からの協賛をいただいた上で、一般の聴講者も一定数受入れたいと考えている。シンポジウム前半では国内の一流の有識者による講演、後半ではパネルディスカッションを開催して、議論を通して生物工学技術の活用・貢献について考える機会とし、最終的にSDGsを軸とした社会実装に繋がる産学連携技術交流のきっかけとなることを目的とする。
共催:岡山大学
幅広い生物の能力を生物工学的な手法で発揮させ、新たな価値創造につなげることが強く期待されている。また新たな測定手法の開発が新たな価値創造につながる。本セッションでは、培養技術、計測技術に焦点を当て、国内スタートアップ企業を中心にご紹介頂く。最先端の技術開発とその展開に関するディスカッションは幅広い事業展開を通じた商業的発展に向け、産学連携を介した公益につながることが期待される。
Published by 支部:東日本 on 02 9月 2019
日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2019年度は書類審査ならびに口頭発表形式の二次審査を行い、以下の三名に『日本生物工学会東日本支部長賞』を授賞いたしました。(2019.8.30)
羽城 周平 氏

福谷 洋介 氏

中西 昭仁 氏
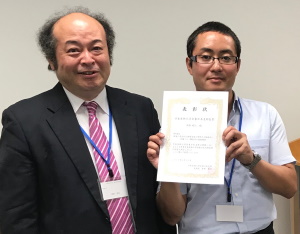
♦関連記事:
Published by 学会事務局 on 28 8月 2019
| 開催日 | 開催場所 | 詳細 |
|---|---|---|
| 第29回 2024/5/23 | 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター オンライン | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第28回 2023/5/30 | 千里ライフサイエンスセンター 山村雄一ライフホール | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第27回 2022/5/24 | 日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第26回 2021/5/25 | 日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン | ►開催案内 ⇒報告 |
| 【開催中止】 第25回 | ►開催案内 | |
| 第24回 2019/5/23 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第23回 2018/5/24 | 東京農業大学アカデミアセンター横井講堂 | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第22回 2017/5/25 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第21回 2016/5/19 | 東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第20回 2015/5/21 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第19回 2014/5/21 | サントリーホールブルーローズ | ►開催案内 ⇒報告 |
| 第18回 2013/5/24 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |
| 第17回 2012/5/25 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |
| 第16回 2011/5/27 | サントリーホールブルーローズ | ►開催案内 |
| 第15回 2010/5/28 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |
| 第14回 2009/5/29 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |
Published by 学会事務局 on 27 8月 2019
第71回日本生物工学会大会の初日(2019年9月16日)に2019年度学会賞の授賞式が開催されます。 授賞式の後に、生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞の受賞講演が行われます。また、生物工学奨励賞(江田賞・斎藤賞・照井賞)および、生物工学アジア若手賞の受賞講演は、同日午後に行われる予定です。
【日時】2019年9月16日(月)9:00~9:50
【会場】岡山大学 創立50周年記念館(金光ホール)
9:00~9:05 会長挨拶
9:05~9:10 韓国生物工学会(KSBB)会長挨拶
9:10~9:20 名誉会員、功労会員推戴
9:20~9:50 各賞授賞式
《生物工学功労賞,生物工学賞,生物工学功績賞,生物工学技術賞》
日時:2019年9月16日(月)9:55~11:30
会場:岡山大学 津島キャンパス K会場(創立50周年記念館・金光ホール)
《生物工学奨励賞(江田賞)》
日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50
会場:岡山大学 津島キャンパス I会場(一般教育D棟3階 D34)
《生物工学奨励賞(斎藤賞)》
日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50
会場:岡山大学 津島キャンパス E会場(一般教育D棟1階 D12)
《生物工学奨励賞(照井賞)》
日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50
会場:岡山大学 津島キャンパス J 会場(一般教育E棟2階 E23)
《生物工学アジア若手賞》
日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50
会場:岡山大学 津島キャンパス G会場(一般教育D棟2階 D25)
♦関連記事:【学会賞】2019年度学会賞受賞者決定のお知らせ
Published by 学会事務局 on 23 8月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 23 8月 2019
生物工学会誌 第97巻 第8号
西村 顕
今、米国でクラフトサケが人気なのはご存じでしょうか?クラフトサケとは、現地の小さなサケ・ブリュワリーで醸造される日本酒のことで、2018年にニューヨーク州で初めて開設された“Brooklyn Kura(ブルックリンクラ)”で醸造された日本酒は、現地の日本酒ソムリエたちに絶賛されました。米国内には多くの小規模な蒸留所やビール醸造所があります。一方、サケ・ブリュワリーは、Brooklyn Kura を含めて約15か所と少ないのですが、今後参入者が増加すると言われており、クラフトサケがブームになりつつあります。また、米国のみならず世界中で、日本酒の品質・味わいに対する評価は高く、その特異的な醸造技術にも熱い視線が注がれています。
日本生物工学会には賛助会員として多くの発酵・醸造関係の企業が属しています。筆者も大学卒業以来36年にわたり日本酒メーカーに勤務し、現在は、研究部門から離れて経営企画部門にいますが、企業生活の半分を研究開発部門で過ごしました。冒頭に述べた米国での日本酒醸造への熱い視線は、元技術者(研究者)として喜ばしいとともに、世界に発信できる現状の日本酒に関する技術的側面の研究成果が少ないことが気がかりです。
「清酒醸造の歴史は、たゆまない技術革新の歴史」と先輩諸氏から教えられてきました。室町時代の「菩提もと(乳酸発酵の利用)」や「火入れと呼ばれる低温熱殺菌技術(pasteurization)」、江戸時代の「寒造り」、明治時代の「速醸もと」、大正・昭和時代の「醸造協会酵母」の整備、「四季醸造工場」の建設、「連続蒸米機」「大型製麹機」「自動圧搾機」などの開発、昭和から平成にかけては、「生酒劣化防止技術」「高香気生産性酵母」の育種、「発酵制御技術」「麹菌の機能」や「清酒酵母の高発酵能」の遺伝子レベルでの解析など、まさしく技術革新の歴史でした。技術革新のたびに、日本酒の品質が向上し、おいしくなり、さらに安心・安全が付加され、大いに愛され消費されてきました。
しかし、平成から令和に時代がかわるとき、日本酒の現状には寂しいものがあります。30年近く毎年消費量が減少し、日本酒業界全体が疲弊しつつあります。消費が減少した要因は多々ありますが、本学会に席を置き、業界で長く仕事をしてきた筆者には、世界に発信できる最近の日本酒に関する革新的な技術開発、研究成果の少なさが一因ではないかと感じています。
筆者が、研究開発部門のリーダーでいたころ、部下に以下のような言葉(ある本の引用だと思いますが、書名は忘れました)を贈っています。「普通は、研究が進展するにつれ問題が整理され、わかったこととこれから検討すべき点がはっきりしてくる。にもかかわらず、問題が徐々に複雑になる場合は、テーマの筋が良くないか、研究の進め方が良くないかのいずれかだ。良い研究テーマは、どこかすっきりした美しさ、簡明さを秘めている。進め方についても、複雑になるよりも、簡明になっていく方向を選択したほうがいい。さらに重要な要件として、テーマの懐の深さがある。アイデア自身のフレキシビリティ、展開が多様となる可能性を秘めたテーマが面白い。何を美しいと感じ、何を簡明だと受け止めるか、何を懐が深いと思うか、そこに研究者のセンスが問われる。テーマの良否は、そのテーマを考え出した研究者のセンスと切り離しては考えられない。自分のテーマの素性の良否を冷静に問う姿勢を持った研究者は、自分の研究を冷静に見つめることができる。」(これらの言葉が、少しでも若手研究者の一助となれば幸いです)
最後に、令和時代には、本学会の醸造(特に、日本酒)にかかわる技術者、研究者が発奮し、世界に発信できる研究成果を生み出し、そして、日本酒産業を活気づけてくれることを期待しています。
著者紹介 白鶴酒造株式会社(取締役執行役員 経営企画室長 兼 商品開発本部長
Published by 支部:中部 on 23 8月 2019

Published by 支部:中部 on 23 8月 2019
【主催】岐阜大学 応用生物科学部(岐阜大学70周年記念事業)
【共催】日本生物工学会 中部支部
《特別講演》
《研究講演》
《ポスターセッション》
準備の都合上、講演会および懇親会への参加を希望される方は、9月2日(月)までにシンポジウム公式サイトの申込フォーム(https://gifubread.info/wpx/)からお申し込みください。
岐阜大学応用生物科学部応用生命科学課程 橋本美涼
Tel:058-293-2916(直通) E-mail
Published by 支部:北日本 on 22 8月 2019
本企画は盛会のうちに終了いたしました。多くのご参加どうもありがとうございました。
10:00~12:00 学生ポスターセッション@フロンティア棟1階エントランスホール
昼食 (役員会議)
13:20-13:25
開会の辞………松本 謙一郎(生物工学会北日本支部副支部長/北海道大学工学研究院応用化学部門)
13:25-13:55
「下水道の現状と未来像」
………………佐藤 久(北海道大学工学研究院環境創生工学部門 教授)
13:55-14:25
「余剰汚泥を活用した下排水からのバイオプラスチック生産への挑戦」
………………井上 大介(大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 准教授)
休憩
14:40-15:10
「未利用資源の海藻を原料としたバイオプラスチックの微生物合成を目指して」
………………山田 美和(岩手大学農学部応用生物化学科 准教授)
15:10-15:40
「バイオマス利活用の現場からの課題」
………………石井 一英(北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 教授)
休憩
15:55-16:20
飛翔賞受賞記念講演「情報科学と進化工学を組み合わせた分子認識タンパク質創出プロセスの開発」
………………伊藤 智之(東北大学工学研究科バイオ工学専攻 博士後期課程)
16:20-16:45
北日本支部賞受賞記念講演 「糖尿病性腎症の治療 -微生物酵素工学からのアプローチ-」
………………及川 大樹(東北大学工学研究科バイオ工学専攻 博士後期課程)
16:45~16:50
閉会の辞………魚住 信之(生物工学会北日本支部支部長 東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻)
17:40~ 懇親会(会場未定)
〇ポスター発表
ポスター発表ご希望の方は、メールにて下記担当者宛にタイトル・著者リストをお送りください。ポスター発表は、シンポジウムのテーマとは関係なく、広い意味での生物工学的内容を含む研究を発表頂けます。要旨の提出は不要です。発表者は生物工学会の会員である必要はありません。英語でのポスター発表も可能です。
Published by 学会事務局 on 20 8月 2019
<第一部:公開セミナー>
14:00~16:00 「生命誕生の神秘:生物工学者の考える大胆な仮説」
進行役:中村 史(産総研・バイオメディカル研究部門)、神谷 典穂(九州大学大学院・未来化セ)
「科学と認識の間:自然科学だけでは生命現象の完全な把握はできない・人工知能による再整理」
…三宅 淳(大阪大学・国際医工情報センター)
「生命と物質のインターフェース」
…堀 克敏(名古屋大学大学院・研究部会長)
「秩序と無秩序の間で、何かが起こった?」
…高木 昌宏(北陸先端科学技術大学 マテリアルサイエンス研究科)
<第二部>(非公開・部会委員及び事前登録者のみ)
16:30~18:00 「創造的研究:生物工学温故知新」(全員参加)
進行役:座古 保(愛媛大学大学院・理工)
コメンテーター:三宅 淳、堀 克敏、高木 昌宏
<第三部:活動方針検討会>(非公開)
20:00~22:00
進行役:堀 克敏(名古屋大学大学院)
・次年度研究部会の運営方針
・その他
Published by 支部:九州 on 16 8月 2019
10:00~10:20
「糀産業について」
……浅利 良得(有限会社糀屋本店 糀師)
10:20~10:40
「麹文化のお酒「焼酎」の魅力」
……高下 秀春(三和酒類株式会社 取締役)
10:40~11:00
「みその効用」
…… 後藤 頼信(フンドーキン醤油株式会社 品質保証部)
11:00~11:20
「最新のバイオテクノロジーと食への応用の可能性」
……塩屋 幸樹(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 講師)
11:20~11:40
「発酵食品で楽しく減塩・おいしく減塩」
……平川 史子(別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授)
11:40~12:00
「健康ウォッチ めざせ100歳」
……湯けむり健康戦隊ゲンエンジャー(別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 学生)
12:00~12:20
「食品の香りと美味しさについて」
……米元 俊一(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 客員教授)
♦第2部(13:00~14:10)
「アルコール適性検査と飲酒の功罪」
……木下 健司(武庫川女子大学薬学部健康生命薬科学科 教授)
※講演中に希望者に対してアルコール適性検査を行います。定員100名
<実験の部>(13:00~15:00)
♦〔A〕「スマホで微生物を見てみよう!」
定員10名 ①13:10~13:40 ②13:50~14:20
大坪 素秋(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 教授)
♦〔B〕「バイオリアクターでアルコールをつくってみよう!」
定員10名 ①13:10~14:00 ②14:10~15:00
陶山 明子(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 准教授)
♦〔C〕「発酵食品にかかわる微生物の遺伝子を取り出してみよう!」
定員10名 ①13:10~14:00 ②14:10~15:00
塩屋 幸樹(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 講師)
<実習の部>(13:00~15:00)
♦〔D〕「麹を使った料理教室」定員30名
浅利 妙峰(有限会社糀屋本店 代表取締役)
♦〔E〕「ゲンエンジャーによる減塩教室」
湯けむり健康戦隊ゲンエンジャー(別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 学生)
♦〔F〕「アルコール適性検査」定員100名 ※講演第2部で実施します。
<展示物の部>(10:00~15:00)
「別府大学食物栄養科学部発酵食品学科における発酵食品に取り組む学生の活動について」
(別府大学食物栄養科学部発酵食品学科 学生)
本シンポジウムは、JSPS科研費 JP19HP1234 の助成を受けたものです。
主催:日本生物工学会九州支部
共催:別府大学
Published by 支部:東日本 on 08 8月 2019
(公社)日本生物工学会東日本支部 主催
| 日時 | 2019年11月8日(金)13:00~11月9日(土)16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 大学セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催趣旨 | 「令和最初」の学生発表討論会で、研究室の中だけではみえない世界に飛び込もう!~日本生物工学会東日本支部 第14回学生発表討論会のご案内~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 学生・一般合わせて 35名程度 (定員になり次第、締め切らせて頂きます。相互交流の観点から、学生はできるだけ指導教員と一緒に参加されるようお願いします。人数に限りがありますので、広く交流を図る目的から学生さんはなるべく1研究室あたり2名程度までの申し込みにご協力下さい。学生単独での参加も可能ですが、必ず指導教員の許可を得てからお申し込みください。また、特許に係る情報を含むプレゼンテーションには対応できませんので、ご了承ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | プログラム予定
本セミナーは、三つのプログラムから構成されます。 <研究発表会> 参加学生全員に、自分の研究内容について発表していただきます。一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。発表時間は1名あたり10分間(+質疑10分間)を予定しています。全体の発表時間は限られておりますので、先着順で受付させていただき、枠が埋まった時点で学生さんの申込みを締め切らせていただきます。研究発表では研究室外の人にも実験の背景や目的、進捗状況などをわかりやすく説明することを心掛けて、スライドを用意してください。(PCはこちらでも用意いたしますが、持参等については申込後に確認します。) <自由討論会> 企業や研究所などで社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。 <基調講演、モーニングプレゼンテーション> 本セミナーでは、将来生物工学分野での活躍を目指す皆さんへのエールとして、生物工学分野で活躍されている大先輩方に、ご自身の研究歴やご経験を1日目の基調講演にてお話しいただいています。また、2日目にモーニングプレゼンテーションとして、日本生物工学会飛翔賞の受賞者による講演を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会人の皆様へ | 本討論会では、企業・法人ならびに国公立研究機関に所属する方(大学教員は含まない)を「社会人」と表記させていただきます。 本討論会では、下記「参加申込」にて「アドバイザー就任を希望」で申込みいただいた方には「学生発表討論会アドバイザー」として、日本生物工学会東日本支部長名にて依頼状を発行いたします。「学生発表討論会アドバイザー」に依頼する任務の内容、参加費、謝金につきましては、こちら(「学生発表討論会アドバイザーについて」)をご覧ください。また、アドバイザー就任を希望されない場合、一般会員の参加費をお支払いいただきますようお願い致します。今年度の本討論会で募集するアドバイザーは5名です。ご参加をよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加申込 | 10月17日(木)までに、1) 氏名、2) 性別(部屋割りに必要)、3) 一般会員(大学教員以外)/一般会員(大学教員)/学生会員/学生非会員の別、4) 社会人の場合はアドバイザー就任希望の有無、5) 所属および学生の場合は学年、6)連絡先住所・TEL・E-mail、7) その他連絡事項(特にアレルギー等で食事指定のある方はご相談ください) を記入の上、件名を「第14回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。 プログラム作成のため、学生の方には、参加申込締切後に簡単な要旨(500字程度)を作成して頂きますのであらかじめご承知おきください(要旨〆切は10月28日を予定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加費 | 参加費の支払は、当日受付時にお願いいたします。 学生会員3,000円(税込)、学生非会員4,000円(税込)、一般会員(大学教員・社会人)10,000円(税込) (いずれも宿泊代・夕朝昼食代・要旨集代込) 大学教員・社会人の皆様には、研究発表会において学生の発表に対する様々な視点からのご指摘や自由討論会での積極的なアドバイスをお願いします。 定員に限りがありますので、下記申し込み先まで早めにお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込先 | 日本生物工学会東日本支部 第14回学生発表討論会 担当 大槻隆司(山梨大学大学院医学工学総合研究部生命環境学域) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Published by 支部:東日本 on 08 8月 2019
| 社会人の皆様へ | <学生発表討論会アドバイザーについて> 本討論会では、企業・法人ならびに国公立研究機関に所属する方(大学教員は含まない)を「社会人」と表記させていただきます。 本討論会では、「参加申込」にて「アドバイザー就任を希望」で申込みいただいた方には「学生発表討論会アドバイザー」として、日本生物工学会東日本支部長名にて依頼状を発行し、以下の役割をお願いいたします。なお、アドバイザー就任を希望されない場合には一般会員として10,000円の参加費をお支払いいただきますのでご了承ください。 今年度の本討論会で募集する社会人アドバイザーは5名です。ご参加をよろしくお願いいたします。 <アドバイザーにお願いする任務>
<アドバイザーの謝金> 学生発表討論会の参加費は無料とし、アドバイザー任務に対する謝金(交通費込)として、討論会当日に日本生物工学会東日本支部より源泉徴収分差し引き後額10,000円を支払う。 |
|---|---|
| 問合せ先 | 日本生物工学会東日本支部 第18回学生発表討論会 世話人 細川正人(早稲田大学大学院先進理工学研究科) |
Published by 学会事務局 on 01 8月 2019
こちらでは、生物工学会誌に掲載された『プロジェクト・バイオ』の目次および87巻1号以降掲載記事(PDF版)がご覧いただけます。第99巻(2021年)より本コーナーの掲載記事は、J-STAGEで公開しております。
| 掲載記事 | 著者(*代表者) | 所属(掲載当時) | 巻–号–頁 (掲載年) |
|---|---|---|---|
| 酒蔵発のタンパク質受託生産サービス | 幸田 明生*・阪本 薫・山田 尚平・橋本 一俊・仙波 弘雅・木田 真理衣・畑 健介・加戸 悠・山田 浩之・坪井 宏和・坊垣 隆之 | 大関 (株) 総合研究所 | 98-12-706 (2020) |
| ふくしま発宇宙日本食の開発 | 小野 洋一 | 日本大学研究推進部知財課 | 98-7-382 (2020) |
| ヨーグルトにユニークな特徴を付与するプロテアーゼの開発 | 品田 敦子 | (株) 合同酒精 | 98-4-203 (2020) |
| UV-LEDにより育種した新規清酒酵母「LED夢酵母」 | 岡久 修己 | 徳島県立工業技術センター 食品・応用生物担当 | 98-1-42 (2020) |
| 微生物活用への取組み~NBRCが提供する多彩な乳酸菌とデータプラットフォーム~ | 宮下 美香*・渡邉 瑞貴・木村 明音 | 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター(NBRC) | 97-12-770 (2019) |
| 事業化へ向けた研究開発材料としてのCHO細胞の樹立 | 源治 尚久 | (株) chromocenter | 97-7-450 (2019) |
| ナノ粒子の食品への展開 | 金城 綾乃*・尾形 望嘉・松尾 タケル・江口 暢次朗・鶴丸 早織・平野 隆・福田 宏太郎・原 敏夫・永井 朋子・松原 正東 | (株) 先端医療開発 | 97-6-365 (2019) |
| 玄米発酵飲料 玄米オリザーノ®試飲後の心理学的変化~4象限マトリクス「KOKOROスケール」を用いた新しい解析と近未来展望~ | 益崎 裕章1*・片岡 洋祐2・満田 昌代3・藤井 力4・阿部 啓子5 | 1 琉球大学, 2 (株) Kokorotics, 3 会津天宝醸造 (株), 4 酒類総合研究所, 5 東京大学 | 97-5-296 (2019) |
| L8020乳酸菌と特許ビジネス | 二川 浩樹 | 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 | 97-4-230 (2019) |
| ゲノム編集による養殖魚の品種改良―筋肉増量マダイの作出― | 家戸 敬太郎 | 近畿大学水産研究所 | 97-1-42 (2019) |
| ニホンウナギの完全養殖技術の現状と展望 | 野村 和晴 | 水産研究・教育機構 | 96-12-722 (2018) |
| 沙漠海岸にバイオマス・コンビナートを造る | 倉橋みどり | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | 96-10-605 (2018) |
| ジャガイモマイクロチューバー生産技術の開発,実用利用,応用 | 大西 昇 | キリン (株) | 96-9-552 (2018) |
| 「きぼう」日本実験棟を利用した高品質タンパク質結晶生成実験の新しい展開 | 木平 清人*・永尾 紗理・和田 理男・石田 卓也・山田 貢・岩田 茂美・吉崎 泉 | 宇宙航空研究開発機構 | 96-8-484 (2018) |
| なぜ我々は土壌微生物叢の動態を知りたいのか | 藤田 朋宏 | (株) ちとせ研究所 | 96-1-40 (2018) |
| 有毒藻類の大量培養による下痢性貝毒認証標準物質の製造 | 内田 肇1・渡邊 龍一1・松嶋 良次1・及川 寛1・石原 賢司1・鈴木 敏之1*・山﨑 太一2・川口 研2・高津 章子2 | 1 水産研究・教育機構, 2産業技術総合研究所 | 95-12-764 (2017) |
| 持続可能な生産と消費を目指すアグロフォレストリー | 林 建佑 | (株) フルッタフルッタ | 95-11-682 (2017) |
| 玄米発酵飲料の開発と機能の検証 復興支援,そして健康・長寿への道 | 満田 昌代1*・金本 淳一1・益崎 裕章2 | 1会津天宝醸造 (株), 2琉球大学 | 95-9-568 (2017) |
| 多変量解析に一石を投じる―ConfeitoGUIplusの開発 | 萬年 一斗1・尾形 善之2・鈴木 秀幸1* | 1かずさDNA研究所, 2大阪府立大学 | 95-7-420 (2017) |
| 生スピルリナの研究開発とタベルモ事業の挑戦 | 尾張 智美 | (株) ちとせ研究所 | 95-2-100 (2017) |
| 飲み込んでも安全な乳酸菌抗菌ペプチドの口腔ケア剤の開発 | 永利 浩平 | (株) 優しい研究所 | 94-12-794 (2016) |
| アスベストの有無を簡単に検知できるタブレット顕微鏡 | 黒田 章夫 | 広島大学 | 94-8-507 (2016) |
| ビフィズス菌の新しい食べ方を提案する「BifiX フローズンジェリー」の開発 | 瀧田 佳樹*・伊澤 桂・玉井 敏博 | 江崎グリコ (株) | 94-6-352 (2016) |
| バイオ高速精製カラム「CIM®モノリス」~モノリス型担体の進化と未来~ | 青木 裕史 | 昭和電工 (株) | 94-5-286 (2016) |
| 「腸内細菌検査」を迅速簡便化する検体プールとPCRによるスクリーニング法の開発 | 松本 弘嵩・東 隆寛・荒川 琢* | 東洋紡 (株) | 94-4-212 (2016) |
| 宇宙環境下における閉鎖居住施設における食料生産用養殖技術の開発 | 遠藤 雅人 | 東京海洋大学 | 94-1-36 (2016) |
| バイオ画像自動分類ソフトウェアCARTAの開発 | 朽名 夏麿 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科, エルピクセル (株) | 93-12-760 (2015) |
| トドマツの枝葉を利用した空気浄化剤の開発 | 大平 辰朗 | 森林総合研究所 | 93-11-698 (2015) |
| 緑茶カテキン(ガレート型カテキン)の機能性研究と特定保健用食品の開発 | 卯川 裕一*・提坂 裕子 | (株) 伊藤園 | 93-10-63 (2015) |
| 健康長寿への貢献を目指したりんごポリフェノール配合食品の開発 | 灘岡 勲 | カルピス (株) | 93-9-558 (2015) |
| カスピ海ヨーグルトに含まれる新規機能性糖質ラクトビオン酸の開発 | 桐生 高明*・木曽 太郎・中野 博文・村上 洋 | 大阪市立工業研究所 | 93-8-494 (2015) |
| 北海道食品機能性表示制度【ヘルシーDo】の経緯と展望について | 田村 耕志 | 北海道経済部食関連産業室研究集積グループ | 93-7-416 (2015) |
| 光センシングと自然免疫応答を利用した食品機能性評価法 | 數村 公子 | 浜松ホトニクス (株) | 93-6-356 (2015) |
| みえ発「地産地消型バイオリファイナリー」 | 田丸 浩 | 三重大学大学院生物資源学研究科 | 93-1-40 (2015) |
| グリーンフェノールと高機能フェノール樹脂生産への挑戦 | 乾 将行1*・郷 義幸2 | 1地球環境産業技術研究機構, 2住友ベークライト(株) | 92-12-680 (2014) |
| 健康寿命伸長のための大腸内ポリアミン増強食品の開発 ―狙った生理活性物質を腸内細菌に産生させることができるのか?― | 松本 光晴 | 協同乳業 (株) | 92-9-516 (2014) |
| 「渾沌(カオス)」の制御法…複合培養系を制御するコツ | 篠原 信 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 92-7-372 (2014) |
| ニワトリ抗体の医薬品への応用展開 | 庄屋 雄二・豊浦 雅義* | (株) ファーマフーズ | 92-6-312 (2014) |
| 摂食・嚥下障害のサポート―食の支援ステーションの紹介― | 井上 誠 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 | 92-5-242 (2014) |
| 環境微生物を利用した石油・天然ガス資源開発技術 | 藤原 和弘*・佐藤 朋之・川村 太郎・浅野 貴博 | 中外テクノス (株) | 92-4-194 (2014) |
| 咀嚼・嚥下困難者向け食品の品質評価 | 神山かおる | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 92-3-120 (2014) |
| 地域農業の力で糖質が湧き続ける?!セルロース系原料糖化技術「CaCCO」の現在と未来 | 徳安 健*・池 正和 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 91-11-660 (2013) |
| DHA結合型リン脂質(PC)の研究開発 | 大久保 剛 | 日油 (株) | 91-5-264 (2013) |
| ビトリゲルの開発とその再生医療,創薬,動物実験代替法,化粧品および食品の分野での実用化構想 | 竹澤 俊明 | 農業生物資源研究所 | 91-4-214 (2013) |
| マイコトキシン汚染検体前処理用カラム「Trapper DON/NIV」の開発 | 佐々木 道代・加藤 美穂子 | (株) フロンティア研究所 | 90-12-800 (2012) |
| 酵素・微生物を利用した地域特産農産物の食品加工 | 西脇 俊和 | 新潟県農業総合研究所 食品研究センター | 90-11-742 (2012) |
| 乳糖を原料とした新規機能性オリゴ糖「ラクトビオン酸」の開発 | 木村 隆 | ユニチカ (株) | 90-9-595 (2012) |
| がごめ昆布をめぐる食クラスターの取組み | 仲川 昇一 | 北海道食産業総合振興機構 | 90-9-598 (2012) |
| 地域の特産物を用いたブランド発泡酒の開発 | 梶川 悟史 | 宮崎ひでじビール (株) | 90-7-442 (2012) |
| 名水分析,名水鑑定から見えてくること | 森川 博代 | 有限会社 名水バイオ研究所 | 90-4-204 (2012) |
| 高機能タマネギの開発と地域ブランド化 | 岡本 大作 | 有限会社植物育種研究所 | 90-3-144 (2012) |
| 低エミッシヨン型水産加工を目指したウニ魚醤油の開発 | 田中 真人 | (株) 丸恭水産 | 90-1-42 (2012) |
| 世界中の人々が安全な水を飲めるように | 小田 兼利 | 日本ポリグル (株) | 89-11-692 (2011) |
| 構造改革特別区域制度を活用したどぶろくの製造 | 吉川 修司 | 北海道立総合研究機構 食品加工研究センター | 89-8-504 (2011) |
| 戦艦「大和」の呉から届ける「海軍さんの麦酒」 | 佐々木雅治 | 呉ビール (株) | 89-5-274 (2011) |
| 「地ビール」は文化へ【松江地ビールビアへるん】 | 矢野 学 | 島根ビール (株) | 89-3-134 (2011) |
| 日本橋茅場町で造られた日本最初のビール“幸民麦酒” | 辻 巌 | 小西酒造 (株) | 89-2-84 (2011) |
| ドイツ発、牛久経由、世界行き | 高野 貫冶・角井 智行* | シャトーカミヤ 牛久ブルワリー | 89-1-32 (2011) |
| 植物工場は究極の地産地消 | 中村 謙治 | エスペックミック (株) | 89-1-34 (2011) |
| 大山の味“Daisen G Beer” | 岩田 秀樹 | 久米桜麦酒 (株) | 88-12-686 (2010) |
| 岡山の地ビール「独歩」―15年の歩みとこれから― | 宮下 晃一 | 宮下酒造 (株) | 88-11-618 (2010) |
| 「ビールを楽しむ」きっかけづくりを | 園田 智子 | (株) イクスピアリ | 88-10-544 (2010) |
| 「Panaferd-AX」の開発 | 坪倉 章 | JX日鉱日石エネルギー (株) | 88-9-492 (2010) |
| 鹿児島ならではのビールを目指して 城山ブルワリー | 倉掛 智之 | 城山観光ホテル | 88-9-494 (2010) |
| 「整腸・Ca吸収促進Wの効果」乳果オリゴ糖の開発 | 藤田 孝輝 | 塩水港精糖 (株) | 88-7-362 (2010) |
| 「ビール」その100年の夢を紡ぐ,品質本位のもの造り | 山口 司 | ワダカン (株) | 88-7-364 (2010) |
| 「糖質ゼロ」清酒の開発 | 犬堂 雅栄*・堤 浩子 | 月桂冠 (株) | 87-9-448 (2009) |
| =新しい微生物資源を求めて③= NITEの海外微生物探索:モンゴル編 | 安藤 勝彦 | 製品評価技術基礎基盤機構(NITE) | 87-8-404 (2009) |
| =新しい微生物資源を求めて②= NITEの海外微生物探索:ベトナム編 | 安藤 勝彦 | 製品評価技術基礎基盤機構(NITE) | 87-7-352 (2009) |
| =新しい微生物資源を求めて①= NITEの海外微生物探索:インドネシア編 | 安藤 勝彦 | 製品評価技術基礎基盤機構(NITE) | 87-6-298 (2009) |
| 新ジャンル「麦とホップ」の開発 | 坂下 聡 | サッポロビール (株) | 87-5-252 (2009) |
| As busy as a bee; roses are blue! | 中村 典子・田中 良和* | サントリーホールディングス (株) | 87-4-206 (2009) |
| 「納豆のススメ」日本初遺伝子組換え食品 | 池田 順子 | 有限会社A-HITBio | 87-3-150 (2009) |
| “愛・地球博”が残したもの ~バイオマス・プラスチックの本格普及へ向けて | 大島 一史 | 財団法人バイオインダストリー協会(JBA) | 87-2-98 (2009) |
| 醤油から生まれた機能性成分SPS | 真岸 範浩*・松下 裕昭・古林 万木夫 | ヒガシマル醤油 (株) | 87-1-34 (2009) |
| セリシンの機能利用と製品開発 | 辻本 和久・佐々木 真宏* | セーレン (株) | 86-11-570 (2008) |
| 甲州きいろ香にみるワインの個性化醸造法 | 小林 弘憲1*・故 富永 敬俊2 | 1メルシャン (株), 2ボルドー第二大学醸造学部 | 86-7-366 (2008) |
| ALA配合液肥「ペンタキープ」の商品開発 | 岩井 一弥 | コスモ石油 (株) | 86-4-200 (2008) |
| トレハロースを身近に,夢の糖一般化大作戦 | 姫井 佐恵 | (株) 林原商事 | 86-3-136 (2008) |
| メチル化カテキンの抗アレルギー作用と「べにふうき」緑茶の開発 | 山本(前田)万里 | 農研機構 野菜茶業研究所 | 86-2-92 (2008) |
| 2つの乳酸菌から生まれた高血圧予防飲料の開発 | 水澤 進 | (株) ヤクルト | 86-1-26 (2008) |
| 新規な分離技術「超音波霧化分離」 | 松浦 一雄1*,3・矢野 陽子2・脇坂 昭弘3 | 1(株) 本家松浦酒造場, 2立命館大学, 3産業技術総合研究所 | 85-12-554 (2007) |
| 北海道えりもから発信する魚醤油の現在と未来 | 吉川 修司 | 北海道立食品加工研究センター | 85-11-500 (2007) |
| 安全な食材で食卓を囲むために-残留合成抗菌剤検査方法の開発 | 加藤 美穂子 | (株) フロンティア研究所 | 85-10-456 (2007) |
| 産学官共同研究による「福岡オリジナルソフト清酒」の開発 | 松江 勇次 | 福岡県農業総合試験場 | 84-12-506 (2006) |
| 研究用ヒト3次元培養組織「ラボサイト:LabCyte」 | 加藤 雅一 | (株) ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 84-6-248 (2006) |
| 熱応答性磁性ナノ粒子( Therma-Max )の開発~万年主任社長奮闘記~ | 大西 徳幸1*・近藤 昭彦1,2 | 1マグナビート (株) , 2神戸大学 | 84-5-204 (2006) |
| 最高のセキュリティを求めて | 田中 昌司 | バイオニクス (株) | 84-4-154 (2006) |
| “すっきり”と“しっかり”の両立で実現! ―「キリン のどごし<生>」の開発― | 太田 雄人 | キリンビール (株) | 83-12-582 (2005) |
| スーパードライ酵母で実現した味-「アサヒ新生」の開発- | 髙橋 浩一郎 | アサヒビール (株) | 83-11-532 (2005) |
| 「サッポロドラフトワン」による新スッキリ味の創出 | 中村 剛 | サッポロビール (株) | 83-10-494 (2005) |
| 「ビールの泡」エンジェルリング | 近藤 平人 | サントリー (株) | 83-9-454 (2005) |
Published by 部会:代謝工学研究部会 on 29 7月 2019
日本生物工学会代謝工学研究部会では2019年度の活動の一環として、技術交流会を開催します。ご好評いただきました過去の交流会につづき、第7回交流会でも研究部会関係企業や大学院生、若手研究者を対象として、代謝シミュレーション技術の講習・実習を行います。論文発表されている研究事例を参考に、遺伝子破壊による代謝経路の設計や律速反応候補を抽出するための手法について、実際に解析を行なう際にどのように計算を行なうか解説・体験します。代謝シミュレーションの実行環境はMatlab(体験版)を利用します。
詳しくは、大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座ホームページ(http://www-shimizu.ist.osaka-u.ac.jp/hp/me.html)をご覧下さい。
Published by 学会事務局 on 24 7月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 24 7月 2019
生物工学会誌 第97巻 第7号
金川 貴博
自然界では、どの種の生物も、他の種の生物との係わりあいの中で生活している。ヒトでは、他の種の生物を食して生きているという形での係わりあいだけでなく、ヒトの皮膚の表面や腸内には多種類の細菌が生息していてヒトの健康に係わっている。だから、皮膚表面や腸内に、どんな種類の細菌がどれくらいいて、どんな働きをしているのかを解明したいと思うが、複数種の細菌が混じった状態のものを解明するのは、ほぼ不可能である。したがって、皮膚表面や腸内にいる細菌の様子は、よくわからない。こう言うと「最新のDNA解析技術を使えば、かなりわかるはずだ」という反論が出てくるだろうが、本当にそうなのか。DNA解析を行えばたくさんのデータは出る。しかし、そのデータは試料の細菌相をどの程度に反映しているのだろうか。
細菌相解析上の最初の問題点は、試料中のどの細菌からも等しくDNAを抽出する手段がないという点である。DNAの抽出のしやすさは菌ごとに異なり、DNA抽出段階で大きな偏りが生まれる。DNA抽出後の操作としては、菌の同定の指標である16S rRNA遺伝子をPCR増幅することが多いが、ここでも偏りや誤りを生じる。この点について、私は総説に詳述した1)。この総説はELSEVIER社のMost Downloaded JBBArticles(最近90日間)に今もランクインしており、引用回数も増え続けて500回を超えた(2019年5月に確認)。微生物集団を解析したデータには偏りがあることが広く認識されつつあるようである。解析データはあまり当てにならない。
一方で、微生物集団の利用は大いに進んでいる。微生物の利用というと発酵食品や医薬品製造に目が行きやすいが、実際にもっとも微生物が利用されているのは廃水処理分野である。しかしながら、廃水処理分野に微生物の専門家は私以外にはほとんどいない。そもそも微生物学の基本は純粋培養であり、他の種の生物との係わりを断ち切った特異な環境で育つ微生物を対象にして出来上がった学問は、特異な環境(純粋培養系)にしかあてはまらない。自然界の微生物集団を扱うには、現在の微生物学とは異なる考え方が必要であり、微生物学者には不向きな分野と言わざるをえない。どの微生物にも当てはまるような共通事項は使えるが、使える事項はわずかしかない。
それでは、微生物学者は微生物集団にどう挑めばよいのか。ひとまず微生物学を忘れて、微生物集団を注意深く眺めることである。目の前で起こっていることが真実の姿である。微生物集団の中身を解析するのではなくて、さまざまな条件のもとで集団が示す行動を十分に見ることが必要であり、これには膨大な時間がかかる。これを自分で行うのは大変だから、こういう作業は他の分野の人に任せよう。他人の実験や現場のデータを眺めた結果、微生物学者の強みを発揮できそうな局面が来たら乗り出す。「先手必勝」ではなくて「後手楽勝」をねらってみよう。
微生物集団の利用は医学分野でも始まっている。「糞便移植」である。これは、お腹の調子が悪い人を治療するために、お腹の調子がいい人から便をもらって腸内に挿入する方法である。お腹の調子がいい人は、腸内の微生物相健全なのであるから、健全な人から出た新鮮な便を調子が悪い人に入れて腸内に健全な微生物相を作る。「善玉菌?」を入れるのではなく、微生物集団をそのまま使う。廃水処理分野の発想と同一である。
微生物集団の利用は今後ますます重要になるだろう。微生物集団に挑むには、微生物学の常識を捨てて、研究対象をよく見て、考え方を組み立てなおす作業が必要になる。
1) Kanagawa, T.: Bias and artifacts in multitemplate PCR, J. Biosci. Bioeng., 96, 317 (2003).
著者紹介 京都先端科学大学バイオ環境学部(特任教授)
Published by 学会事務局 on 23 7月 2019
2019年度生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2019は、7月20日(土)~21日(日)に、琵琶湖畔近江白浜の旅館『白浜荘』(滋賀県高島市)にて開催されました。
⇒活動報告はこちら
Published by 支部:九州 on 23 7月 2019
| 日時 | 2019年10月5日(土) |
|---|---|
| 場所 | コンパルホール 1階文化ホールおよび4階調理実習室 (大分県大分市府内町1丁目5番38号) |
| 日時 | 2019年12月7日(土)9:00~17:30(予定) |
|---|---|
| 会場 | 長崎大学 水産学部(長崎県長崎市文教町1-14) |
Published by 支部:九州 on 23 7月 2019
第26回日本生物工学会 九州支部長崎大会を長崎大学 水産学部にて下記の要領で開催します。
多数のご参加をお待ち申し上げます。
⇒一般講演・学生賞講演プログラム
| 日時 | 2019年12月7日(土)9:30~19:30 |
|---|---|
| 場所 | 長崎大学 水産学部(長崎県長崎市文教町1-14)→アクセス |
| プログラム | 【一般講演】
【特別講演】特別講演会場(大講義室)13:10~14:10 学会長挨拶…髙木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学)
|
| 参加費 | 一般2,000円、学生1,000円 (税込、講演要旨集代を含む。当日受付でお支払いください。) |
| ミキサー | 長崎大学 大講義室 17:30~19:30(参加費無料) |
| 講演申込み締切日 | 2019年 |
| 講演要旨締切日 | 2019年11月1日(金)必着 |
| 問合せ先 | 長崎大学 水産学部 日本生物工学会九州支部 長崎大会実行委員長 小田 達也 〒852-8521長崎県長崎市文教町1-14 E-mail: |
終了しました。多数のお申込みありがとうございました。
<講演申込み要領>
E-mailでお申し込みください。九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。
なお、送信時の件名は「第26回支部大会/発信者名」とし、下記項目をメール本文に記載してください。
1)講演題名
2)発表者:氏名(ふりがな)、所属略称(連名の場合は講演者氏名の前に○印)
3)連絡先:郵便番号、住所、所属、氏名、TEL、FAX、E-mailアドレス
4)学生賞審査希望の有無:希望する場合、審査講演のセッション(修士の部・博士の部のいずれか)と承諾を得た指導教員名を明記してください。
【学生賞】学生会員の研究奨励のために、九州支部学生賞を設けています。一般講演の申し込みをされる学生会員で学生賞の審査を希望される方は、申し込み時に学生賞の希望(修士の部・博士の部いずれか)と承諾を得た指導教員名を明記してください。なお、申し込みは指導教員あたり各賞1名まででお願いします。
(注)一般講演は一人一題のみで、複数の講演はできません。また、すべての講演は液晶プロジェクターを用いて行う予定です。PC(Macの方は接続アダプターも含めて)は講演者ご自身でご持参下さい。接続はVGA端子(D-Sub 15ピン)です。なお、PCを持参できない場合は、その旨をあらかじめお知らせください。
<申込み先>
長崎大学 水産学部 日本生物工学会九州支部 長崎大会実行委員会
(担当)山口 健一 E-mail:
受信後、確認のメールと講演要旨集執筆要領を併せてお送りします。
Published by 若手会 on 22 7月 2019
本年度の生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2019は7月20日~7月21日に、琵琶湖国定公園白浜荘にて開催されました。
おかげさまをもちまして全国から111名(一般47名、学生64名)の御参加をいただき、7件の特別講演、59件のポスター発表、全員参加の座談会を行いました。
はじめに
若手会会長の今中先生にご挨拶いただき、講演会を開始しました。

講演会
初日の講演会では6名の先生方にご講演いただきました。研究内容だけではなく、研究とは何か、研究開発の苦労など、多彩なトピックをご講演頂きました。
特別講演1
『理学研究者が行うタンパク質工学~アカデミアが目指すべき技術開発とは?』
高木 淳一 先生(大阪大学 蛋白質研究所)

特別講演2
『生物と機械の融合—心筋・電気器官その他を用いた独創デバイス—』
田中 陽 先生(理化学研究所 生命機能科学研究センター)

特別講演3
『特許出願する?しない?究極の選択!~そもそも発明って何?~』
前田 治子 先生(京都北山特許法律事務所)

特別講演4
『腸内フローラ検査サービスMykinso立ち上げからの4年間を振り返って』
竹田 綾 先生(株式会社サイキンソー)

特別講演5
『製薬企業における生物工学出身者のキャリアパス』
葛本 雅宣 先生(塩野義製薬株式会社)

特別講演6
『ワイルドはセクシーである~夢のない研究なんてNGだぜ~』
内藤 健 先生(農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センター)

活発な討論が行われました。

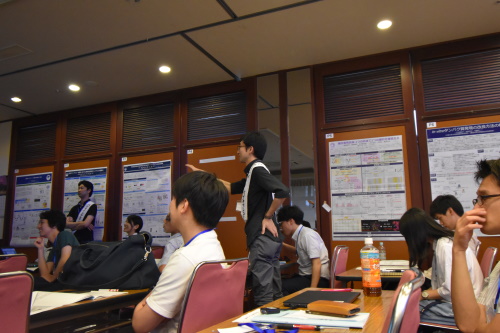
ポスターセッション
59件のポスター発表で活発な議論が行われました。
BBQ
白浜荘でバーベキューの夕食を楽しみました。
学会長の髙木昌宏先生が乾杯の挨拶をされました。
討論会
朝方まで、研究やキャリアに関して討論が盛り上がりました。
講演会
二日目の講演会ではSpiber株式会社の村上先生にご講演いただきました。
特別講演7
『構造タンパク質の実用化への挑戦』
村上 賢宏 先生(Spiber株式会社)

座談会
「これからの未来の話をしよう」というテーマで、研究の未来や今後のキャリアパスについて、全員参加型の座談会を行いました。


授賞式
1日目のポスター発表の投票結果から各ポスター賞が授与されました。
最優秀ポスター賞
・橋本 講司(The Scripps Research Institute)
P10: 人間が作った文字を大腸菌が覚えた!人工塩基対による遺伝暗号拡張可能性の検証

優秀ポスター賞
・藤野 美穂(広島大学)
P12: シンプル酵素触媒における酵素の高機能化に関する研究

・今井 祐太(名古屋大学)
P46: 細胞形態情報解析による神経系細胞の薬剤応答プロファイリング

・大林 洋貴(九州大学)
P15: 薬物キャリアへの応用を志向したペプチド-小分子共集合体の創製

・白井 薫(石川県立大学)
P50: メタン発酵消化液による植物病原菌の生育抑制効果

特別ポスター賞
・佐藤 崚(九州大学)
P04: タンパク質の片末端集合化を可能にするPolyTagの機能性評価

・緋田 安希子(広島大学)
P51: 植物病原菌は何を目印にして宿主を探す?

・東 秀隆(岡山大学)
P17: 超好熱菌由来タンパク質CutA1を利用した高次構造体の構築と分子認識素子への応用

優秀ポスターデザイン賞
・北村 瑠璃子(大阪府立大学)
P28: サンゴに共生するRuegeria属細菌の分布調査を目的とした環境DNA検出法の検討

おめでとうございます。
おわりに
実行委員から、お礼申し上げ、閉会とさせていただきました。
会場で集合写真を撮影しました。

本セミナーをご支援いただきました日本生物工学会(本部、関西支部、バイオインフォマティクス相談部会)、 加藤記念バイオサイエンス振興財団、ご協賛・ご寄附を頂きました多数の企業様(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、宮野医療器株式会社、株式会社島津製作所、株式会社池田理化、三洋貿易株式会社、月桂冠株式会社)に深く御礼申し上げます。また、ご多忙の中、講演をお引き受けくださいました講師の先生方、会場のお世話をしてくださいました白浜荘の皆様、本セミナー開催の機会をくださりサポートくださいました若手会役員の先生方に心より感謝申し上げます。そして、全国よりお集まりいただきました参加者の皆様、誠にありがとうございました。本セミナーをきっかけに、皆様の交流の輪がさらに広がることを祈念しております。
来年も福岡での夏のセミナーにてお会いしたいと思います。
生物工学若手研究者の集い夏のセミナー2019 実行委員一同
青木 航(京大)
安藤 晃規(京大)
岡橋 伸幸(阪大)
曽宮 正晴(阪大)
西村 勇哉(神戸大)
堀之内 貴明(理研)
三浦 夏子(阪府大)
Published by 部会:バイオ計測サイエンス on 16 7月 2019
バイオ計測技術が生み出す膨大なデータから、役に立つ知見を見つけるには、データを解析するテクニックが必要となります。表計算ソフト上で気合と根性と膨大な時間を使って行ったデータ処理が、Pythonというプログラミング言語を覚えれば、あっという間に終わります。Pythonは、バイオインフォマティクス技術を活用したデータマイニング、AIの活用への近道です。そこで本講座はデータ解析の必要に迫られた大学院生、研究者を対象に、学生チューターに助けてもらいつつ自習用教材を用いて、Pythonを使う基礎を学びます。また、少人数でのハンズオンセミナーを行い、課題解決へPython活用法を実践します。今回は生物工学分野の学生、および社会人を対象として行います。
自習形式。教材をもとに自分で学習。わからないところはチューターに聞く。
Published by 学会事務局 on 08 7月 2019
こちらでは、生物工学会誌に掲載された『生物材料インデックス』がご覧いただけます。第99巻(2021年)より本コーナーの掲載記事は、J-STAGEで公開しております。
Published by 支部:東日本 on 03 7月 2019
2019(令和元)年7月2日
日本生物工学会 東日本支部長
青柳 秀紀
日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ
日本生物工学会東日本支部は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与いたします。
本年は、8月19日(月)を応募締切とし、書類選考による一次選考通過者を対象として、8月30日(金)に第二次選考を兼ねた発表会を行います。なお、同発表会は、日本生物工学会会員に対して公開いたします。
多くの会員の皆さまのご応募をお待ちしています。
| 日程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 応募について | ||||||||
〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1 | ||||||||
| 日本生物工学会東日本支部長賞 授賞規程 | ||||||||
|
Published by 支部:東日本 on 02 7月 2019
今年度の「生物工学フォーラム」では、第1部は「人工知能は生物工学の夢を見るか?」と題し、最近話題の人工知能を駆使した創薬・生物工学研究を推進されているフロントランナーの3人の先生方にご講演いただきます。
また第2部では、日本生物工学会東日本支部で活躍する若手研究者を顕彰する「日本生物工学会東日本支部長賞」の選考会を兼ねた、受賞候補者の研究講演会を行います。
⇒日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ(応募締切:8月19日)
| 日時 | 2019年8月30日(金)13:00~ |
|---|---|
| 場所 | キャンパスイノベーションセンター東京 国際会議室 (東京都港区芝浦3-3-6)JR田町駅東口前 |
| プログラム | 第1部 「人工知能は生物工学の夢を見るか?」
第2部 「日本生物工学会東日本支部長賞候補者講演会」
|
| 参加費 | 【フォーラム】
|
| 事前登録締切 | 2019年 ※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。 |
| 申込方法 | こちらのフォームに必要事項(氏名、所属、会員種別、E-mail、TELおよび懇親会参加の有無)を明記してお申込みください。 |
| 申込・ 問合せ先 | 日本生物工学会 東日本支部 支部長: 青柳 秀紀(筑波大)E-mail 担当幹事: 上田 宏(東工大)E-mail 柘植 丈治 (東工大)E-mail |
Published by 若手会 on 24 6月 2019
盛会のうちに終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
生物工学若手研究者の集い(若手会)では、例年開催している若手会総会・交流会に加え、「イブニングセッション」を開催します。皆様どうぞご参加ください。
18:00~18:10 若手会総会
18:10〜20:00 イブニングセッション・若手会交流会
Published by 学会事務局 on 24 6月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 21 6月 2019
Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の2018年のImpact Factorが2.032(2017年は2.015)と発表されました。英文誌編集委員会では、日々迅速かつ厳正な審査を続けています。今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。
2018 Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019)
Published by 学会事務局 on 20 6月 2019

この度、日本生物工学会の第22代会長を拝命いたしました、北陸先端科学技術大学院大学の髙木昌宏でございます。伝統ある本学会の会長ということで、その責任の重さを痛感しております。不安もございますが、副会長の福崎英一郎先生(大阪大学)、秦 洋二氏(月桂冠)、ならびに理事・役員、そして会員の皆様の御助力により、2022年(令和4年)の創立100周年記念行事に向けて、一層の学問領域の活性化と会員サービスの向上に励みたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
以下に、私が会長就任に際して思うところを述べさせていただきます。
【取り組むべき課題:アクションプラン】
第19代会長の園元謙二先生が提唱された3つのアクションプラン、つまり、
について、私の在職期間中も粛々と実行したいと考えています。特に力を入れたいのは、産業界との連携と学会誌の充実です。産学連携委員会のアンケート調査でも、産業界から「学会活動を、広報の場として活用したい」との声が寄せられており、そのご要望にお応えしたいと考えております。また、ユニークな企画で好評を頂いている和文誌、インパクトファクターが2を越えた英文誌についても、さらなる充実に向けて知恵を絞りたいと考えております。
【生物工学会らしさ:密度の濃い人間関係】
上述したプランは、他学会とも共通する課題です。すると「生物工学会らしさとは?」について、常に意識する必要があります。私どもの学会の歴史を振り返りますと、その発端は、学生の企画に基づいた「同窓会組織」でした。その後、醗酵工学会へと発展するまでの歴史は、第5代会長の照井堯造先生のお言葉を借りれば、「学会組織としての健全な発達への要望と、同窓会組織への郷愁」の葛藤の歴史であったそうです。我々の学会に独特の雰囲気を感じておられる向きもあるそうですが、その理由を考えるに、「上意下達ではない同窓会的組織」であった設立の思想が、脈々と受け継がれているからです。会員の皆様が相互に、他学会とは異なった密度の濃い人間関係を構築しつつ、忌憚のないご意見・ご要望を、学会に向けて発信していただければと思います。この雰囲気こそが、生物工学会らしさであり、発展のエネルギーです。
【学理と技術:応用基礎研究のすすめ】
成熟期を迎えた日本の科学技術において、学理と技術の関係については、再認識する必要があると考えています。物理学者の上田良二先生は、次のように述べています。「日本人の多くは、学理を応用して技術を開発するものだと思っている。しかし、ガリレイは望遠鏡を改良したが、幾何光学を勉強してからその仕事をしたのではない。蒸気機関の発達の後を追って熱力学が確立されたことはよく知られている。日本人は、学理を生むような技術を開発したり、技術のなかから学理を育てた経験に乏しいから、教壇に立つ先生まで、学理が先で技術が後と思い込んでいる。」つまり、応用研究や実用化が先に進んでから、基礎研究分野が生まれる「イノベーション」を仕掛けることがもっとできるはずです。科学史を紐解くと、黒体輻射が量子力学を生み、アスピリンが脂質メディエーター研究を生んだように、「技術が先で学理が後」となる「応用基礎研究」について意識した研究テーマ設定について、より真剣に考える必要があると思います。
「バイオテクノロジー」は、典型的な学際領域であり、さまざまな知識と手法が相互に対峙・融合して発達が遂げられています。創造的研究とは、結局は学問と学問が出会う境界領域で生まれています。そして、それはとりもなおさず人と人の出会いに端を発するのです。工学、農学、医学、薬学などの学問分野、さらには、産官学など、異なった種々の価値観を相互に、そして積極的に、刺激、対峙、融合させ、会員の皆様が、イノベーション創出に関わるための一助となることが、学会活動の大切な使命です。
2019年6月
日本生物工学会会長
髙木 昌宏
Published by 学会事務局 on 10 6月 2019
Fabrication of in vitro functional tissues which can accurately model disease condition is required for efficient drug development. Although there are a lot of skeletal muscle related diseases, very few drugs for them have been developed so far. Kazunori Shimizu and Hiroyuki Honda have developed 96 well formatted microdevices for fabricating tissue-engineered human contractile skeletal muscle and applied them to model disease condition such as skeletal muscle atrophy. A ribbon-shaped skeletal muscle tissue with a lot of myotubes is formed between two micro-posts. When the tissue generates a contractile force by electric stimulus, the tip of the post (white circle) moves and the contractile force can be quantified by its displacement.
This image was taken by Nao Yamaoka and Saki Ohsumi at Honda’s laboratory in Nagoya University (http://www.nubio.nagoya-u.ac.jp/proc/index_english.html).
(© 2019 The Society for Biotechnology, Japan).
⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号
⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)
Published by 支部:中部 on 06 6月 2019
日時:2019年8月6日(火)13:00~17:40(交流会 18:00~20:00)
場所:じゅうろくプラザ(岐阜市橋本町1丁目10番地11)
http://plaza-gifu.jp/access/
参加費:講演会 無料
交流会参加費(税込)一般3,000円、学生1,500円(予定)
《特別講演》
《若手研究者による講演》
準備の都合上、講演会および交流会への参加を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。
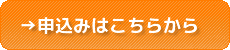
問合せ先:中部支部庶務幹事 中川智行 E-mail
Published by 部会:バイオインフォマティクス on 05 6月 2019
この度バイオインフォマティクス相談部会は、2019年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー(2019年7月20日 滋賀県高島市)におきまして、共催企画として「バイオインフォマティクス出張相談窓口」を開催いたします。企画は会期中に同会場内で行いますので、夏のセミナーの参加者はどなたでもご参加頂くことができます。奮ってご参加下さい。
バイオインフォマティクス出張相談窓口 開催概要
【問合せ先】バイオインフォマティクス相談部会
理化学研究所・生命機能科学研究センター
堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp
バイオインフォマティクス出張相談窓口は、2019年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナーの共催企画として、2019年7月20日-21日に滋賀県高島市にて開催しました。開催にあたり、実行委員長の青木航先生(京都大学)をはじめとする実行委員の先生方にご協力を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。
当日の様子


会場では、ポスター発表時に部会のポスターを掲示して部会委員が説明をおこなったほか、「たすき」をかけた部会委員が随時相談や説明に応じました。
Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 03 6月 2019
脂質駆動学術産業創生研究部会代表
徳島大学大学院社会産業理工学研究部
櫻谷 英治
脂質研究領域のさらなる発展には多様な学術分野の融合と新規概念の導入が必要と考えられます。すなわち、新規機能性脂質の創出、脂質・脂質代謝物の正確なリピドーム解析、脂質代謝産物を介したヒト(細胞)と腸内細菌の相互作用解明、細胞への脂質の輸送と生理学的機能解明、機能性脂質の物性評価と合成技術開発などが重要となります。本研究部会では、脂質と脂質代謝物を鍵化合物とした新たな機能の開拓に基づき、産業の創出を駆動することを目指しています。これからの脂質研究に関する情報交換、産学官交流にご興味をお持ちの方に、毎年開催の講演会を中心とした本研究部会の活動に、ご参加いただければ幸いです。
【日時】2024年10月4日(金)
【場所】北海道大学 工学部 フロンティア応用科学研究棟2階レクチャーホール(鈴木章ホール)
(世話人:北海道大学・菊川寛史)
⇒詳しくはこちら
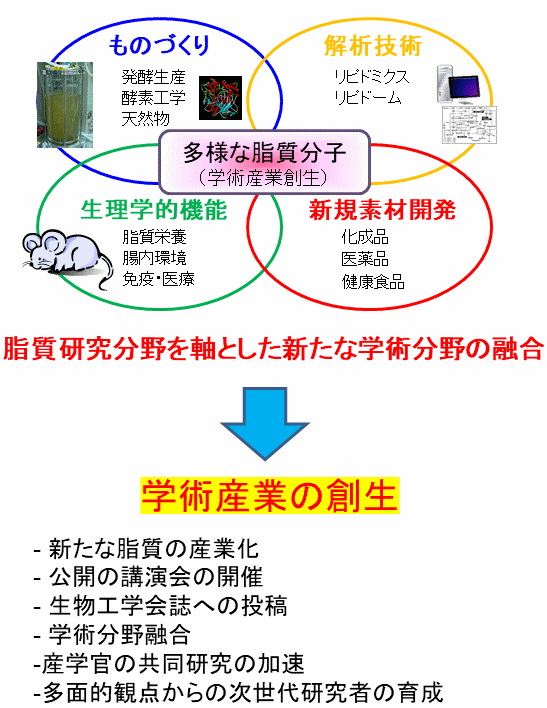
| 代表 | 櫻谷 英治(徳島大・生物資源・教授) | |
|---|---|---|
| 委員 | 岸野 重信(京大院・農・准教授) | 安藤 晃規(京大院・農・助教) |
| 竹内 道樹(京都工繊大・分子化学・助教) | 菊川 寛史(北大院・工・准教授) | |
| 和泉 自泰(九大・生医研・准教授) | 高橋 政友(九大・生医研・助教) | |
| 中谷 航太(九大・生医研・助教) | 渡邉 研志(広島大院・統合生命・助教) | |
| 雜賀 あずさ(産総研) | ||
| オブザーバー | 小川 順(京大院・農) | 永尾 寿浩(大阪技術研) |
| 秋 庸裕(広島大院・統合生命) | 角田 元男 | |
| 岩崎 雄吾(中部大・応用生物) | 馬場 健史(九大・生医研) | |
| 杉森 大助(福島大院・理工) | ||
徳島大学大学院社会産業理工学研究部
生物資源産業学域
櫻谷 英治
E-mail
| 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 次世代植物バイオ研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | バイオインフォマティクス相談部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 脂質駆動学術産業創生研究部会 | 非線形バイオシステム研究部会 | 培養技術研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)|
Published by 学会事務局 on 03 6月 2019
会員の皆様からご推薦いただきました候補者から受賞候補者選考委員会にて選考を行い、2019年5月23日(木)の理事会にて本年度の学会賞受賞者が決定しました。
授賞式は第71回日本生物工学会大会の初日に開催されます。
【日時】2019年9月16日(月・祝)9:00~9:50
【会場】岡山大学 創立50周年記念館(金光ホール)
注)所属は推薦・申請時のもの。
伊藤 伸哉(富山県立大学工学部)
「新規酸化還元系バイオプロセスの基盤技術開発とその応用」
紀ノ岡 正博(大阪大学大学院工学研究科)
「再生医療に資する細胞製造性に関する研究」
今井 泰彦(キッコーマン(株))
「未来社会を先導する技術開発研究の実現を目指した産学連携活動への貢献」
伊藤 一成(岡山県工業技術センター)
「無通風箱培養法を利用した固体培養における麹菌の生育と酵素生産に関する研究」
佐々木 建吾(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科)
「持続可能・健康社会の構築に向けた複合微生物系の制御」
杉浦 慎治(産業技術総合研究所)
「圧力駆動型Microphysiological systemsの開発」
小原 聡1・寺島 義文2・杉本 明3・福島 康裕4・菊池 康紀5
(1アサヒクオリティ&イノベーションズ(株),2国際農林水産業研究センター,3サトウキビコンサルタント,4東北大学,5東京大学)
「選択的発酵酵母を利用した砂糖・バイオエタノール逆転生産プロセスの開発」
Li Tan (Chinese Academy of Sciences, China)
“Recycling of municipal solid waste via ethanol and/or methane fermentation”
Han Xiao (Shanghai Jiao Tong University, China)
“Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for efficient biosynthesis of antitumor ganoderic acid HLDOA”
Published by 学会事務局 on 03 6月 2019
*はCorresponding authorを示す。 所属は論文掲載時のもの
Published by 学会事務局 on 01 6月 2019
2019年6月1日より、神谷典穂教授(九州大学)が編集委員長に就任し、英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) 編集委員会の新体制が発足しました。⇒JBB Editorial Board
加藤純一前編集長のリーダーシップのもと、2017年に発表されたJournal Citation Reports2016でJBBのIFは過去最高の2.24を記録しました。英文誌編集委員会では、今後もJBBのさらなる飛躍を目指して編集委員一同努力してまいります。JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。
【新編集委員】(敬称略)
Published by 支部:関西 on 22 5月 2019
| 日時 | 2019年5月20日(月)13:00 ~16:45 |
|---|---|
| 場所 | 大阪府立大学I-siteなんば(大阪市浪速区敷津東2-1-41 南海なんば第一ビル2階) |
| 日時 | 2019年8月30日(金)13:00~19:00 |
|---|---|
| 場所 | 関西大学 千里山キャンパス 第4学舎4号館4201教室(大阪府吹田市山手町3丁目3番35号) |
| 日時 | 2020年(令和2年) 1月31日(金)13:30~18:30 |
|---|---|
| 場所 | 講演会・懇親会:沢の鶴本社ビル5階ホール(兵庫県神戸市灘区新在家南町5丁目1番2号) 見学会:沢の鶴 醸造蔵 瑞宝蔵および資料館(兵庫県神戸市灘区大石南町1丁目29番1号) |
一瀬 涼(関西大院)
受賞課題:乳酸菌の高密度培養のための好気的流加培養による乳酸生産の抑制
丸山 正晴(大阪大院)
受賞課題:時系列メタボローム解析による代謝応答の解析に関する研究
湯川 貴弘(神戸大)
受賞課題:出芽酵母における鉄代謝工学の開発と新規キシロース同化経路構築への応用
♦関連記事:【関西支部】2019年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い
Published by 学会事務局 on 22 5月 2019
『生物工学会誌』97巻5号(2019年5月25日発行)に以下の誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていただきます。
バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)
「微生物が誘ってくれた豊かで充実した研究人生(山下 道雄 著)」
・p. 287 著者紹介欄
誤)東京大学大学院医学系研究科専攻
正)東京大学大学院医学系研究科(“専攻”不要)
・p. 295 略歴欄
誤)東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻生物医化学専攻
正)東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻生物医化学教室
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 支部:関西 on 22 5月 2019
生物工学分野の研究者・技術者にとって『培養』は日常的に行う操作のひとつです。しかし、それを支える理論と技術は奥が深く、基本をおろそかにすると微生物や細胞の能力をうまく引き出すことも、効率の良い生産をすることもできません。今回の懇話会では、培養制御の基礎理論から工業スケールでの実践的な応用例まで、第一線の研究者・技術者にご講演頂きます。
12:30~ 受付
13:00~13:05 開会の辞 藤山 和仁(関西支部支部長・大阪大学生物工学国際交流センター)
13:05~13:35
「培養工学の基礎知識」片倉 啓雄(関西大学化学生命工学部)
培養を効率化するために必須な(1)比速度の概念と求め方、(2)菌体・生産物・基質および溶存酸素の濃度の変化速度式、(3)菌体収率と生産物収率、(4)流加培養の基本式とその意義を分かり易く解説する。
13:35~14:05
「流加培養の乳酸菌培養への応用」片倉 啓雄(関西大学化学生命工学部)
流加培養は高濃度培養を可能にし、グルコースリプレッションを回避できるなどの特徴がある。工業生産における基本技術でもある流加培養を利用した乳酸菌と酵母の混合培養と、乳酸菌の高濃度培養を紹介する。
14:05~14:35
「種々の発酵製品と生産技術開発」神田 彰久(株式会社カネカ R&B企画部)
微生物を利用した発酵製品は食品から医薬品、化学品まで多種多様であり、工業生産にあたっては様々な問題が生じる。ここでは、好気培養のスケールアップも含め、その対応策や今後の技術への期待について述べる。
14:35~14:50 休憩
14:50~15:20
「Value creation by fermentation technology」児島 宏之(味の素株式会社)
生体に不可欠のものである必須アミノ酸は人、動物等では生合成できず外部から取り入れる必要がある。必須アミノ酸を中心とするアミノ酸の微生物を用いた発酵生産の技術を振り返り、発酵工学の将来に向けての課題を考える。
15:20~15:50
「バイオ医薬品生産における動物細胞培養 これまでとこれから」大政 健史(大阪大学大学院工学研究科)
抗体医薬の市場は飛躍的に増加し、世界Top10医薬品の売上げの約7割を占めている。本講演では、抗体医薬を中心に動物細胞培養技術について微生物と動物細胞の相違点、最近のトレンドなど、わかりやすく紹介する。
15:50~16:10 休憩
16:10~16:40
パネルディスカッション「培養工学の未踏のフロンティア」
産業界でニーズがあるにも関わらず、培養をきちんと教えている大学が少なくなっている。生物工学の他の分野に比べて、培養は技術・知識の体系化が進んでしまったがゆえに、ハイインパクトな論文が出しづらく、競争的資金もとりづらいことが一因かもしれない。そこで、このような現状について討論するとともに、培養の分野に未着手のフロンティアが残されているとすれば、それはどのようなものかを考えたい。
16:40~16:45 閉会の辞 大政 健史(関西支部副支部長・大阪大学大学院工学研究科)
17:00~19:00 懇親会
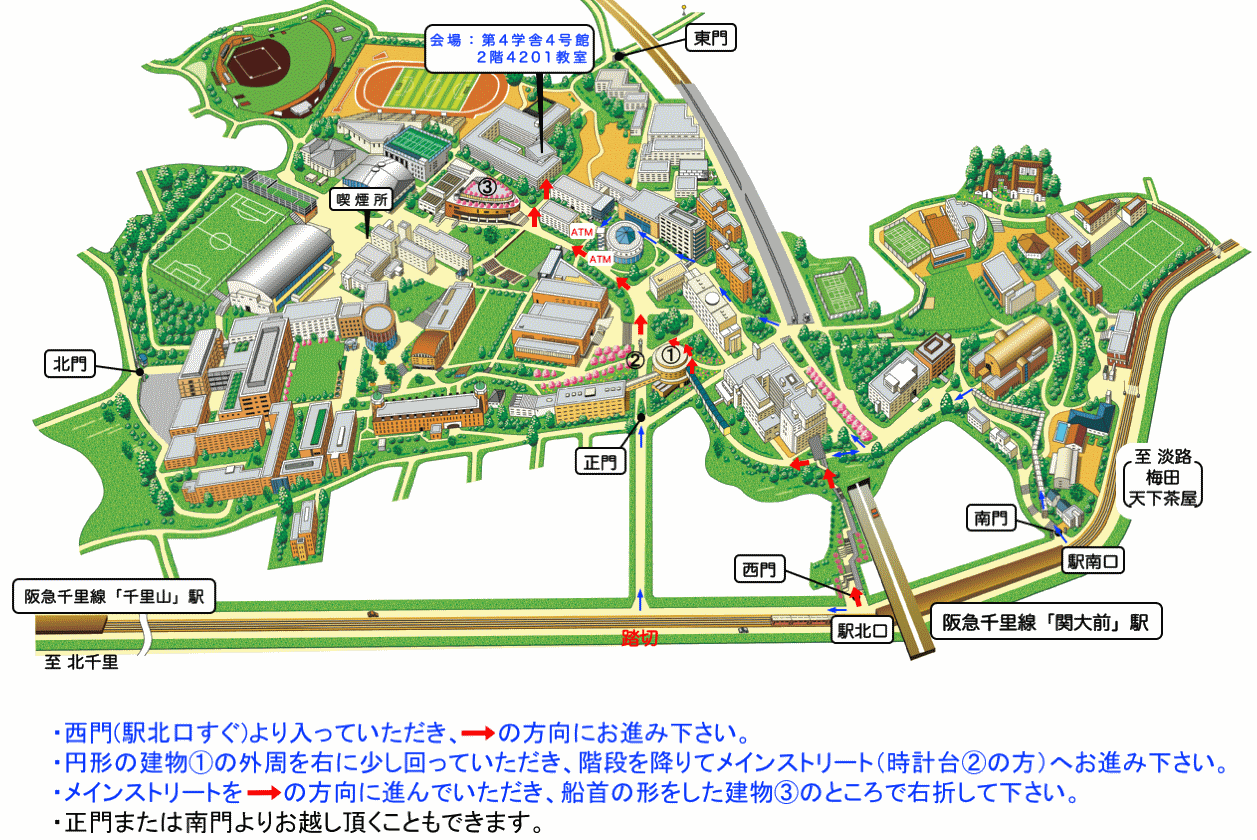
Published by 学会事務局 on 22 5月 2019
生物工学会誌 第97巻 第5号
太田 明徳
私は1971年6月30日卒業という、明治初期の大学9月入学時代のような履歴を持つ大学紛争世代の一員である。大学ストライキ、すなわち学生による授業放棄と大学の封鎖が始まったのは教養学部の2年次学生の時の7月頃であり、翌年1月のストライキ解除まで、長期の無為の期間を過ごしていた。それだけの期間があれば有意義に過ごすことができそうなものであるが、いつストライキが終わるかわからないので、結局、日時が経過するままであった。喫煙という悪癖に馴染んだのが後遺症で、30才直前まで止められなかった。
なんとか無事に学部に進学できたのは、紛争収束のために、さらにいい加減になった単位認定のおかげと思う。農学部農芸化学科に進学したが、この学科を選んだ理由は、微生物に惹かれたためと、受験時にお世話になった家の子息がビール会社の社員で、学科の先輩であったことである。進学決定後は慌ただしく2年次後半と3年次の短縮された課程を済ませて、卒業研究の研究室に配属された。微生物に関心を持ったのならば、伝統があり、人脈も豊かな研究室を選べば良かったのであるが、当時の私はうかつにも卒業研究の研究室の選択によってその後の人生が大きく左右されるなんて思いもしなかった。単純に酵素学が新鮮で先端的な学問分野に思われたので、今堀和友教授の酵素学研究室を志望したのである。
今の私は学生たちに、目指す分野を真剣に考え、調査することを勧めている。若い未熟な人間が慎重に考えても、必ずしも思うようにはならない。しかし、最上の選択ではなくとも人生に対して肯定的で積極的であるかぎり、有意義な人生を送ることができるであろう。どのような分野が自分に向いていて、おもしろいか、また重要であるかということを懸命に考え、選択することが、自分の人生を生きるということでもある。私自身はあまり流れに逆らわず生きてきたように思うが、同時にそのことによって研究者として失ったものも多かったのではないかと振り返ることがある。良い研究者であるということと円満な人生を送ることとはあまり関わりがない。時に研究者となることを人に勧めることにためらいを感ずるのは、それが人生に大きなひずみを生ずることがあるからである。
今堀教授は教養学部基礎科学科の助教授から農芸化学科教授に異動して来られ、私は2代目の農芸化学科卒論生であった。研究室には教授についてきた基礎科学科の優秀な大学院生がいて、農芸化学科の卒論生には必ずしも馴染みやすい雰囲気ではなかった。博士課程院生のなかにはノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先生がいたのであるが、先生は自ら望んで京都大学にいてほとんど不在であり、酵母研究の仲間としておつきあいが始まるのは10年近く後のことである。当時の今堀研究室では助手2名が留学中で、残る当時の太田隆久助教授、大島泰郎助手、そして私を指導した松澤洋助手は、てんでに自分の持ち込んだ研究をしていた。私はこれが当たり前の大学の研究室だと思っていたが、今時の研究室とはだいぶ違ったようである。
卒業研究では松澤助手が分離した大腸菌の形態変異(短桿菌が丸くなる)に関する遺伝学を始めることになったが、酵素学とは関わりのないこのテーマは私に合っていたらしく、楽しかった。今堀研究室の当時の酵素学は一種の分光学で、酵素の円偏光二色性の測定により、酵素の構造を調べる仕事が中心であった。これにはあまり興味が持てず、旋光の数式にも困惑していたので、松澤先生についたのは私にとってまことに幸運なことであった。
後に分子生物学的な手法による研究に向かう大きな契機にもなった。卒論の発表会で今堀教授から、吸光度と濁度の混同を指摘されたが、これが唯一の教授からの直接の教えであった。酵素学研究室に卒論配属の希望をしながら、大学院では志望しなかったのであるが、その理由はもう一つある。当時の今堀研究室には、理学部生化学科の学生も卒論生として来ており、大学院生をチューターとしての「Enzyme Physics」(Volkenstein)の英語版を読む卒論生の読書会があった。そこで生化学科出身の卒論生が教養学部時代にロシア語の原書で読んだと言った。ストライキの期間を有意義に過ごした学生がいたのである。これで今堀研究室に残るという気持ちがきれいに消えてしまった。
結局、私はなんとなく自分に向いた世界に向かって進んでいたのだと思う。もし私が勤勉な勉強家で、当時の酵素学にまともに向き合っていたら、苦しかったに違いなく、博士課程を志望しなかっただろう。若者にとって研究は何より楽しくなくてはならず、新しい発見が伴えばもっと楽しい。楽しくない研究はやらない方が良いと今の私は言うことができる。
著者紹介 中部大学応用生物学部(教授)
Published by 学会事務局 on 20 5月 2019
日本プロテオーム学会(JPrOS)/日本電気泳動学会(JES)合同大会(フェニックス・シーガイア・リゾート、宮崎市)において、日本生物工学会バイオ計測サイエンス研究部会のサテライトワークショップを開催することになりました。本ワークショップでは、バイオ計測技術勉強会と題して、実際に計測を行う際に必要な技術を理解することを目的に、それぞれ計測技術の第一人者の先生にプロトコールを解説していただきます。
| 日時 | 2019年7月26日(金)14:40~17:10 |
|---|---|
| 会場 | フェニックス・シーガイア・リゾート シーガイア コンベンションセンター 会場2(天樹)(宮崎市) |
| プログラム |
|
| 参加登録について | こちらの申込方法 専用サイトにて登録をお願い致します。 |
| 参加申込締切日 | 2019年7月12日(金) |
| 参加費 | ワークショップの参加費は無料です。 ナイトセッションの参加希望者は、「ナイトセッションの参加希望」および「宿泊(必要・不要)」を追記ください(宿泊については先着順)。宿泊料は、コテージヒムカ:5000円、ラグゼーツ葉:7000円となります。 |
| 詳細URL | バイオ計測サイエンス研究部会HP https://www.sbj.or.jp/division/division_bio_analysis.html |
| 問合せ先 | 日本生物工学会 バイオ計測サイエンス研究部会 幹事 馬場 健史 E-mail: |
Published by 学会事務局 on 20 5月 2019
日本プロテオーム学会(JPrOS)/日本電気泳動学会(JES)合同大会(フェニックス・シーガイア・リゾート、宮崎市)において、日本生物工学会バイオ計測サイエンス研究部会共催のシンポジウムを開催することになりました。本シンポジウムでは、1細胞解析技術の開発に第一線で取り組んでおられる若手の先生方にご講演いただきます。
| 日時 | 2019年7月26日(金)8:50~10:50 |
|---|---|
| 会場 | フェニックス・シーガイア・リゾート シーガイアコンベンションセンター会場2(天樹)(宮崎市) |
| プログラム |
|
| 詳細URL | バイオ計測サイエンス研究部会HP https://www.sbj.or.jp/division/division_bio_analysis.html JPrOS/JES合同大会HP https://www.jhupo.org/2019/index.html |
| 演題登録期間 | 2019年4月14日 (日)~ 5月24日(金) |
| 参加登録について | <JPrOS/JES合同大会および懇親会に全日参加される方> 日本生物工学会会員は、後援団体会員としてJPrOS・JES会員と参加費は同条件で登録可能です。ただし、ポスター発表の資格はJPrOSまたはJES会員のみです。所属団体名をバイオ計測とし、生物工学会の会員番号入力で参加登録システム(https://www.jhupo.org/2019/registration.html)から登録できます。
<7月26日のみ参加の方> 申込方法 大会の参加登録システムではなく、こちらの専用サイトにて登録をお願い致します。
|
| 参加申込締切日 | 2019年7月12日(金) |
| 問合せ先 | 日本生物工学会 バイオ計測サイエンス研究部会 幹事 馬場 健史 E-mail: |
Published by 支部:関西 on 20 5月 2019
日本生物工学会関西支部では、2014年度より「啓発活動基金」を活用し、産学官の若手研究者の育成と国際化を目的としたワークショップ・シンポジウムを開催しています。
| 2014年度 | Workshop on Asian Brewery Technology(月桂冠) ⇒開催報告はこちら |
|---|---|
| 2015年度 | TSB2015「Current status of industrial biotechnology in Thailand and Japan」(タイ) ⇒開催報告 |
| 2016年度 | ICY14「Yeast Fermentation in Asia」(淡路島) ⇒開催報告 |
| 2017年度 | TSB2017「The special Thai-Japanese Biotechnology Joint Session on Enzyme Engineering for Industries」(タイ) |
| 2018年度 | 生物工学会「ASEAN における生物資源の社会実装を目指した研究ネットワーキング」<国際シンポジウム>(関西大学) |
| TSB2018「Bridging Research and Society’s Needs」(タイ) |
2019年度は6回目の企画として、タイ・プーケットで11月11、12日に開催予定のThai Society of Biotechnology(TSB)主催の国際シンポジウム(http://www.tsb2019.com/)でジョイントセッションの枠を主催者より頂戴しました。その演者を関西支部から招待したく、準備を進めています。
関西支部地域内の民間企業、研究機関、大学等に所属する研究者から、2-3名 の演者を派遣し、国際シンポジウムでの発表の機会を与えるとともに、タイを中心とする東南アジア地域におけるバイオテクノロジーの基礎・応用研究の現状を学ぶ機会にしたいと考えています。
つきましては、本企画の趣旨に賛同いただき、参加を希望される若手会員を募りたいと思います。下記の実施要領をご一読の上、奮って応募いただければ幸いです。なお、予算により演者数が変わることがあります。
Thai Society of Biotechnology(TSB)主催の国際シンポジウム(TSB2019)
The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference”Bridging Research and Society’s Needs”
【日時】2019年11月11日(月)・12日(火)
【場所】Duangjitt Resort & Spa, Phuket
http://www.tsb2019.com/
Published by 学会事務局 on 17 5月 2019
電源設備法定点検に伴うサーバー停止により、日本生物工学会のホームページおよび大会ホームページが以下の期間利用できなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、上記期間中も会員システム、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(EVISE)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。
Published by 学会事務局 on 24 4月 2019
こちらでは、生物工学会誌第97巻(2019年)掲載の特集記事一覧(PDF)をご覧いただけます。
⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら
第97巻|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|
Published by 学会事務局 on 23 4月 2019
こちらでは、生物工学会誌のシリーズ企画『間違いから学ぶ実践統計解析』の続編(全12回・隔月掲載)をご覧いただけます。
⇒『間違いから学ぶ実践統計解析』本編はこちら
| 著者 | 巻–号–頁 (掲載年) | ||
|---|---|---|---|
| 最終回 | 統計処理の落とし穴 | 松田 史生 川瀬 雅也 | 99-2-86 (2021) |
| 第11回 | p 値とサンプルサイズ | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-12-702 (2020) |
| 第10回 | 深層学習,すぐできます. | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-10-559 (2020) |
| 第9回 | 微妙な時のしきい値が肝心 | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-8-450 (2020) |
| 第8回 | 階層クラスター分析はちょっときまぐれ | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-6-328 (2020) |
| 第7回 | 偽反復 | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-4-206 (2020) |
| 第6回 | 主成分分析その2,結果を解釈する ⇒iris.csv | 松田 史生 川瀬 雅也 | 98-2-92 (2020) |
| 第5回 | 主成分分析その1,方法のおさらい | 松田 史生 川瀬 雅也 | 97-12-766 (2019) |
| 第4回 | Pythonによる統計入門2 ⇒metabolome.csv | 松田 史生 川瀬 雅也 | 97-10-629 (2019) |
| 第3回 | Pythonによる統計入門1 ⇒test1.csv | 松田 史生 川瀬 雅也 | 97-8-522 (2019) |
| 第2回 | Pythonの文法_分岐と繰り返し | 松田 史生 川瀬 雅也 | 97-6-360 (2019) |
| 第1回 | Python? | 松田 史生 川瀬 雅也 | 97-4-226 (2019) |
Published by 学会事務局 on 23 4月 2019
生物工学会誌 第97巻 第4号
宇多川 隆
産業界から大学へ、そして公設研究所と異なる文化の中で勤務する機会を得た。その間にバイオものづくりの研究・開発・生産に従事し、それぞれの立場でその面白さを経験してきたので一端を紹介する。
最初にバイオものづくりの面白さを知ったのは、入社して間もなく取り組んだ抗ウイルス剤の製法研究においてである。生産菌の探索を1年近く続けたが、ポジティブな結果がまったく得られず諦めかけていたところ、ある時、発酵(酵素反応)に使用していた培養器の温度が上昇するというトラブルに見舞われた。失敗かと思われたその発酵(反応)液を分析すると、なんと目的とする抗ウイルス性化合物(アデニンアラビノシド:Ara-A)が生成していたのである。生産の最適温度は60°Cにあり、室温まで冷却するとAra-Aの結晶がキラキラと出てきた。その時の感激は忘れられない。ヘルペスウイルスに効果的で、多くの関係者の尽力で工業化され、商品名アラセナAとして上市された。60°Cでは生産微生物の生育はおろか完全に死んでしまう。なぜ当該微生物は死ぬほどの温度で抗生物質を作るのか不思議であり、興味の尽きないところである。
他にも、高温で強い活性を示すアミラーゼやプロテアーゼなども中温微生物によって生産されることが知られている。生物の生育至適環境と酵素力価の至適条件が必ずしも一致しないところに生物触媒のスクリーニングの難しさと面白さがある。酵素活性の最適値の多様性は生物の進化と関係があるのかもしれない。一方、耐熱性DNAポリメラーゼは高温菌、アルカリプロテアーゼは好アルカリ細菌が生産するように生育環境と酵素の活性発現至適条件が一致するものは数多く知られている。
その後、地域資源をバイオの力で有効に活用するという研究に携わることになった。漁業が盛んな地域では、魚加工場から大量の副生物(アラ)が生成し、その多くは有償で廃棄されている。この副生物には良質なタンパク質とそれを分解する酵素が含まれている。分解酵素の最適温度は55°Cにあり、タンパク質は速やかに分解されてアミノ酸を遊離する。この性質を利用すると、魚加工副生物から短時間で魚醤を生産することができる。サバやブリの加工副生物を原料にした場合、1~3日で発酵が完結し、精製して得られる魚醤は旨味を呈していることから調味料として販売するに至っている。廃棄されていた副生物を短時間で有用物に変換するバイオの力に感動である。55°Cではサバやブリは生存できないが、体内の酵素が生きているところに生物の驚異を感じる。
高温発酵では速度が速くなるだけでなく、雑菌の生育がほとんど認められないので、都合の悪い化合物が副生しないことも大きな利点である。雑菌が汚染すると、Ara-A生産の場合アデニン部位がヒポキサンチンに分解されて抗ウイルス活性は弱くなる。魚醤では、ヒスチジンが分解されてアレルギー物資であるヒスタミンが生成する。
有用物質の生産研究において微生物などをスクリーニングする場合、中性・常温条件で実験することが多いが、温度やpHなどの条件を大胆に変えてみると、思いもよらない新しい反応や物質の発見につながる可能性がある。
現在の地球上に生存する生物は、過去のさまざまな環境を生き延びてきた生物の末裔であり、過去の過酷な環境に対応してきた能力がその遺伝子の中に隠されていると考えられる。この能力を引き出し、有用物質の生産に利用することは、バイオによるものづくり研究者の重要なミッションである。
常識にとらわれず、だれもが思いつかないような条件において発現される生物の力を利用し、有益なものを生産するバイオものづくりの面白さを味わってほしい。
著者紹介 福井県食品加工研究所(特別研究員)
Published by 学会事務局 on 23 4月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 学会事務局 on 22 4月 2019
井藤 彰
2018年度生物工学奨励賞(照井賞)受賞者
九州大学大学院工学研究院(受賞時)
2019年4月11日~12日にかけて韓国済州島(Jeju)のMaison Glad Jeju Hotelにおいて、韓国生物工学会(Korean Society of Biotechnology and Bioengineering; KSBB)の2019年春季大会(2019 KSBB Spring Meeting and International Symposium)が“Biotechnology from the Nature to Human Life”という大会スローガンで開催された。日本生物工学会(The Society for Biotechnology, Japan; SBJ)からは、2018年度「生物工学功績賞」の清水浩先生(大阪大学)と「生物工学奨励賞(照井賞)」の筆者が招待され、講演を行った。
済州島は朝鮮半島の南に位置する風光明媚な観光地であり、道路には椰子の木が立ち並び、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドが軒を連ねることから「韓国のハワイ」とも言われるが、 学会当日は気温が低く、韓国の先生方も寒さに少し驚いていた。その日は4月にして東京でも積雪があったので、特別寒かったと思われる。学会会場であるホテルまでは、ホテルのシャトルバスで空港から15分ほどの便利なロケーションだった。

KSBBの春季大会は昨年から2日間プログラムで行われている。6題の全体講演と20件のシンポジウム、784題のポスター発表が行われた。シンポジウムのうち、7つのセッションが国際シンポジウムになっており、バイオセンサーとバイオチップ[台湾生物工学会(Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan; Best)とのジョイントシンポジウム]、ナノバイオセンシングとセルエンジニアリングI、ナノバイオセンシングとセルエンジニアリングII、ティッシュエンジニアリングと再生医療、酵素工学、システムバイオロジーと合成生物学、漢方の科学と工学がテーマとなっていた。
清水先生はシステムバイオロジーと合成生物学のセッションで基調講演を、筆者はティッシュエンジニアリングと再生医療のセッションで招待講演をそれぞれ行った。他の日本人としては、味の素がランチョンセミナーを開催しており、ES/iPS細胞用の培地の紹介のほか、現地で立ち上げられたAjinomoto GenexineによるCHO細胞用の培地最適化事業が紹介された。ランチョンセミナーには珍しく、お弁当ではなく、温かいプルコギ定食がシンポジウム参加者全員に供された。他にも、バイオエネルギー、微生物による物質生産、タンパク質工学などのテーマが設定され、約150件の口頭発表が行われた。
1日目の夜にレセプションが開かれ、SBJのメンバーである清水先生と筆者はBESTのメンバー三名とKSBBの国際連携担当の先生方とテーブルを共にした。テーブルには多くのKSBBの先生に訪れて頂き、お酒を酌み交わしながら懇談する機会を頂いた。特に、シニアの先生方が、SBJの発展とKSBBとの交流に尽力されたSBJのシニアの先生方のお名前を出してお話されるのを聞き、SBJとKSBBの交流の歴史を実感した。レセプション後は二次会にお誘い頂き、さらに密な交流を深めるとともに、今年のSBJの年次大会は岡山で、KSBBの秋季大会は韓国大邱(Daegu)で行われる旨、情報交換した。
末筆ながら、今回のKSBB訪問をご支援いただきましたKSBB会長のHei Chan Lee先生(Sun Moon University)をはじめ、国際連携ご担当のJong Wook Hong先生(Hanyang University)、Seung Pil Pack先生(Korea University)、筆者の講演の座長を務められ、会期中温かくお世話頂いたKye Il Joo先生(POSTECH)、KSBB事務局のHye Won Kho氏に厚く御礼申し上げます。また、今回貴重な機会を頂きましたSBJ国際展開委員長の跡見晴幸先生とSBJ事務局の皆様、SBJの先生方に厚く御礼申し上げます。

懇親会会場にて
<台湾生物工学会(BEST)の講演者と同じテーブルを囲んで>
左から、Prof. Seung Pil Pack (Korea Univ.) 、Prof. Jae-Hyung Jang (Yonsei Univ.) 、
Prof. Hee-Jin Jeong (Hongik Univ.)、Prof. Hyung Joon Cha (POSTECH)、
Prof. Chun Jen Huang (Nat’l Central Univ., Taiwan)、筆者、清水浩先生、
Prof. Ho Hsiu Chou (Nat’l Tsing Hua Univ., Taiwan)、
Prof. Hsing-Wen Sung (Nat’l Tsing Hua Univ., Taiwan)
♦関連記事:【国際交流】韓国生物工学会(KSBB)大会参加報告
Published by 学会事務局 on 08 4月 2019
第71回日本生物工学会大会(2019)の一般講演、およびシンポジウム要旨登録の受付を開始しました。
締切以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。
本年度の一般講演はすべて口頭発表形式で行います。
一般講演(口頭発表)の発表者は2019年会費既納の本会正会員または学生会員に限ります。講演申込みには発表者の会員番号が必須となり、会員番号がない場合には登録できません。事前に必ず入会手続きをお願いします。会員番号は入会登録と会費の入金確認ができ次第お知らせしますが、1週間程度かかりますので早めの手続きをお願いします。⇒入会はこちらから
Published by 支部:北日本 on 02 4月 2019
Published by 支部:北日本 on 02 4月 2019
14:00~14:05
開会の辞………魚住 信之(日本生物工学会北日本支部 支部長)
14:05~14:30
「バイオスティミュラント資材の現場での取り組みについて」
………………高谷 憲之(株式会社 ハイポネックスジャパン)
14:30~14:55
「機能性液肥、微生物資材を含めた現場での活用例」
………………高木 篤史(株式会社 サカタのタネ)
休憩
15:10~15:35
「微生物、薬剤、鉄鋼スラグを組み合わせて植物の病気を防ぐ」
………………今崎 伊織(農研機構東北農業研究センター)
15:35~16:00
「植物の鉄の吸収メカニズムに適合させた農業資材」
………………鈴木 基史(愛知製鋼株式会社)
休憩
16:15~16:40
「農業分野を中心とした、トレハロースの研究と開発の取り組み」
………………大垰 勝寛(株式会社 林原)
16:40~17:05
「気孔開閉と根長の制御をめざした植物イオン輸送体の活性化剤・阻害剤の探索」
………………魚住 信之(東北大学大学院工学研究科)
17:05~17:10
閉会の辞………松本 謙一郎(日本生物工学会北日本支部 副支部長)
17:40~ 懇親会(東北大学青葉記念会館「レストラン四季彩」、TEL. 022-711-2350)
Published by 学会事務局 on 01 4月 2019
| 内容 | 開催日 |
|---|---|
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「転機に立つ日本のイネ育種」〈東京〉 | 2019.03.20 |
| 【協賛行事】第14回理研「バイオものづくり」シンポジウム〈和光市〉 | 2019.03.08 |
| 【協賛行事】熱測定スプリングスクール2019(第82回熱測定講習会)~熱測定の基礎,測定データ解析,解釈法まで系統的に学ぶ~〈東京〉 | 2019.03.07-8 |
| 【協賛行事】サイエンス友の会特別教室「微生物がパンを作る! 筑波大学で微生物実験&見学会」〈つくば市〉 | 2019.03.02 |
| 【協賛行事】18-3 エコマテリアル研究会 「プラスチックの取り巻く環境を俯瞰する 」〈東京〉 | 2019.03.01 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「口腔ケア革命」〈東京〉 | 2019.02.19 |
| 【協賛行事】平成30年度 産総研 材料・化学シンポジウム 「21世紀の化学反応とプロセス-SDGsの推進に資する化学技術と材料-」〈つくば市〉 | 2019.02.08 |
| 【協賛行事】GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向:講演会&見学会」〈大阪〉 | 2019.02.07-8 |
| 【協賛行事】第11回大阪大学国際医工情報センター 国際シンポジウム「再生医療に資する細胞製造」〈大阪〉 | 2019.02.04 |
| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会 公開講演会「バイオ×デジタル(AI・IoT)」~バイオ産業におけるデジタルトランスフォメーション~〈東京〉 | 2019.02.01 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「核酸医薬開発の動向と課題」〈東京〉 | 2019.01.30 |
| 【協賛行事】第24回高専シンポジウム in Oyama〈栃木〉 | 2019.01.26 |
| 【協賛行事】第36回コロイド・界面技術シンポジウム「ブレークスルーを生み出す次世代コロイド界面技術」〈東京〉 | 2019.01.24-25 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「微生物・覚醒」〈東京〉 | 2018.12.17 |
| 【協賛行事】第31回バイオエンジニアリング講演会〈郡山市〉 | 2018.12.14-15 |
| 【協賛行事】SCIS&ISIS 2018 (Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems〈富山〉 | 2018.12.05-8 |
| 【協賛行事】第45回炭素材料学会年会〈名古屋〉 | 2018.12.05-7 |
| 【協賛行事】第31回イオン交換セミナー「イオン交換の基礎と応用(無機イオン交換体、イオン液体、原子力化学)」〈東京〉 | 2018.11.30 |
| 【後援行事】第三回国際シンポジウム「コメとグローバルヘルス~コメとコメ糠の科学~」〈京都〉 | 2018.11.29-30 |
| 【協賛行事】第38回水素エネルギー協会大会〈東京〉 | 2018.11.28-29 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「カフェと健康長寿~機能性、コホート研究から商品設計まで~」〈東京〉 | 2018.11.26 |
| 【関連行事】TSB2018“Bridging Research and Society’s Needs“〈タイ〉 | 2018.11.22-23 |
| 【協賛行事】日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 第6回分散凝集科学技術講座「分散・凝集のすべて」~希薄系から濃厚系までのあらゆる分散・凝集現象に関わる研究者・技術者のための最新理論とテクニック~〈東京〉 | 2018.11.15-16 |
| 【協賛行事】第32回日本吸着学会研究発表会〈大阪〉 | 2018.11.08-9 |
| 【協賛行事】第54回熱測定討論会〈横浜〉 | 2018.10.31-11.02 |
| 【協賛行事】第35回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2018〈東京〉 | 2018.10.29-11.01 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「結晶が変える未来社会」〈東京〉 | 2018.10.26 |
| 【協賛行事】18-2 エコマテリアル研究会「生物がつくる多様なバイオポリマー」〈京都〉 | 2018.10.19 |
| 【協賛行事】18-4 ポリマーフロンティア21「持続可能社会のためのバイオベース素材の現状と展望」〈東京〉 | 2018.10.16 |
| 【協賛行事】未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(43) 「高圧力科学技術の未来を拓く新発見・新技術」 〈東京〉 | 2018.10.12 |
| 【協賛行事】未踏科学技術協会 特別講演会 量子計算利用シリーズ 第2回「量子ハードウェアのビジネス利用」~量子コンピュータ・量子アニーラーは何に使えるのか~」〈東京〉 | 2018.10.10 |
| 【協賛行事】第16回高付加価値食品開発のためのフォーラム「オルガネラから考える抗老化~食とえいようがかかわれるか?~」〈静岡〉 | 2018.09.28-29 |
| 【協賛行事】第69回コロイドおよび界面化学討論会「分散系、凝集、ソフトマターの科学」〈つくば市〉 | 2018.09.18-20 |
| 【後援行事】第10回日中醸造・食品・栄養・環境シンポジウム(第2回日中伝統食品創新フォーラム)〈四川省成都市〉 | 2018.09.13-15 |
| 【関連行事】第22回酵母合同シンポジウム「アジアへのゲートウェイ九州から発信する酵母の魅力!」〈福岡市〉《日本生物工学会九州支部共催》 | 2018.09.12-13 |
| 【後援行事】JASIS2018〈千葉〉 | 2018.09.05-7 |
| 【協賛行事】第20回日本感性工学会大会「創造的多様性 (Creative diversity)」〈東京〉 | 2018.09.04-6 |
| 【協賛行事】第34回ファジィシステムシンポジウム(FSS2018)「Human + Fuzzy = Humane」〈名古屋〉 | 2018.09.03-5 |
| 【協賛行事】第31回におい・かおり環境学会〈千葉〉 | 2018.08.30-31 |
| 【共催行事】第37回日本糖質学会年会〈仙台〉 | 2018.08.28-30 |
| 【共催行事】第32回日本キチン・キトサン学会大会/14th International Chitin and Chitosan Conference (14th ICCC) / 12th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (12th APCCS)〈大阪〉 | 2018.08.27-30 |
| 【協賛行事】第81回熱測定講習会~明日から使える!材料・環境・医薬・バイオ分野の熱測定初心者・ユーザー向け基礎講義&実習~〈京都〉 | 2018.08.23-24 |
| 【協賛行事】 微生物科学イノベーション連携研究機構・発足記念シンポジウム「微生物科学の新たな学知創出をめざして」〈東京〉 | 2018.08.21 |
| 【協賛行事】極限環境生物学会シンポジウム・日本Archaea研究会講演会合同大会〈神戸〉 | 2018.08.03-4 |
| 【協賛行事】18-1 エコマテリアル研究会 「バイオベースマテリアルをつくろう・つかおう」〈東京〉 | 2018.07.20 |
| 【協賛行事】日本学術振興会 先導的研究開発委員会「食による生体恒常性維持の指標となる未病マーカーの探索戦略」公開シンポジウム〈東京〉 | 2018.07.20 |
| 【協賛行事】スマートエンジニアリング TOKYO 2018〈東京〉 | 2018.07.18-20 |
| 【後援行事】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2018〈仙台〉 | 2018.07.15 |
| 【協賛行事】第25回旬の技術・見学講演会「酵素の新たな産業応用への挑戦とクラフトビール醸造所見学会」〈埼玉〉 | 2018.07.13 |
| 【協賛行事】大阪工研協会 バイオ実習セミナー ―微生物・細胞取扱いと検査・試験の基本操作―〈大阪〉 | 2018.07.06, 2018.07.09 |
| 【後援行事】早稲田地球再生塾(WERS)第1回勉強会「SDGs推進のための建築物の脱炭素化と新しい緑のデザイン-ZEB/ZEHの動向、自然エネルギー、バイオフィリックデザイン-」〈東京〉 | 2018.07.06 |
| 【後援行事】第15回日中韓酵素工学会議(酵素工学研究会第79回講演会、40周年記念シンポジウム合同)〈京都〉 | 2018.06.30-07.01 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会 「”未来へのバイオ技術”勉強会「東京五輪への課題シリーズ:魅力的で安全・安心な食の提供に向けて」〈東京〉 | 2018.06.29 |
| 【関連行事】日本油化学会 東海支部 油化学セミナー「油脂・脂質の機能性と応用」〈名古屋〉《日本生物工学会中部支部協賛》 | 2018.06.29 |
| 【共催行事】第39回動物細胞工学シンポジウム「バイオ医薬品の高品質化に向けた物性解析」〈東京〉 | 2018.06.15 |
| 【協賛行事】 “未来へのバイオ技術”勉強会「筋肉修復に向けた先進医療の可能性」〈東京〉 | 2018.06.11 |
| 【後援行事】第86回日本醤油研究発表会〈東京〉 | 2018.06.08 |
| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「接ぎ木で産業革命を興す!」〈東京〉 | 2018.06.05 |
| 【協賛行事】第20回マリンバイオテクノロジー学会大会〈宮崎〉 | 2018.05.26-27 |
| 【協賛行事】第25回HAB研究機構学術年会「人体模倣システムを用いた創薬研究基盤技術の新基軸」〈つくば市〉 | 2018.05.24-26 |
| 【協賛行事】バイオプロセス講演・見学会「高度化するバイオ医薬品生産技術—グローバル化、連続生産、少量多品種生産—」〈東京〉 | 2018.05.17-18 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「育てる!バイオと水産業2~ウナギとマダイの明日」〈東京〉 | 2018.05.16 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「感動、デザイン、センシング。」〈東京〉 | 2018.04.27 |
| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「先進遺伝子治療はどこまで行こうとしているか~エピゲノム疾患治療と脳神経再生医学」〈東京〉 | 2018.04.19 |
| 【協賛行事】第8回ポルフィリン-ALA学会年会〈東京〉 | 2018.04.14-15 |
| 【後援行事】早稲田地球再生塾(WERS)開設記念シンポジウム「知の結集から新たな再生の道を探る -日本版バイオエコノミーとSDGs推進-」〈東京〉 | 2018.04.06 |
Published by 学会事務局 on 01 4月 2019
盛会のうちに終了しました。多数のご参加ありがとうございました。⇒活動報告はこちら
「生物工学若手研究者の集い(若手会)」は、生物工学(生体分子工学、細胞組織工学、醸造・食品工学、代謝工学、生物化学工学、生物情報工学など)に関連した研究を行っている、全国の学生、ポスドク、若手企業研究者、若手教員の相互交流を目的とした団体です。この度、2019年の若手会夏のセミナー(合宿形式)を滋賀県高島市にて開催する運びとなりました。高島市は琵琶湖西岸に位置し、 その水辺景観は日本遺産に認定されています。また、京都へも近く、近隣には多数の世界文化遺産があります。
今年は第一線で活躍する研究者の特別招待講演や、参加者と講演者との座談会形式による交流企画、優秀賞つきのポスターセッションなど、参加者全員が主体的に発表し交流するイベントを企画しております。参加者の皆様が一泊二日でじっくりと熱い議論を行って有意義なつながりを作ることを支援致します。
教育機関、研究所、企業の若手研究者や学生の方々を含め、生物工学に興味のある皆様の多数のご参加を心よりお待ち致しております。
「理学研究者が行うタンパク質工学~アカデミアが目指すべき技術開発とは?」
……高木 淳一(大阪大学 蛋白質研究所)
「腸内フローラ検査サービスMykinso立ち上げからの4年間を振り返って」
……竹田 綾(株式会社サイキンソー)
「生物と機械の融合—心筋・電気器官その他を用いた独創デバイス—」
……田中 陽(理化学研究所 生命機能科学研究センター)
「ワイルドはセクシーである~夢のない研究なんてNGだぜ~」
……内藤 健(農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センター)
「特許出願する?しない?究極の選択!~そもそも発明って何?~」
……前田 治子(京都北山特許法律事務所)
「構造タンパク質の実用化への挑戦」
……村上 賢宏(Spiber 株式会社)
「製薬企業における生物工学出身者のキャリアパス」
……葛本 雅宣(塩野義製薬株式会社)
Published by 学会事務局 on 25 3月 2019
日本生物工学会では、定款に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を実施いたしました。
選挙結果を下記のとおりお知らせします。
♦ 関連記事:
【正会員の方へ】2019-2020年度代議員の選出について
Published by 学会事務局 on 25 3月 2019
生物工学会誌 第97巻 第3号
秦 洋二
日本生物工学会の始祖は、1923(大正12)年に設立された大阪醸造学会である。名前の通り、清酒醸造などの醸造・発酵分野が中心となった学会である。当時は国税収入の中に酒税が占める割合が2割近くに及び、酒造業の発展は安定な税収確保のためにも重要な課題であった。また単なる「お金」だけの問題ではなく、酒造りのテクノロジーは、当時の微生物学で解明するに非常に魅力的な研究対象であったに違いない。
酒造りにおいては、西洋に先んずること300年以上前から低温加熱殺菌法「火入れ」が導入されていたり、複数の微生物を巧みに操りながら清酒酵母のみを純粋に培養する技術「生もと」が確立されていたり、先人たちの努力により多くのテクノロジーが組み込まれていた。ただ、これら先人たちが苦労して発明したものについて、国際的には我が国が発明者になりえていない。低温加熱殺菌法の発明者は、火入れの完成から300年後のルイ・パスツールである。なぜか?それは、清酒製造におけるテクノロジーについて、その理屈が解明されていなかった点があげられる。ヨーロッパのような多民族で構成される地域においては、人種、言語が異なる相手を納得させるために「理屈」で説明することが要求される。まさしくパスツールは、低温加熱により混入する乳酸菌が死滅することを理屈で明らかにした。一方我が国のように、ほぼ単一民族で同一言語を使用する地域においては、理屈もさることながら「情緒」を含む人間同士の信頼関係で他人を説得することが多い。酒造りをはじめ、日本の伝統的技術においては、当時の世界に先んずる発明が多数見いだされているが、残念ながら理屈の解明がなされずに、その多くについて世界の中で発明者の名称は与えられていない。
このような「宝の山」であった清酒醸造技術を当時の最新の科学理論で次々と解明していった原動力が大阪醸造学会であった。大阪醸造学会の学会誌である『醸造學雑誌』の創刊号には、清酒醸造におけるさまざまな問題点を技術的に解決する論文はもちろんのこと、「清酒醸造上の持論」のような論説記事や、「南シナにおける酒類」といった国際色溢れた論文まで掲載されている。また同年は関東大震災に被災した年でもあり、下半期の学会誌には、「大震災と諸味仕込用タンク」といった時事に迅速に対応した記事も紹介されている。学会誌として、清酒醸造の技術的な学理の解明だけでなく、さまざまな分野で酒造産業の発展に貢献した雑誌であったことがうかがえる。
生物工学会は、4年後の2023年に創立100周年を迎える。醸造・発酵が中心となってスタートしたが、現在は生物化学工学として微生物が関係する幅広いプロセスに応用されるようになり、さらに酵素工学、動植物細胞工学とその研究対象が広がり、近年は生物情報工学など新しい分野との融合も図られ、幅広い研究領域を網羅する学会となった。設立当初の大阪醸造学会が対象とする産業分野が醸造・発酵産業に限られていたものが、いまでは食品産業はもちろんのこと、医薬、医療分野、環境分野など、学会が貢献すべき産業分野も大きく広がっている。かつての大阪醸造学会が酒造業の発展に大きく貢献したように、現在の生物工学会もその波及する産業界の発展に大いに貢献して欲しいと願う。そのためには何が必要か?その一つに「枠を超える」「壁を取り除く」ことがあげられる。『醸造學雑誌』が、学術誌として単なる技術・研究報告にとどまっていたならば、酒造業への影響力は限定的であったかもしれない。学術誌の枠を超え、酒造業の発展に必要な情報提供を進めたが故、業界への貢献度は飛躍的に向上したのではないだろうか。先述のように生物工学会が関係する研究領域は非常に多岐にわたっている。この多様な研究領域の枠を超えて、異業種の壁を取り除いて、さまざまな産業に貢献できる技術シーズを学会から発信し続けることを期待する。
著者紹介 月桂冠(株)総合研究所
Published by 学会事務局 on 25 3月 2019
![]()
PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。
Published by 支部:西日本 on 05 3月 2019
生物資源活用による地方創生(グローカルバイオ)研究部会の主催で、シンポジウムが開催されます。地域の生物資源の活用や,DIYバイオのようなバイオテクノロジーを利用した新しい動きなどに焦点を当てます。興味ある方は奮ってご参加ください。
Published by 学会事務局 on 01 3月 2019
日本生物工学会2019年代議員選挙の投票受付は、2019年3月1日(正午)をもって終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
Published by 学会事務局 on 01 3月 2019
第71回日本生物工学会大会(2019)のホームページを公開しました。大会サイトでは、2019年9月16日(祝・月)から18日(水)に、岡山大学津島キャンパスで開催される年次大会に関する情報を発信していきます。
講演要旨登録と大会参加申込のウェブ受付は、2019年4月8日(月)より開始いたします。
本大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
公益社団法人日本生物工学会
第71回年次大会(2019)ホームページアドレス
https://www.sbj.or.jp/2019/